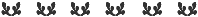|
 | |
|
『夕日が沈むのを見るのは嫌 夕日の沈むところなんか見たくない なぜって あの人がいなくなったからよ』 (『セントルイス・ブルース』/ビリー・ホリディ)
最後のほうは、兄はよく抱き締めてくれるようになっていた。 「兄さんだよ。わかるかい、兄さんだよ――」 兄はそう言って、膝立ちになってオレを抱き寄せ、大声を上げて泣き出した。オレは何が何だかわからなくて、ただただうろたえながら、泣きじゃくる兄の硬い髪をがむしゃらにかきまぜながら慰めようとしていた。昔の口約束を兄が憶えていてくれたことに驚いていた。鼻のあたりがむずむずした。単純に嬉しかったのと、それからなぜ今になって兄がそんなことを言い出したのかが全然わからなくて、戸惑っていたのだ。 オレが子どもの頃からずいぶん厳しい人だった兄は、いつも穏やかな笑顔を浮かべていて、見た目は優しげに見えた。ただ何物にも折れない芯の強さが、彼の潔癖を完全なものに造り上げていた。 オレが転んだ時もそうだ。彼はいつもの調子でゆっくりと歩き続けていて、手を貸してくれることはなく、頭を撫でてくれることもなく、慰めの言葉もなかった。つまり、一時期オレ自身でもどうにもならないくらいに困った事態に直面した時、彼は決して手を差し伸べたり、なにか気の利いたアドバイスをくれたりしたことはなかったのだ。 薄情なくらいの厳しさが、彼にしかできない優しさの表し方であることはわかっていた。子どもが大人に成長するまで、彼はたどたどしい足取りに辛抱強く歩調を合わせて歩き続け、ゴールへ導いてくれたのだ。おかげでオレはひとりでも大抵のことはこなせるようになったし、転んだ者の気持ちも良くわかった。馬鹿で自分本位の子どもだったオレには絶対に理解できなかっただろう、ある種綱渡りでもするような用心深さだって手に入れた。 兄がそんなふうになったのは突然過ぎて唐突で、オレには今でもよくわからない。ただ一度赦されると、今まで軽蔑を怖がってせき止めていた欲求の壁が一気に瓦解した。オレは兄に甘えた。ひたすら甘えて、甘えた。姿を見れば飛びついていったし、子どものころの口癖が当たり前になって、いかめしい礼儀正しさも忘れ、兄がどこへ行くのも「兄さん、兄さん」とあとをついて回っていた。 みっともなく見えることは頭のどこかで分かっていたし、だってオレはもういい大人だったからだ、だけど兄はまたひたすらオレを甘やかしてくれて、その度にオレは泣きそうだった。 あのやんわりした線引きが消えた。まるで兄じゃない別の人間みたいだった。兄はもう以前みたいに決してオレを拒むことはなく、折にふれてオレに触りたがった。手のぬくもりもなにも知らなかったんだと、その時になって初めて気付いた。 兄が母校の特別ゲストに呼ばれたとき、一仕事を終えたあとで誰もいなくなった屋上で、昔一番大切な人と眺めるのが好きだったフェンス越しの夕日を見せてくれたことがある。オレは悪ふざけの虫にそそのかされて、必要以上に子どもぶって抱き上げてくれるようにせがんだ。オレは喉の奥で笑っていた。オレにとっては、いい年をして悪ふざけをする『子どもごっこ』だった。 兄にはそうではないようだった。兄はなにかとても切実な心の動きに引っ張られてそうしているらしかったのだ。それが何なのかはオレには結局今になってもわからないが、ひょっとすると兄は怖がっていたのかもしれない。ふとした瞬間に、兄はオレを見て怯えたように立ち竦むことがあった。たとえば、見せしめに首を刎ねられた子どもの死骸を前に親が浮かべる絶望の表情――オレは昔、ちょっとばかり荒れていたことがあって、そういうものを沢山見る機会があった――に似ていると思った。 兄への違和感が気持ち悪かった。だから、オレは心のどこかで、以前のような兄の拒絶を心待ちにしていたのかもしれない。 だけど兄はオレの尻を軽々と持ち上げ、背中に腕を回して支えてくれた。オレは兄のたくましい首に腕を回して、横顔に見惚れていた。今でも、夕日の赤い光の中で輝いている兄の美しい輪郭は、何度も夢に見るくらいにオレのなかで鮮やかだ。 オレが兄を慕う想いは、長い間兄にとっての混乱と頭痛の種で――知っていたのだ、ちゃんと、本当は――いつも困らせていたように思う。だから急に兄がオレを甘えさせてくれて、我儘を言ったときにあの困ったような笑顔のかわりに、いたわるような、とても大切な、深遠な生命のあり方そのものを見るような眼をされた時、逆にオレのほうが困ってしまうことがあった。一度なんて、優しくしてくれるのが嬉しくて泣きだしてしまったことがある。 オレに甘えを許してくれるかわりに、兄はオレと決闘をしてくれなくなった。前みたいにデッキを見せてくれなくなった。オレが駄々をこねて決闘をせがむと、なだめるように身体に触れる。そうされると、オレはもう言いなりになるしかない。 兄は背が高く、筋肉質で、そのくせ優しい面差しが彼をどこか女性的な風貌に見せていた。事実兄は処女ではなかった。変な言い方かもしれないが、実際にそうだった。詳しいところは良く知らない。一度それで痛い目を見ていたから、詮索はしなかった。オレはその人になりたがって、生まれて初めてってくらいの大目玉を食らったことがある。 兄はきめの細かい気付きやすさで、オレにやり方を根気よく、ひとつずつ教えてくれた。全部。 髪の先から足の小指の爪の先まで、くすぐるように舐められるのは、オレは兄を誰よりも尊敬していたから、気持ちがいいよりも先に申し訳のない気持ちになったものだった。兄はそうやってオレの素肌の感触だとか、温かさだとか、恥ずかしがって叫ぶところだとか、そんな死にそうになるひとつひとつの反応に、ひどく安心したように頷く。何か、大事な確認ごとをするみたいに。 「長生きするんだよ。いつも、身体に気をつけるんだ」 兄はそういつも別れの挨拶みたいなことを言って、鼻先を擦り合わせて、腕のなかへ入れて包み込んでくれた。 「キミだけはボクを置いていっちゃ駄目なんだから」 兄は沈まない太陽だった。どこまでも昇ってく。オレは地べたに這いつくばって、まぶしい兄の背中を見上げるのが何より誇りだった。光を目指して走り続けていれば、いつかは辿り着けると信じたかった。暗い闇の中を振り向くのはもううんざりだった。 だから、夜なんか永遠に来なければよかったんだ。 1 穏やかな色に光る海面に白い花束を投げ入れ、遊星は軽く顎を引いて目を閉じた。水が跳ねるかすかな音。再び目を開けた時には、花は波の間に沈んで見えなくなっていた。
彼は高々度の空から祭儀に集った客船群を見下ろしている。人間離れした視力を持った彼の目には、乗客ひとりひとりの顔がはっきりと見えていた。
晴れた空から雷が落ちた。昔、嵐の海に落ちる雷を見たことがあるが、あの時のような雷雲の気配はどこにもなく、海は平らに凪いでいた。まるで何かとてつもない重量を持った大きな白い剣が、空の彼方から勢い良く突き降ろされたようにも見えた。
|
||
 |
 |