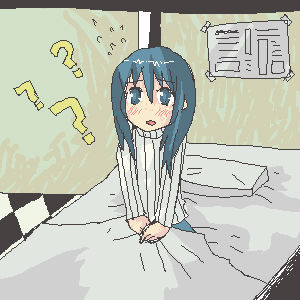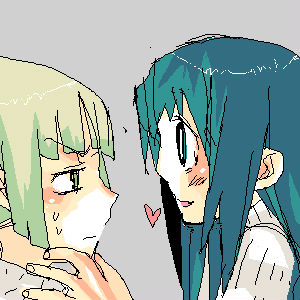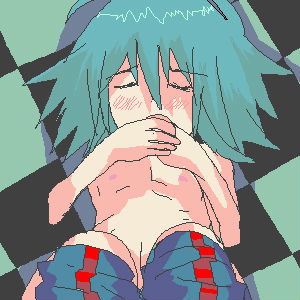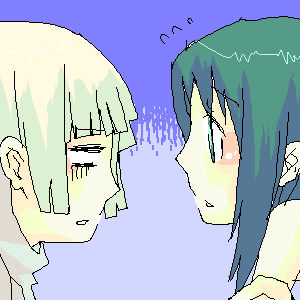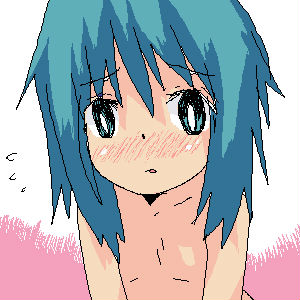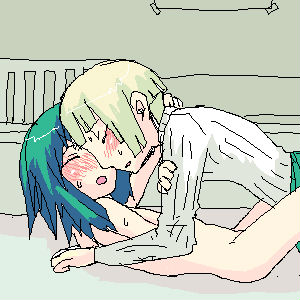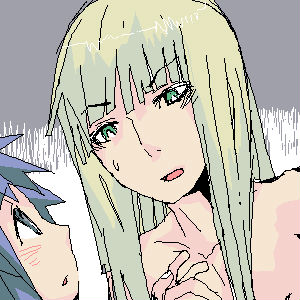目を覚ました。今日は大分、良く眠れたと思う。
身体はだるかったが、意識ははっきりしていた。すっきりとした朝だ。
ベッドから身体を起こすと、背中の下で錆び付いたパイプがぎしっと軋む音がした。
(……? 変だな)
中央区のセントラル竜の間は、どれも特別なものが設えられていた。
正直リュウにはもったいないものばかりだと言って良い。
それらが、まるで下層区ですり切れるまで使い込まれたような、疲弊が入り混じった悲鳴を上げるわけがない。
竜の間の調度品や家具をオーダーしたのは、センスの良い配偶者だった。
ローディとして生まれ、下層区で育ったリュウとは違って、その男は生まれも育ちも高貴で、何の気まぐれを起こしたのだか十二の歳にレンジャーを志願して下層へ降りてこなければ、おそらく一生顔も合わせなかったに違いない。
そういったことに関しては、リュウは口にこそ出さないが、運命というものを信じているのだった。まるで虹色にきらきら輝くような色。
ようようはっきりしてきた視界には、懐かしい景色が映っていた。
低い天井は、二段ベッドの上段の底である。
下段からは鉄骨の柱とテレビ、乱雑にものが乗ったままのデスク、つけっぱなしのテレビが見えた。
(あれれ?)
ずるずるとベッドから這い出した。
そこばっかりは懐かしい反射でもって、ベッドの枠に掛けてあったシャツを着込みながら、ぼんやり床に座り込み、リュウはきょろきょろと周りを見渡した――――
ゴム張りの床。靴底の跡がぺたぺたといくつも重なり合って、汚れて光沢を失っている。
部屋の支柱、五段しかない階段の手すり。部屋に入った時から手垢がついて、錆びていた。
ロッカー。二つある片方は、すっきり片付いている。もう片方からは、乱雑にものが溢れている。
頭の上のベッド上段からは、足が食み出していた。白いつま先。だらしなくぐだっと垂れている。
見慣れたボッシュのものであるはずだ。だが、少し奇妙だった。
いつもより柔らかく、幼く見えた。
「……ぼっしゅ?」
目を擦って、リュウは座ったまま背中を伸ばして、ボッシュの足の指を摘んで引っ張った。
するとすぐにあからさまに、うっとおしそうに身じろぐ気配が伝わってきた。
「……るせえ……起こすな」
「う……」
険悪な返事が返ってきて、リュウはびくっと竦んだ。
いつもなら、リュウの「起きて」という仕草に、ボッシュはなあ頼むもうちょっとだけなんて甘えたみたいに言うのに、今日はどうもおかしい。
「ぼ、ぼしゅ……お、起きてっ、あれ? あ?」
ふと気付いて、リュウは慌しく洗面所に駆けこんだ。
姿見に映った自分の姿に、リュウはしばし言葉を失った。
切ったはずの髪が、いつのまにか肩を越えるくらい、長く伸びている。
顔立ちも少しばかり幼かった――――が、いつもより幾分かシャープに見えた。
身体中が痩せ、骨ばった、少年の体つきをしていた。
「え、え、えっ?」
リュウは目を白黒させて、ばたばたと自分の身体に触れ、確認した。間違いなかった。
身体はぴんとした直線で構成されていて、硬く、柔らかい胸もなかった。
オリジンリュウ=1/4は十六歳当時そうあった、少年の姿に戻っていた。
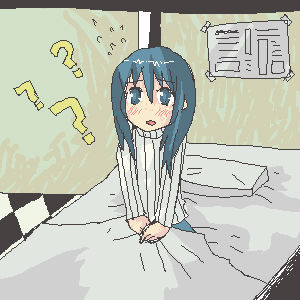
ぐいんと足を引っ張られた。
そのせいで、ほとんど天井とおんなじ高さにあるベッド上段から落下、顔から床に叩き付けられた。
痛みの余り言葉が出てこない。悲鳴すら出ない。何が起こったのかわからない。
「う、う、うー!」
幼児が親に泣き付くみたいな、甘ったれた情けない声が降ってきた。それから、ぎゅうと縋り付かれる感触。
そこでボッシュは、はっとなった。寝起きのぼんやりも、どこかへ去ってしまった。
「な、何事だー!!」
「ぼしゅううー!!」
思わず絶叫すると、更に大きな声で叫び返された。
「……あん?」
ボッシュは、鼻を強く打ったせいでだらだらと零れてくる鼻血を押さえて、目を険悪に眇めた。
見ると、リュウだ。
いつも少し俯きがちで、穏やかで、激昂するところなんか見たこともない相棒のリュウ=1/8192が、大声でわんわん泣きながらボッシュに抱きついてきた。
予想外が過ぎてわけがわからず、ふつふつ沸いていた怒りもどこかへ行ってしまった。
「リュ、リュウ? オマエなに泣いてんの、朝から」
リュウは涙を喉に詰らせてしまって、げほげほ咳込みながら、何がしか人間の言語じゃないぴーぴーした声を上げている。
「ぼ、しゅう……あ、あじ、アジーンが、いないの。ど、どっか、いちゃ、ったあ……」
「アジーン? 誰それ」
聞いたこともない名前だ。
困惑して訊き返すと、リュウははっとしたようにばっと顔を上げて、ボッシュを指さした。
「あ、アジーンでしょ。ボッシュのかっこしたって、おれにはわかるんだから」
「だからそれ誰。わけわかんないこと言うなよ。つうか、オマエさっき何した? この俺に、何をした?」
「……うー? あ、アジーン? ちがうの?」
「だからそれ誰だっつうんだよ。鼻血とまらねえよ。オマエのせいで」
なんだかリュウは別人のような子供っぽさで首を傾げている。
うーうー言いながら、やっとボッシュの惨状に気付いて、慌ててティッシュの箱を差し出した。
「だ、だいじょぶ? 鼻血……ごめっ、おれ、ど、ど、どうしていいか、わかんなくて」
「あとでお仕置きな、オマエ。ていうか、それ誰」
「え?」
リュウが首を傾げたことに苛々しながら、ボッシュは訊いた。
そんな必死に、誰の名前を呼んでるっていうんだ。
「アジーンて誰。男? 女? 続柄は。家族? 友人。 上司、同僚。もしかしてさあ」
自分でも、目が据わってるだろうな、とボッシュは自覚していた。
リュウが怯えたような顔をしているからだ。
とん、とリュウの胸を小突いて、ボッシュは地獄の底から響いてくるみたいな声を出した。
「……好きな、奴、とか?」
「えっと、うん、好きだよ。当たり前じゃないか」
リュウは、なにか変なこと言ってるかなあという気安さで、あっさり頷いた。
「えっと、女の子だって、言ってた。顔だけはかわいいって、弟が。ボッシュも知ってるでしょ?」
「知らねえよ」
気だるく頷きながら、ボッシュとしてはそれどころじゃない。
リュウはボッシュの相棒である。
そして実の所、まったく困ったことなのだが、ボッシュはリュウのことを、まあ憎からず思っているのだった。
誰も彼もうっとおしく目障りなレンジャー基地において、嫌いじゃない唯一の人間だ。
それは大それたことであった。
ボッシュが家族以外で、他人に対してそういう言葉を当て嵌めてやることなんか初めてだったのだ。
子供の頃から憧れていた青い髪の美しい少女――――まあその幻想は今や潰えてしまったのだが、それでもボッシュはリュウのことが好きだった。
そのリュウが、ボッシュの他の人間を、こんなに必死になって呼び、探している。
これが面白いわけがない。

ボッシュがものすごく怖い顔をして、リュウを睨んでいる。
リュウはびくびくしながら、これはどういうことなんだろうか、とできる限り冷静に――――もう十分に混乱しきっていたので、大したものではなかったが――――事態の分析に努めた。
まず、身体。十六歳の少年の姿。リュウも、ボッシュもそうだ。
自分とおんなじ背丈のボッシュなんて、なんだか懐かしいというよりも妙に新鮮だ。
いつもは背伸びしたって、おんなじ目の位置には届かないのに。
普段より小さいボッシュは、たとえ険悪そのものの顔をしていたとしても、なにかミニチュアめいていてかわいいと思う。
これを言ったら、多分怒ると思う。言わないでおこう。
今いる部屋。レンジャールーム。サードレンジャーに宛がわれるホームである。
大体みんな組まされている相棒と同室だった。リュウも例に漏れずそうだった。
リュウ=1/8192は、ボッシュ=1/64とサードレンジャー時代に出会い、こうして相棒同士で任務についていた。
奇妙な感慨が、リュウに浮かんできた。
「うわーっ、なっつかしいなあ……」
はー、と溜息をついて、ボッシュの顔をぺたぺたと触る。
まだあどけなさを残す頬は柔らかい。ぎゅーっと引っ張ると、伸びる、伸びる。
「……オイ?」
「あ、ね、もちょっと触っててい? ね?」
上目遣いでおねだりすると、ボッシュにばちんと頭を引っ叩かれた。
いつもなら「しょーがねーな」なんて目を逸らして言うのに、今日のボッシュはどうやらリュウのおねだりを聞いてはくれないらしい。困った。
「わっけわかんないし! 何なワケ? 変なもんでも食った? ハイ、言ってみろ。俺はなんだ?」
「ボッシュ=1/4」
「そう、1/64なんて、オマエみたいな1/8192のローディが気安く……って、ハア?」
ボッシュはあっけにとられたような、変な顔をしている。
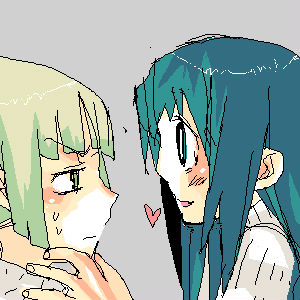
バカだボケだと思っていたら、とうとう故障してしまったようだ。
ボッシュはそろそろ心配になってきて、リュウの額にぺったりと手のひらを当てた。
熱はなかった。
「ちょっと本気で、頭大丈夫か? まだねボケてんの? オイオマエ、自分の名前言ってみろ」
リュウは目をぱちぱちして、まるでおかしいのはボッシュのほうだとでも言いたそうに、眉を寄せた。心配そうな顔だ。そりゃこっちがやりたい顔だとボッシュは思った。
リュウはぺたんと胸を撫で、なんか変だな、と言った。
「リュウだよ。ぜんぜんおかしくなんかない。おかしいのは……うーん、まわりの全部のほうだよ。だっておれ、昨日ちゃんとベッドに入ったとこまで覚えてるし。でも夢にしてはリアルなんだなあ……」
ここで、またふにふにとボッシュの頬を引っ張って、リュウが呟いた。
「……これやめろ。オイ? オマエ、なんだ。言ってみろ。名前、所属、階級と、個人情報その他何でもいい」
リュウは頷いて、指折り数えだした。
「リュウ、22歳。所属は……ええと、ボッシュ? 階級はお嫁さん。特技は……変身? がおーって、背中から火が出たりするの」
「……メディカルルーム行くぞ、リュウ」
「なんで?」
無邪気な顔をして、リュウが首を傾げた。
ふざけているのか、ボッシュをからかっているのか?
いや、それはないだろう。
リュウがこんな高度な冗談を言うわけがない。
ボッシュはリュウの胸倉を掴んで激しく揺さぶりながら、大声を上げた。
「お嫁さんて、なんだそりゃあ?! 男の言うことかよ! しかもオマエが」
「だ、だってちっさい時に約束したって」
「覚えてたの?!」
ボッシュは驚愕して、眩暈がした。大変だ。
あの恥ずかしい約束を、リュウは思い出してしまったらしいのだ!
だからと言って今からハイ父さまこれ俺の婚約者ですなんてリュウを上に連れて行けるわけがない。
リュウは男で、ローディだった。もれなく、上層区メディカルセンターの精神病棟送りである。
「わ、忘れろ! 俺は男となんか結婚したくない! ていうか父さまに殺される!」
「う……いやだったの?」
「当たり前だ! ていうかなんで既に過去形なんだ?!」
叫んで、ボッシュははっとした。
リュウはべそべそと泣きだしてしまっている。
***
ボッシュに辛く当たられるのには慣れていたが、こういう系統――――例えば「オマエなんか好きじゃないよ」という類のものには、いつまで経っても慣れないものだ。
思わずぼろぼろと泣き出してしまうと、ボッシュはぎょっとした顔になった。
「な、なに泣いてんの?」
恐る恐る、どうすれば良いんだろう、みたいな感じで、ボッシュが訊いてきた。
リュウは知っていた。ボッシュという人は、予想外のことにあんまり強くない。びっくりさせてしまったようだ。
リュウは慌ててごしごし顔を拭って、なんでもないよ、と言った。
きっとこれは夢だ。
昔の夢を見ているのだ。
ボッシュがリュウに優しくなかった時分の夢をだ。
だけど、もしこっちが本当で、今までのことが全部夢だったらどうしよう?
リュウは考えて、青くなった。
ボッシュが優しいのも、リュウを好きだと言ってくれたのも、全部リュウの都合の良い夢だったなら、それはとても悲しいことだ。
それこそ死んじゃいそうなくらい。
想像するだけで、喉が詰まった。胸を突かれるような感じだ。
「ぼ、ぼしゅ、おれの、こと、きらい?」
めそめそ泣きながら訊くと、ボッシュは慌てた顔で、なにバカなこと言ってんのローディ、と言った。
「オイ、マジどうしたのオマエ……いいか、オマエはリュウ=1/8192! 16歳、俺と同期のレンジャーだ。そんで、万年サードレンジャー。わかる?」
「う、ちがうも……およめさん、なるんだも……」
「だ、だからバカ、オマエ男だし、ローディだし! 無理無理! オマエは俺をホモにする気か?」
「うえっ……」
「泣き止めよ、オマエ今日その顔で朝礼に出てみろ。あの隊長に何言われるかわかったもんじゃない」
「う……」
ボッシュの面倒臭そうな口調に、リュウはふてくされてしまった。
ボッシュは今日は全然優しくない。
だからつい、意固地になってしまうのだった。
リュウは口をへの字に曲げて、ボッシュに言った。
「き、キスしてくれたら、泣き止んだげる」
「ハア?」
ボッシュが目を丸くした。

あのバカだけど純粋無垢なリュウが、とんでもないことを言い出した。
ボッシュは一瞬硬直してしまった。
「ハア?」
「だ、だからねえ、きっ、キスして? じゃなきゃ、ごめんなさいしたって、許してあげないんだから」
どうやら聞き間違いではなかったようだ。
リュウは真っ赤な顔になって、目にいっぱい涙を溜めて、ちょっと下を向いてもじもじしている。
それはちょっと可愛い。
(……て、そんな場合じゃなかった。ど、どうする? このバカ、本気で故障しちゃったみたい。確か下層区のローディは叩いたら直るんだっけ、故障が……いや、ちょっと待て。これはチャンスじゃあないか? 向こうからいただいてくださいつってんだぞ。ここは男として……つうかコイツも男なんだけど……!)
ちらっとリュウを見てみると、上目遣いでボッシュを見ている。
おねだりの眼差しだ。
生真面目で頭が固く、いつもちょっと俯いて、必要なことしか喋らないような、そんなリュウにこんな意外な顔をされると、正直ボッシュとしては、かなりくるものがあった。
つい反射でリュウの肩をぐっと引寄せると、リュウはびくっと震えて、おずおずと目を閉じた。
そんな反応をされて、黙っていられるわけがない。
なんだか妙な夢を見ているらしい、とボッシュは思った。
そう言えば、さっきリュウもそんなことを言っていたような気がする。夢がどうとか。
(……夢なら仕方ないよな。うん、俺も朝弱いし。ねボケてるんだ。きっとそうだ)
ボッシュは無理矢理に自分を納得させて、リュウの唇に、ちゅっとキスをくれてやった。
男でも、唇は柔らかかった。
顔も可愛い。このまま流されてしまいたくなるくらい。
「んん……」
くすぐったそうな顔をして、リュウが気持ち良さそうな声を出した。
背中がぞくっとする類のものだ。寒気とは別のもので。
ボッシュは目の前が絶望で暗くなるのを感じた。
これじゃ俺は間違いなく、ホモセクシャルの変態だ。
(父さま、すみません……。剣聖に連なるボッシュ=1/64は、下層区で妙な趣味に目覚めちまったようです……)
そもそも、リュウがこんなふうにあからさまに誘うなんてことがあるわけがないのだが……。
「うー……」
ぺろん、とボッシュの唇を舐めて、リュウは薄く目を開けて、両腕をボッシュの背中に回した。
ぎゅうっと抱き付いて、ボッシュを抱いたまま、こてん、と倒れた。
引っ張られるままに、ボッシュはリュウに覆い被さる格好になった。
ふと客観的に、ボッシュは現在の体勢に気付いた。
まるで、ボッシュがリュウを押し倒しているみたいだ。
「……何なの、マジで?」
ボッシュは困惑して、リュウの意図がわからず、眉を顰めた。
リュウはちょっと恥ずかしそうに顔を赤くして、例によって「おねだり」の顔で甘えたように、
「ね、して?」
さも当然のように言った。

なんなのコレみたいな顔をしてはいるけど、やっぱりボッシュはボッシュだ。
ぎゅうっと抱き付いて甘えると、いつもと同じあの「しょうがねえな」って顔をしたのを、リュウは見た。ほんの一瞬だったけど。
「……それ、「ナニが」って聞かねえぞ」
「うん?」
リュウが首を傾げると、ボッシュはちょっとだけいらついたように――――見えるけど、これはほんとは照れ隠しなのだ――――言った。
「だから、そーいうことだよ」
「うん」
ふにゃっと笑って、リュウは頷いて、なんかおかしいなあ、と思った。
ボッシュがリュウに触るのを躊躇うなんて、ほんとに変だ。
「は、はやく触ってよお。はずかしいよ……」
「オ、オマッ、オマエ、そんなにやらしい奴だったの?」
「う……ま、また意地悪言う」
「つか、話噛み合ってねえから」
ボッシュはやけになったみたいに、リュウのシャツをべろっと剥がした。
「ひゃっ……」
冷たい床が直に背中にくっついて、リュウは身を竦めた。

それは別に色気もなにもない、見慣れたリュウの裸だった。いつもの。
シャワーを浴びた後に、着替えを持って入るのを忘れたとかで、デスクで本を読んでるボッシュの前をびしょ濡れのすっぱだかで平気でぺたぺた歩いていくような、そんな見慣れたものだった――――ボッシュとしてはまあ、これに関しては、慣れるまで大分時間が掛かったが。
中央省庁区で他人の裸なんか見る機会がなかったボッシュには当たり前のことで、なおかつリュウは、例の初恋の女の子と顔だけはまったくおんなじだったので。
赤いラインの入った紺色のパンツを膝まで脱がせて、ボッシュはちょっとげんなりした。
ああやっぱり、あるし。
「うー、へんなの……おれ、これが普通のはずなのに、なんかすごくへんなことしてるような気がするなあ」
リュウはぽそぽそ言って、首を傾げた。ボッシュには、リュウが何を言っているのだかわからない。
「もーいいから黙ってなよ。こうなりゃヤケだよ。途中で泣いたって止めやしないからな」
「う……うー、がんばる……」
リュウはちょっと顔を強張らせたが、結局大人しく頷いた。
平べったい腹から、滑らかな股間に手をやると、きゅっと眉を寄せて、口元に手を持っていった。
「……は……あ、ぼしゅ……」
小さくふるふると頭を振って、艶のある吐息を零し、腰を揺らした。
なんだか思うのだけど、この反応、妙に慣れてるふうじゃないだろうか――――確かにリュウは真っ赤になって恥ずかしがっていたが、ボッシュに身体をあっけなく預けきってしまうあたりだとか、さっきの誘いぶりといい、初々しいくせに、どうも初めてっぽくない。
「オマエさあ」
ボッシュは胸がずしっと重くなるのを感じて、リュウに訊いた。
「経験アリ? 初めてってさ、いつ」
「う……」
途端に、リュウはこの上なく真っ赤になってしまった。
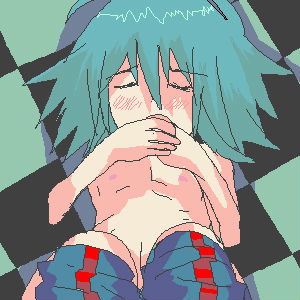
そんなこと、聞かないでほしい。それとも、あれだろうか。ボッシュの新しい意地悪なのだろうか。
ボッシュはちょっと意地悪なので、リュウが困ったり、恥ずかしがるところを見るのが好きなようだった――――「けっこうくる」のだそうだ。何がくるんだかは良くわからないけど。
「初めて」がどういうカウントのされかたをするのか、リュウは他人とはちょっとばかり違った身体の構造をしていたので、良くわからない。
暗いシェルターの中で、鎖に繋がれてひどくされた時?
でもあれはぜんぜん、そう、お互いの合意なんてなかったわけだし、リュウはまだうまくボッシュを見付けられないでいた。
ボッシュがわからないなんて、思い出しても怖くなる。
そしてもしくは、ボッシュのコートを抱えてどきどきしながら廊下を歩いていた、あの呼び出された夜だろうか?
「なんかね、ボッシュ……おれ、はじめて、二回あるみたい」
言った途端ぎゅうと首を締められた。
ボッシュはかなり怒っていた――――ボッシュの怒った顔は無表情なのだ。クールな能面をして、リュウの息を止めている。
リュウは目を白黒させて、腕をばたばたさせた。
「く、く、く、くるひいー!」
「ニ回? ああそうなんだ、やっぱローディだもんな。けっこースキモノなんだね。誰にでも身体、あげちゃうんだ。オマエってそんな軽い奴だったんだ、了解」
「う、う、うー!!」
なんだかひどい誤解を受けているみたいだ。まるでリュウがボッシュのほかの誰かに、そーいうことをさせたみたいな。
「で、誰。それ、誰。言っちゃいな、多分明日の朝、最下層区の下水道あたりから発見されるかもだけど」
「ぼ、ぼしゅ……」
「ハア?」
「ぼっしゅ。はじ、めての……」
酸欠と羞恥で、リュウは赤くなって、ぽそぽそ言った。
やっぱりなんだか新しい種類の意地悪だ。きっとそうだ。
羞恥プレイというやつだろう。はずかしいのがきもちいになるっていう、変なやつ。
「……記憶にないんだけど」
「ほらあ……えっと、暗い部屋につれてかれて、手錠つけられて」
「うん」
「壁に鎖で、つながれて」
「うん」
「お、おれやだって言ってたのに。ボッシュ、無理矢理へんなことするんだもん……。ちょっと、こわかったよお」
「へえ」
なんだか相槌が虚ろだ。ふとボッシュの顔を見上げると、彼はなんだか真っ白になっていた。
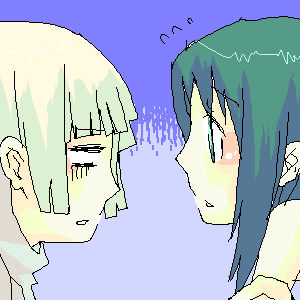
リュウが無垢な目をして、ボッシュを奈落に叩き落すようなことを言った。
(俺は、なにをした……?!)
真っ白になりながら、ボッシュは過去を振り返ってみた。
身に覚えは……ないと思うが、はっきりとはしない。
後暗いのは、もしかしたら、という疑惑のせいだ。リュウはさすがに、そういう悪趣味な冗談は言わないだろう。
酒でも入ったか。それとも、ねボケたのか。そう、今みたいに。
何が困るかというと、ボッシュはもしそんなことがあったとして、何故今自分はそれを覚えていられなかったのかと、ある種残念に思っているということに気がついたからだ。
しかし、それはまずい。リュウ相手に拘束緊縛プレイ。いきなり何をやっているのだ。まずは順序というものがあるだろう。
(て、違う! そうじゃない! そういう問題じゃない!)
ボッシュは半分パニックに呑み込まれそうになってしまった。
「で、でもっ」
はっとしてリュウを見遣ると、ぽーっと潤んだ瞳で、ボッシュを上目遣いに見上げている。
やっぱり、かわいい。
「でもおれっ、ボッシュになら……なにされても」
そして、ぱたん、と腕を床に落とした。
もうどうにでもして、という仕草だ。
知らず、ボッシュはこくっと喉を鳴らせた。リュウが、リュウのくせに、妙にいろっぽい。やらしい。
(ま、マジで、コイツ、なんか知らない間に調教とかしちゃったわけ、俺?)
のろのろとリュウの膝を開かせると、彼はもう次に何をされるのか知っているのだというふうに、ちょっと身体を強張らせて、きゅうっと目を瞑った。
「ね、も、はやくきて。きもちよくして、ぼしゅ……」
舌っ足らずな声でねだられて、それがボッシュの我慢の限界だった。理性の糸というやつが、ぷつんと切れてしまったのだった。
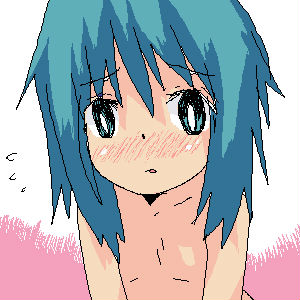
急にぐいっと足を引っ張られて、リュウはちょっとびっくりして、小さな悲鳴を零した。
「ひゃっ……」
乱暴にされるのだろうか。ボッシュはいつも、リュウが泣き出すと優しくあやしてくれるけれど、ちょっとばかりひどくする。
開いた脚の間にぐっと腰を押し付けられて、リュウはさすがに眉を顰めて、すこし震えた。
こんなにいきなり、心の準備はもう万全だけど、身体のほうは大丈夫なのだろうか?
痛くないだろうか?
いや、ボッシュが痛くしたいんなら、リュウはそれで全然かまわないのだけれど。
彼になら、なにをされたって構わなかったので。
「あ、あ……」
不器用に、強引にボッシュのを押し付けられて、ぴりっとした痛みがリュウに訪れた。
慣らしてないから、まだあんまり上手く入らない。
でもリュウの身体の準備が整っていなくたって、ボッシュはお構いなしに突っ込んできた。
この辺、彼らしい。
ボッシュは乱暴で、性急だ。いつもはもうちょっと優しいけど、たまにこうやってひどくすることがある。
我慢がきかないわけ、と彼は言う。
リュウの身体のことでボッシュに我慢なんてして欲しくはなかったから、リュウはぎゅうっと目を瞑って堪えた。
「ぼ……っ、しゅ、あ、うー……」
大分長く時間を掛けて、ボッシュが少しずつ、リュウのお腹の中に入ってきた。
繋がってしまうと、ボッシュはぽーっとした顔で、少し戸惑いがちに、リュウにちゅっとキスしてくれた。
彼はなんだかびっくりしているみたいだった。
「……ホントに、できちゃうんだ、こんなこと……」
ボッシュはリュウのなかを確めるように、少し身じろぎした。
お腹の中で擦れて、リュウは切ない吐息を零した。
「すき、ぼしゅ……ぼ、しゅ?」
リュウはのろのろ顔を上げて、首を傾げた。
ボッシュは真っ赤になっていて、浅い呼吸をしていた。
でも、なんにも言ってくれない。
少し不安になって、リュウは眉を顰めた。
「ね、すきって、ぼしゅ、なんで言ってくれないの?」
「え、えっ?」
「き、キライ? おれのこと、キライになっちゃった? や、やだ、うー……」
「ば、バカ、何言ってんの、オマエ!」
ボッシュは慌てて、リュウの背中を抱いて、焦ったふうに言った。
「き、キライなやつに、こんなことするかよ。は、はじめてなんだよ、こーいうの、誰かに……
くそっ、ずーっと、俺は、ホントはオマエが……」
「……すき?」
「……ああ、そーだよ!」
ボッシュは自棄になったみたいに、真っ赤になって頷いてくれた。
リュウは嬉しくて、ふにゃあと笑いながら、ボッシュにぎゅうっと縋り付いた。
「う、あん、ぼしゅ……」
「……っ! うあ……」
腰を緩く動かすと、中でまた擦れて、ボッシュが熱の篭った溜息を吐いた。
「きっ、きもちい? ねっ、ねえ」
「ちょ、待てって……オマエ、いくらなんでも急に、いきなり……」
「や、やらしいの、ボッシュのせいだもん」
リュウはボッシュの胸に頬を摺り寄せて、ぺろっと舐めた。そして真っ赤になって、弁解した。
「ぼ、ぼしゅ、好きだから、おれ、なんでもしてあげる。ボッシュが気持ち良くなれるなら、はずかしいのもへいきだよ。だ、だって」
リュウはボッシュを見上げ、ぽそぽそ言った。
「おれ、ボッシュのお嫁さんだもん……」
お腹の中のボッシュが、浅い呼吸の度にリュウに擦れて、気持ちが良くて、もどかしい。
「リュウっ……」
ボッシュがリュウの腰を掴んで、さっきよりも深く繋がってくれた。
「あぁっ!」
リュウはびくっと跳ねて、のけぞった。
目の前に、ちかちかした瞬きが浮かび始めた。
断続的にちかっと光る――――
そして、ひどい眩暈がリュウに訪れた。
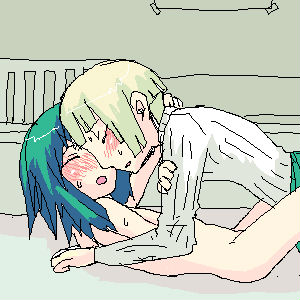
「リュウ……リュウっ!」
ボッシュが呼んでる。その声は湿っていた。
ちょっと泣いてる声だ。
リュウははっとなって、慌ててボッシュを探そうとして、目を開けた。
どうしてこんなに遠くから聞こえてくるのか?
今、リュウはボッシュと「きもちいこと」をしてるんじゃなかったっけ?
不思議なことはいっぱいあったが、とにかくボッシュを泣かせるわけにはいかない。
かわいそうだ。
「ぼしゅ……」
ぐるぐるする視界の中で、ようやく金色の頭を見付けた。途端、視界がクリアになった。
定まらなかった焦点がぱっと合って、ボッシュを見付けた。
金色でさらさらした長い髪の、とても綺麗なひとだ。リュウは目を瞬いて、名前を呼んだ。
「ぼしゅ? どしたの……?」
「リュウ!」
どうしてそんなに悲しそうな顔してるの、とリュウは聞こうとした。
でも口を開く前に、息が止まるくらいぎゅうっと抱き締められて、なんにも言えなくなった。
「リュウ……オマッ、オマエ、また、死んだかと思った。呼んでも起きないし……そーいうことじゃ前科者なんだ。呼んだらちゃんと応えろ、バカ」
ボッシュはリュウがぎゅっと背中を抱き返すと、ようやく安堵したようだった。
なんだかわけがわからなくて、リュウは首を傾げた。
「えっと……おれ、ボッシュときもちいことしてたよ?」
「なにそれ。やらしい夢でも見てた?」
「夢……なの うー、すごいリアルすぎるよ」
「へえ」
ボッシュは浮かべていた心配そうな顔を、いつもの意地悪そうなにやにや笑いに徐々にすりかえていった――――リュウはそれを見てはっとなって、顔を真っ赤にした。もしかして、今ものすごい恥ずかしいことを言っちゃったんじゃないだろうか?
「そんなにやらしい夢、見たんだ。なに、欲求不満? もっと欲しいの?」
「う」
リュウは眉を顰めて、あんまり言わないで、と言った。
「わ、わかってるから! おれ、やらしいも……で、でもボッシュのせいだもん!」
リュウはちょっとムキになって、ボッシュに言い訳した。
「ぼ、ボッシュのこと考えたら、変になっちゃうんだも……だ、だからボッシュのせいだよ」
「光栄だよ、オヒメサマ」
ボッシュはいつもの意地悪な笑いを浮かべている。
そのままリュウに覆い被さって、胸をむぎゅっと掴んだ。
「じゃ、そういうことで」
「え、えっ?」
リュウは目をぱちぱちして、ああそういうことだと理解した。
きもちいことをするのだ。
やっぱりいつものボッシュは、ちょっと意地悪だけど、優しい。リュウに好きだと言ってくれる。
だけどまだ、あの少年時代の彼の手の温かさが残っていた。
リュウの身体が火照ってくるまで、そう時間は掛からなかった。
(なんか、へんなのお……)
なんだったのかなあ、とリュウは心の中で首を傾げていたが、しばらくするとなにも考えられなくなったのだった。
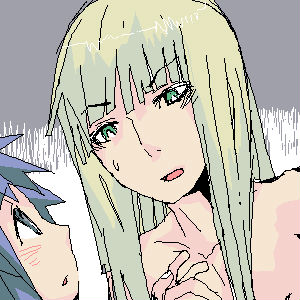
「あ……うー?」
ぱちっと目を開くと、心配そうに覗き込んできているリュウと目が合った。
「あ……ボッシュ?! だ、大丈夫?!」
「……ハア?」
リュウは半分泣きながら、ボッシュに縋りついてきた。
よかったあと涙声で言って、ボッシュの胸に額を擦り付けた。
「し、死んじゃったかと。呼んでも、起きないし……」
「ああん?」
ぐすぐす泣いているリュウをとりあえず引っぺがして、ボッシュはきょろきょろ辺りを確認した。
見慣れたレンジャールームである。
ベッドの上だ。何故か、リュウの。
ボッシュはまだ半分泣きが入っているリュウの顔を見上げて、耳まで赤くなった。
「リュ、リュウッ?!」
「え、えっ? なに? なにか欲しいものある? なんでも言って、おれ……」
「じゃなくて! オマエ、そのっ……平気か?」
「へっ?」
「いや……」
ボッシュはまともにリュウの顔を見られず、下を向いてぼそぼそ言った。
「あんだけ……その、アレ。まあ、そーいう感じ」
「……あの、ほんとに大丈夫? おれのこと、わかる?」
「何言ってんの? リュウだろ」
ボッシュは改めてリュウを観察した。
彼はいつもの生真面目な顔で、じっとボッシュを覗き込んできていた。
その声は誠実で、甘えは含まれていなかった。潤んでもいなかった。
良く考えてみれば、リュウがあんなことをするわけない。
まるで新婚何ヶ月かの人妻みたいな(そんなものを実際に見たことないが、まあイメージだ)ことを言いながら、ボッシュに迫ってくるわけがないのだ。
しかもお嫁さんになるんだ、とか言いながら泣くし。
(ゆ……め?)
あんまりにも馬鹿馬鹿しい……ボッシュは激しい自己嫌悪と落胆で死にそうになった。
そんな夢を見る自分が嫌だった。だが、それが夢だったことがものすごく残念だった。もう頭の中がぐっちゃぐちゃだ。わけがわからない。
「ほんとに大丈夫? あ、水持ってくるよ」
「あ、ああ」
ボッシュはふるふる頭を振って、あんまりにもリアルに蘇ってくるリュウの感触に、真っ赤になって溜息をついた。
これじゃまともにリュウの顔を見られやしない。
確かにボッシュはリュウに好意を抱いてはいたが、そういう意味じゃない。
人妻はやりすぎだ。しかしせっかくなら裸エプロンがよかった。いやだから、そんなじゃないんだ。
「はい、水……飲める?」
コップ一杯の水を汲んできたリュウが、気遣わしげにベッドに腰掛け、ボッシュの口元に差し出した。
冷たい水で喉を潤すと、少しまともな思考が返ってきた。人心地ついた。
ふっと見上げると、結い上げられたリュウの首筋が目に飛び込んできた。
ボッシュは硬直した。
「リュ、リュウ?」
「え? なに?」
「オマエ、その首の、なに?」
リュウの首には、D値の刻印のまわりに二つばかり赤い痣が見えた。
リュウは、ああ、と頷いた。
「今日起きたら、なんか、あって……寝てるうちに虫に刺されたかなあ」
「む、虫?」
ボッシュはまた、安堵と落胆を一緒くたに感じた。
リュウはいつも通りだった。こんなになんでもない顔のリュウが目の前にいると、あれはやっぱり夢だったんだ、という気になってくるのだった。ボッシュの都合の良い夢。
ボッシュは嘆息し、起き上がった。時計を見上げ、そしてまた硬直した。
「午後4時ー!?」
「うん、ほんとに良く寝てたんだから……起こしたって全然起きないし、返事もなくて」
何てことだ、せっかくの非番が台無しだ。
がっくり項垂れたボッシュだったが、はっとして、慌ててリュウに訊いた。
「お、おい、俺なんか変な寝言言ってなかった?」
「ううん……なんにも」
「あ、そ」
ボッシュはほっとして、ベッドから起きあがった。腰がものすごくだるい。シャワーでも浴びようと浴室の扉を開け――――
「何だこりゃああッ?!」
身体中に赤い小さな痣がある。どれも薄く消えかけていたが、ボッシュは思い当たることが山ほどあって、悲鳴を上げた。
「リュウ――――ッ!」
「あ? あれ? ボッシュ、どしたの? うわ、その赤いの」
浴室から飛び出すと、ボッシュの身体にあるキスマークとおぼしき斑点を見て、リュウは困った顔をした。
「ボッシュもやられたんだ……実は、おれもすごいんだ、身体中。最近任務で掃除する暇なかったからなあ。やっぱり、しなきゃまずいなあ。きっと虫、大発生だよ。困ったな」
リュウは素直にそう思っているようで、眉を顰めて首を傾げている。
ボッシュはもう何が本当のことだかわからなくなってしまった。
「なあ、なんか……オマエ、変な夢とか見なかった?」
「え? いや、今日は、なんにも見てない……と、思うけど」
「あ、そう……」
もう全部何かの幻覚だと思うことにしよう。そうしたほうがいい。心の健康のためだ。
ボッシュはそう自分に言い聞かせて、シャワールームに戻ることにした。
扉を閉める前に、そういえばねえ、とリュウが困ったように言った。
「でもなんか誰か、朝からずーっとおれの耳元で悩ましく囁いてるような気が……あれ……アジーン……?」
別段何の関係もなさそうだ。ボッシュはリュウを放ったまま、シャワーのコックを捻った。
さあっと熱い湯が流れてきた。
このままいろんなものを押し流してしまえたらどんなにいいかと考えて、ボッシュは溜息をついた。
そんなに上手く行かないことは知っている。
それからもリュウは別段変わりなく、いつもどおりだった。
基地の外の階段で足を滑らせ、転げ落ちて頭を打つまで「なんか誰か頭の中にいるう」と困った顔をしていたが、それもどうやら解消されたようだ。疲れていたのだろう。
ボッシュ自身はと言えば、それからもうあんな夢も見ないかと思えばそうでもなく、まあ妙な願望が入り混じったものを何度か見ることになる。
メイド服だとか、ナース服だとか、そんなものだ。
だがそれらにはあの例のリアルさが欠けていた。
なんだったんだろうなあと気になって仕方なかったが、それもそのうち夢だったと自己完結できるようになった。
まったくの悪趣味な夢だ。
そんなことがあるはずがないのだ。
ボッシュは、これがほんとのことだったらなあなんて、少ししか思っていない。

・終・
|