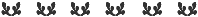|
 | |
|
夜が来た。一面の薔薇の花で埋め尽くされた常春の園が、薄青い闇の来訪とともに、ひそやかな囁きをさざめかせながらまどろみはじめた。遠い鐘楼の境界線が化石のような月に照らされてぼんやりと光っている。
幻想の中の風景だと彼は思った。事実、この地は現実社会から隔離されていた。学園というものはどこもそうだ。かの名高きアカデミアも、この名ばかりのアルカディアも。 彼は生垣のなかに身体をねじり込むようにして潜っていた。夕立ちに湿り気を与えられた黒い土が不快だ。泥水がスラックスに染み込んでゆく。鞭のようなつる草がむき出しの皮膚を絡めとり、無数の棘がある種の拷問具のように肉を突き刺す。彼はうめき声を上げたが、すぐそばまで規則正しい足音が近付いてきている。罵声を呑み込んだ。 「奴はいたか?」 「いえ、こちらには」 「必ず見つけ出せ」 追跡者だ。押し殺した声が聞こえる。 「生徒たちが騒ぐ前に捕らえるのだ。我々の雇い主は、奴を『なるだけ』無傷で連れ戻すことをご所望だ」 よく言うぜ、アマゾネス。テルモドン河のヒッポリュテ。彼は自分の身体じゅうに刻まれた裂傷を見下ろして、唇のかたちだけで皮肉を言った。右のふくらはぎに麻酔弾が埋め込まれている。それでも彼は、しばらくの間、体内を侵食していくアザペロン薬剤がもたらす強烈な睡魔に抗っていた。 「この理想郷にあんな汚らわしい『モノ』が紛れ込むなど前代未聞だ。虫唾が走る」 冷えきった声は異物への嫌悪感と生理的な恐怖を隠しもしない。おぞましい虫けらの気配に震えている。彼の手首を、肘のあたりまで、大きななめくじが這っていった。粘液を引きずった跡が、ランタンの灯りを受けて光っている。 無機質な足音が煉瓦のアプローチを抜けて、薔薇園を過ぎ去っていく。単調なリズムを上の空で聴きながら、彼はいつしか昏倒していた。夢を見た。これまでの人生を辿る、ぱっとしない、錆びた鉄の色をした記憶の再現だ。 『息子を決して私の目の届くところへ置くな。いいか、金ならいくらでも払う』――小等部へ上がる前に、父が見知らぬ誰かに向かって受話器越しに怒鳴っている場面に出くわしてしまったことがある。 幼い彼が当時耳にした言葉は、心の奥深い部分へ突き立ったストックレス・アンカーとなった。親にさえ疎まれ、必要とされない事実。それを引きずったまま生きてきた。 生まれつきそうだったのかはわからないが、彼は少なくとも物心ついた頃には敵意と粗暴を身に纏い、暴力の姿に成形した苛立ちと怒りを周囲にぶちまけながら成長した。中等へ上がる頃には、矯正施設が門戸を広げて彼を待ち構えていた――すんでのところで少年院送りにならなかったのは、父親の取り計らいのためだ。 彼の父親はとんでもなく大金持ちで、いくらかの賄賂を払って息子を豚箱から引き取ると、ささやかな寄付金を贈って寄宿舎つきのスクールに押し込んだのだ。事実上の厄介払いだった。 退屈なスクールでの生活も、そう長くは続かなかった。幾度も問題を起こした末にドロップアウトした彼は、空っぽの家には帰らず、世界中を放浪し始めた。何を求めての旅だったのか、今となっては思い出せもしない。くだらない理由だったのだろう。理由すらなかったのかもしれない。彼は満たされず、いつでもくすぶり続けていた。 どこへ行っても、彼はある理由から人々に異端視され、迫害されてきた。 彼の父親ははりぼての名誉と慈悲深さを盲信し、重用する種類の地位にあった。名前と顔写真付きの経歴書の価値を、たった一ペニーでも吊り上げるための大いなる障害――つまり自らの放蕩児の存在に、寛容の限界をむかえた。 父親は彼を拘束し、財産として所有する、古代の貴族が打ち捨てた廃城に幽閉した。 どうしておれが、こんなにもみじめな目に遭わされなけりゃならない? 彼はつくづく疑問に思っていた――おれのほうが周りにいる誰よりも強いのに、優れているのに、金の亡者め、権力の信奉者め。人類の進化の証であり、奇跡の体現である彼を不当に扱う父親を、彼は心の底から軽蔑した。 彼は朽ちかけた城を脱走した。そして追手に脚を撃たれて今に至る。 薬物の昏睡から目が覚めたとき、暴力的なほどに明るく輝く青い空が頭上に見えた。マリア・カラスの無垢な赤薔薇が蕾を開き、つる草の茂みは濃い青緑の影に塗りつぶされ、さわやかな高原の朝の風に揺すられていた。眩しくて目がちかちかした。全身が痺れていて、仰向けになったまま口を開け、喉の奥へ一滴の朝露を呑み込むのが精一杯だ。撃たれた右足が熱を帯び、にぶい痛みが彼を苦しめた。 「おおい、待てって」 誰かがやってくる。真鍮の鈴が鳴るように涼しげな声をしていて、男なのか、女なのかも分からない――まだ寝ぼけているのか? 女に決まっている。男子禁制のこの学園に、自分以外の男はいない。 驚くほど近くに人の気配を感じて、彼は呼吸を止めた。誰かは、そばにいる何者かと親しげに会話を交わしている様子だが、足音はひとりぶんだ。ぎざぎざしたハート型の葉が揺れ、日差しがまともに彼の顔に当たった。眼球が金色の矢のような陽光の直撃を受け、しばらく何も見えなかった。 すすけた灰色の修道服を着た女が彼を覗き込んできていた。驚いたようだったが、騒ぐそぶりもない。血のにおいを嗅ぎ取ると、心得たふうに彼の前へ跪いて動かない腕を取った。不動化薬が残していった硬直がなければ、彼は間違いなく相手を殴りつけ、馬乗りになり、辱め、動かなくなるまで無差別の敵意をぶつけていたはずだ。 「オレは保健委員なんだよ。あんた、ラッキーだったな」 携帯式の薬箱を開けて、女は男のような喋り方をした。彼の足の惨い傷跡を見ても悲鳴を上げなかった。 消毒液のにおいが鼻孔に充満する。頭が浮いた。水筒の口が顎に当たる。彼は溺れるように水を飲んだ。喉が溢れ、犬のように大げさな呼吸の合間にこわばった咳を何度も繰り返した。 「おまえ、カードを持っていないか」 自分の喉から出た声は頭蓋の内側で反響し、まるで未練がましい死人の嘆きのように聞こえた。女はきょとんとしている。意味がわからなかったのだろう。彼は満足の笑みを浮かべた。 「デュエルモンスターズだ。こんな傷くらいおれの〈力〉ですぐに治るんだ。持ってるはずだ、おまえは、ここの生徒なんだろ。その胸糞悪い修道女のなりを見ればわかる」 女はデッキケースを開き、〈非常食〉のカードを差し出した。彼はなにも知らない女への軽蔑と憐れみを込めて鼻を鳴らし、カードを傷口にかざした。びびるなよ、おれの力を見せてやる。 玩具のカードが彼の手の中で本物の魔法に昇華され、記されたテキストが現実のものとなる。むごたらしい盲管射創が塞がってゆく。肉の間に埋まった弾丸が消失し、なめらかな皮膚が回復する。もう血は一滴も零れない。 カードゲーム・デュエルモンスターズの実体化能力。これこそが彼に宿った大いなる力だ。同時に、彼が人々に忌み嫌われる根源だった。 女は何も言わない。声も出ないほど驚いているのか――いや、そうではない。あくびさえ零しそうな顔だった。信じられないことに、彼が持つ特別な力に対して、女は児童向けの幼稚な算数式の羅列と同程度の退屈を見出していたのだ。 彼が引き起こした奇跡を目の当たりにした者は、誰もが恐怖にかられて逃げ出した。そして数の暴力を引き連れて戻ってきて、彼を叩きのめした。それが正常な法則だった。無情な数式。 女は逃げない。畏れない。彼は取り乱した。女ひとり怖がらせてやれない。慌て、うろたえた。 女は、目の前で馬鹿な子どもが覚えたての手品を披露したときのような、なにもかもわかっているんだという態度で――『あたり前じゃない。オキトのコインボックスや、ペッパーズ・ゴーストのトリックとか、それからデビッド・カッパーフィールドがいかにして瞬間移動をしたかってことに比べれば、あんたの子供だましは種も仕掛けもお見通しよ』――そんなふうにして、薄い肩をすくめただけだった。 学園指定のピンクのポシェットをまさぐり、魔法使いが古式ゆかしいかばんから不思議な道具を出現させるように――まるで『私の方がすごい魔法を使えるのよ』と言わんばかりに――プラスチックの安っぽいランチボックスを引っ張り出した。 食べ物! 彼は本能的に腕を伸ばして女のランチボックスをひったくった。中身は蒸した米を丸めて鮭の切り身を包み、のりで覆った奇妙な食べ物だ。食べ付けない味で、しょっぱくていびつだが、長い時間を飲まず食わずで過ごした彼には涙が出るほどうまかった。 「おにぎりって言うんだ。知らないか。オレの国の食い物だよ。なかなかいけるだろ――なぁキミ。こう考えたことはないか。キミの力は、キミがなすべき使命を果たすために与えられた力。キミは選ばれたんだ」 女が言った。 「だけど今のキミは怯えているだけだ。自分の力を理解しようとしない親に、先生に友達に、出会ったやつらみんなに、この世界じゅうにさ。みんなの考えてることがわからない。こんなにすごい力を持ってるのに、誰も認めてくれない、誰も褒めてくれない。そんな馬鹿なことはあっちゃならない――キミは孤独で、だけど孤独を貫ける程にキミ自身を信頼しきれてもいない。手にした『力』の来し方行く末を怖がっているキミが振るう拳は、本来ならキミ自身へ向けられるはずだった苛立ちに他ならない。誰のためのものでもない。八つ当たりさ。 もう一度言うけど、キミに宿った特別な力は、使命を完遂するためのものだ。それが大きな力なら、きっと大きな意味がある。果たされるのは今じゃないかもしれない。だけど必ず、たとえ手の届かないくらい先の未来にだって、キミがキミだけの使命に気付く時が来る。ぶれるな、考えろ、力の意味を。キミの痛みは誰かにぶつけられるものじゃない。もちろんキミ自身に向けられるものでもない。早くなんとかしないと、そいつはいつかキミ自身の肉体も魂さえも食らい尽くすぜ」 空になったランチボックスを投げつけて、彼はけだもののようにすごんだ。 「そんな御託はどうでもいい。おれが欲しいのは力! 力だ!!」 女は呆れたようだった。 「ばかなんだな」 「なんだと!?」 「そんなに力が欲しければ、一回、世界征服でもしてみればいいさ」 彼は驚いて、壊れた音響機器のように、「せかい、せいふく」――女の言葉を繰り返す。 彼女は赤を基調にしたセーラー制服を翻らせ、銀杏の並木道を駆けてゆく。昼過ぎに降った雨で濡れたタイル舗装路を、モカ色のペニーローファーが蹴り上げるたびに、浅い息が弾み、胸元のリボンが上下した。扇形をした金色の葉が舞い落ちてくるなかで、彼女の視界の端に見知らぬ男が携帯電話を構える姿が映った――若いれいようのような快活さで飛び跳ねていた肢が強張り、シャッターを切る音が彼女の心臓を凍えさせた。
ふいに丁字路の角から長身の青年が幻のように現れ、よそ見をしていた彼女は正面から衝突した。派手に転倒したせいで生乾きの泥がボックスプリーツのスカートを汚し、ショルダーバックのデッキが開いてデュエルモンスターズのカードがほうぼうへ散らばってゆく。彼女は息を乱して、震える指をカードへ伸ばした。 「ご、ごめん」 「そっちこそ大丈夫かい。きみも、カードも」 ぶつかった相手はやわらかい声で言った。ぶどう色の長い髪の青年だ。彼女の前にしゃがみこんで、一緒にカードを拾ってくれる。暖かそうなクリケットセーターを着ていて、淡いブルーのシャツの襟元にボトルグリーンのリボンタイを結んでいる。頬に、それほど遠くはない少年時代の名残りのそばかすが薄く残っていた。無邪気そうなコーヒー色の瞳は、軽い眩暈に似た既視感をもたらしたが、その正体に思い当たる前に、背後へ集まりつつある人の気配が彼女の中へ再び強い羞恥と危機感を呼び起こした。逃げなければならない。 「……誰かに追われてるの?」 「えっ? あ、いや、その」 「わかった」 青年は顔つきを凛々しく引き締めて、彼女の肩を掴んだ。 「逃げよう。きみ、こっちだ」 青年に手を引かれて、彼女は枯れた噴水と風化しかけた遊具が並ぶ寂しげな公園を横切り、薄暗い高架下を抜けて走り続けた。開発が進むにつれて姿を消し始めているが、童実野町には曲がりくねった裏道がいくつも存在する。それらは思わぬ場所で繋がりあっており、今もふたりが歩道橋の階段を駆け上ると、目の前に駅前ビルの壁面に設置された大型液晶ディスプレイが出現した。デュエルディスクを構えた初代決闘王の勇姿が映し出されている。思わず立ち止まって、子どものように歓声を上げた。 『うわぁ……』 隣の青年も、彼女と同じく口をぽっかりと開けっ放しにしている。ふたりは顔を見合わせて、同時に噴き出した。 「きみも?」 「うん。キミもなんだ」 「遊戯さん、強くて恰好良くって、憧れるよねぇ!」 「ああ、あの人に憧れねぇ決闘者なんかいねーぜ!」 「あは。いねーぜ、だって! きみ、そんなにかわいい顔して、女の子なのに。まるで男の子みたいな喋り方をするんだ」 彼女は桜色の唇を押さえてしどろもどろになった。砂糖菓子のように白い指で、青年の袖を引っ張る。 「悪いけど、このことは黙っててくれないかな」 「学校、厳しいの? 言葉遣いとか」 「う、うん。まあ、そんなとこ」 「秘密にするよ。約束する」 彼女はほっとして、あらためて青年の顔を見上げた。既視感の正体に思い当たったのだ。 「キミって、レオン・ウィルソン? 初代KCグランプリで遊戯さんを追いつめた、おとぎの国のレオン。童話デッキ使いの天才決闘者じゃないか」 「あ、見てくれてたんだ! そうなんだよ。ぼく、遊戯さんと闘っちゃって」 映像記録が作られた当時の面影を残したまま青年に成長したレオンは、夢見るようにきらきらと瞳を輝かせている。無垢な好奇心と打算のない憧れを表現する姿は、彼女自身も小さな子供だったころ、海の向こうで開催されたデュエル大会で武藤遊戯と対峙していた少年決闘者に間違いなかった。 「もう、もうすごいんだ。あの人、どんな絶望的な状況でも諦めないで、一番苦しい時にぼくを励ましてさえくれた。決闘者の中の決闘者だよ。ねぇ、きみは、えっと……」 「オレ、あ、えーと、『オレ』じゃないや。『わたし』は……」 「普通に話せばいいのに。友達の前ではさ」 「え?」 「遊戯さんに憧れるファン同士、もう友達だよ」 レオンが屈託なく言った。彼女も少し微笑んで、頷いた。 「カンナだよ。デュエル・アルカディア一年生。今はちょっと用事があって、童実野町に来てるんだ」 駅のショッピングモールで、カンナはヒッコリーデニムと前立てのフリルがついたニットのパーカーに着替えた。泥で汚れた制服をクリーニングショップに預けてから、踊り場のベンチに座ってチョコレート色のツーテールをほどいた。レオンが長い三つ編みを作ってくれる。 「これでよし。今のきみがさっきまでのきみと同一人物だなんて、きっと誰も気が付かないよ」 「レオンは器用なんだ」 「髪をいじるのは慣れてるんだ。家にいてひとりで暇を持て余した時なんかに、よく遊んでたんだよ」 「なんか、わりぃな。ここまでさせちまって」 レオンはカンナに赤縁の伊達眼鏡を掛けさせながら、穏やかに首を振った。 「とんでもない。悪いのはよそ見をしていたぼくだからね。ごめん、きみみたいな可愛い女の子を危ない目に遭わせるなんて」 「か、かわいいとか、ねーし」 「かわいいよ。きみはぼくの憧れの人にどこか似てる。とっても美人だと思うよ」 カンナは耐えきれないくらいに照れくさくなり、同時に、奇妙な懐かしさを憶えていた。レオンは、カンナの近しい知り合いの誰かによく似ているような気がする。 「ええと、レオンはどうして日本に来たんだ? 観光旅行とか?」 「ぼくね、今期のKCグランプリに参加するんだよ。もちろんカンナも知ってるでしょ」 「ああ。冬に海馬ランドで開催される大会だよな。でもまだだいぶ日があるぜ」 「そう。ちょっと、その、大事な用があって」 「ふうん?」 「ま、まあそれはいいんだけど。本戦にはぼくの友達も出るんだ。そいつ、カレッジの後輩で学年首席なんだけど、かなりの変わり者でね。今朝も童実野港に着くなり、大事な夢を探しにいくんだって言い置いたっきりどこかへ消えちゃった。先生たち、また慌ててるだろうなあ」 「夢ねぇ。よくわかんないけど」 「ねぇカンナ。きみも決闘をするんでしょ?」 レオンは期待に満ちたまっすぐな視線で、カンナを見つめた。 「ぼく、遊戯さんが好きな人とぜひ闘ってみたい。予選大会には出るのかな」 「もちろんだぜ!」 カンナは大きく頷いた。今冬に開催される〈KCグランプリ二〇〇九〉を勝ち抜いた優勝者は、特別枠で参加する無敗の決闘王に挑戦する権利を得る。これでエントリーしなければ偽物の決闘者だ。 カンナの携帯が震えた。新着のメールが表示される。差出人欄に厳格な寮長の名前を確認し、整った顔から血の気が引いていく。相手の苛立ち度合いを認めて、反射的に背筋を正していた。 「オ、オレ、帰るよ。うちの寮長先生、門限にはとくにうるさいんだ」 「途中まで送っていくよ」 「大丈夫だって。それじゃ、色々世話になった。ありがとうレオン」 カンナは大慌てで、つむじ風のように駆け出した。
タクシーの行列が続く駅のロータリーへやってきたレオンは、構内通路の両脇いっぱいに並ぶポスターの中から、見覚えのある少女が悪戯っぽい微笑を投げかけてきていることに気が付いた。
チョコレートのようにとろりとした艶のあるブラウン色の髪を、ツーテールに結っている。パニエ付きの赤いミニワンピース姿で、果実を思わせる潤んだ唇の両端がはにかむかたちに上がっている。 先程までレオンの隣を歩いていた、あの男勝りの風変わりな話し方をする美少女だった。レオンは呆然とポスターのコピーを読み上げた。 「『次世代決闘者アイドル、神月カンナ』――あの子、アイドルだったんだ。どうりでかわいいと思った」 駅前ビルの巨大スクリーンが、神月カンナを起用した新型デュエルディスクのコマーシャル映像を流している。聞き覚えのある甘い声が、唄うような柔らかさで囁きかけてくる。庇護欲を強烈にかき立てる種類の可憐な仕草は、レオンに見せていた荒っぽい動作や少年じみた口癖からは想像もつかないものだ。まるで別人に見えるほどに意外だが、決して悪くない。 「しまったなあ、サインもらっとくんだった……」 レオンは天を仰いで額を叩き、本気で落胆した。神月カンナのポスターへ熱心にカメラを向けている人々のどこか憑かれたような眼差しを見ていると、多くの肩書きを背負った今のレオンには、あの少女が何者に追われていたのかを推測することができた。 ポケットの中で電子生徒手帳のアラームが鳴った。通話ボタンを押した途端に、ハイトーンの能天気な笑い声が響いてくる。決して協調性に欠けているわけではないのに、度しがたい方向音痴で、頻繁に行方不明になっては周囲を混乱させてくれるカレッジの後輩からだった。レオンはまだ興奮をうまくなだめきれないまま、早口でまくしたてた。 「ねぇ、さっき、すごく面白い子に会ったんだよ。女の子なんだけど、きみにもぜひ会わせてあげたいな。きっとびっくりすると思うから。あ、そうだ、きみが探してた友達には会えたの? ……え、行方不明? ふーん。なんだか素行がきみによく似てるな。でもきみと互角の決闘者だっていうのなら、冬の大会で会えるんじゃないか。じゃ、またあとでね――ヨハン」 レオンの年少の友人は、デュエルモンスターズに関わりのある事柄以外は眼中になく、気が付けば空っぽの宙に向かって親しげに話しかけている変人だ。彼に言わせればそれはお互いさまになるらしいが、レオンは長い付き合いのなかで、彼があれほど誰かに執心している姿を見たことがない。あの男のお目当てが男性なのか、それとも女性なのか、本当に実在する人間なのかは見当もつかないが、純粋な興味を覚えていた。 あの〈宝玉獣のヨハン〉が夢にまで見る相手とは、一体どんな決闘者なのだろう。 「ぼくも、楽しみだ。カンナにまた会えるかもしれない」 今度はサインをねだろうと意気込んだ。 かつてレオン・ウィルソンを名乗り、多くのデュエル大会においてタイトルを総なめにしてきた天才決闘者レオンハルト・フォン・シュレイダーは、ヨーロッパにおいて第一位のゲームシェアを誇る大企業シュレイダー社の副社長を務めている。来春に発足する日本支社を一手に担うことになる彼は、今回この極東の島国へ渡るにあたってひとつ心に誓ったことがある。
クラスメイトの取り巻きの少女たちが、童実野ホテルのロビーでカンナを待ち構えていた。
「ごきげんよう、カンナ様。あら、おかしな恰好ですこと!」 「まあ、本当に! カンナ様を心から敬愛する私たちでなかったら、きっと気がつかなかったに違いありませんわ」 まわりを囲んで、かしましい歓声を上げながら肘や肩に触れる。珍しい動物の扱いだ。開放的な広い空間に並んだ白大理石の丸テーブルに着き、一日の終わりの時間をゆったりと過ごしていた他の宿泊客たちが、ぎょっとして振り返った。カンナの姿を認めると、彼らはテーブルの下からこっそりとカメラを取り出した。弱りきったカンナは、愛想笑いを顔に貼り付けた。 「ミス・カンナ!」 ロビーじゅうに凛とした声が響き渡った。少女たちの笑い声が止む。養護教諭のミス・ゴーランドが腰に手を当て、アルフレッド・シスレーの油彩画を背に立っていた。縁なしの眼鏡越しに見える黒い目がカンナを厳しく責めている。彼女はかんかんだった。 「旅行中の門限は学園と同様の十七時です。とっくに過ぎていますよ!」 「すみません。ゴーランド先生」 カンナは素直に頭を下げた。 「たとえアイドルと呼ばれて世間から好奇の目を向けられていようとも、貴女は名門デュエル・アルカディアの生徒なのです。特例はありません。貴女は我が校の規則に忠実に従わなければならないはず」 「仰るとおりですわ、ゴーランド先生」 「いいですか、ミス・カンナ。貴女には沢山言って聞かせなくてはならないのです。アルカディアに在籍する一人前のレディとしての自覚と誇りさえ持っていれば、門限を破るような、自ら規律を乱すような馬鹿な真似はしないはずですよ。それなのに貴女自身のその素行! 言葉遣いはすぐに乱れるし、歩き方は冬眠明けの浮かれた熊のようだし、出席率の低さや先週の定期テストの悲惨な結果、まったく目を疑います。なんですの、その、みっともない恰好は? 制服はどうしたの?」 「あ、えっと、転んで汚れてしまって……でも、親切なひとが助けて下さったんです。門限に遅れたのも、そのう、ちょっといろいろあって……」 「言い訳は聞きません、ミス・カンナ」 ゴーランドはぴしゃりと言った。 「これから私の部屋へいらっしゃい。この学園の名誉ある生徒として、貴女にふさわしい振る舞い方をわかってもらえるまで、じっくりお話をしたいわ。他の生徒たちは早くレストラン・ルームへお行きなさい。夕食の時間はすでに過ぎています。ルールをきちんと守ること。ドロップアウト・ガールの真似なんてするのはとんでもないことですよ。そして寄り道をせずに部屋に戻って、シャワーを浴び、明日に備えなさい。貴女がたのオリエンテーション旅行はまだ初日なのですから」 カンナの取り巻きの女子生徒たちは、若い女教師の高圧的な態度が気に障ったらしく、湿った目付きを向けている。しかしゴーランドに一睨みされると、牧羊犬に追われる羊の群れのようにひとかたまりになって、蔦模様が描かれた濃い色のカーペットの上を歩いていった。 「ひどい。カンナ様が授業に出られないのは、お仕事の都合でしょうがないことなのよ。校長先生だってわかってて、応援してくれてるのに。ゴーランド先生ってカンナ様のこと目の敵にしてる感じだよね」 「ええ。若くて綺麗だけど、ちょっとキツすぎますわ。きっとご自分よりも若くてかわいいカンナ様に、ライバル意識を燃やしていらっしゃるんだわ」 「オールドミスの女教師がトップアイドルの神月カンナ様に張り合うなんて、いくらなんでも身の程知らずよね」 これ見よがしのひそひそ話だ。カンナはゴーランドの機嫌の更なる降下を肌で感じ取り、寒気がした。思ったとおり、神経質そうな指がカンナの耳をつまんで引っ張った。 「いたたた! 先生、ちょっと、耳は、わたし……」 「こっちよ、ミス・カンナ。私は貴女のためを思って忠告しているのです」 ウォールランプの橙色の光が、吹き抜けの天井まで高く伸びたアーチ型の窓に映り込み、清潔な純白のカーテンを温かい色に染めている。ファインダー越しに覗き込んでくる宿泊客たちの合間を抜け、犬のリードのように耳を引かれてエレベーターで高層階まで昇った。長い廊下の先にあるゴーランドの部屋へ着くと、女教師は素早くルームキーを回して客室の扉を開け、カンナを中に押し込んだ。背後で鍵が掛かると、廊下を漂っていたかすかな物音が完全に遮断され、耳鳴りがするほどの静寂がやってきた。ゴーランドがカンナの背中を叩いた。 「――さて、茶番は終了だ」 ミス・メアリー・ゴーランドが、今日初めての作っていない声色で言った。 「ご苦労だったな。もういいぞ、下っ端」 それを聞いた途端に、全身から力が抜けた。凝り固まった筋肉をほぐし、二人掛けのソファに沈み込んで、背もたれに両腕をかかしのように広げて乗せ、全体重を預けて、カンナは――トップアイドルの神月カンナを演じていた遊城十代は、天井を虚ろな目で見上げながら肺のなかの空気を残らず吐き出した。 「マジ、きついですよ。これ」 「なんだよ。もうギブアップか。思った以上にだらしのないやつだな」 十代は苦りきってうめいた。 「そんなんじゃないですけど……」 神月カンナは、海馬コーポレーション社が発表した新型デュエルディスクのコマーシャルへの出演をきっかけに、爆発的な人気を博した現役高校生アイドルだ。あらゆる媒体に目まぐるしく登場する彼女に魅了された人々は、カンナをソリッドビジョンの妖精と呼ぶ。 事実だ。カンナは立体映像と人工音声が電子の奔流のなかで無限に増殖を繰り返しているソリッドビジョン・ガールであり、人々の共同幻想のなかに住んでいる。〈トップアイドルの神月カンナ〉という少女など、本当はどこにもいない。白昼夢を縫い合わせてできた着ぐるみの中には、女心のひとかけらも理解できない青年がみじめな顔をして入っている。 ただ神月カンナという女性は実在する。彼女は人々の幻想の中の少女よりもふた回りほど歳を取っていて、今頃は名前も知らないスモール・タウンに新しい家を手に入れ、見たこともない家族と暮らしているはずだ。 彼女にはもう四年も会っていない。 『はじめは〈アンナ〉って名前を付けようと思っていたのよ。あの頃パパと見に行ったアンナ・カレーニナのバレエがあんまり綺麗だったから。でも、だめだったわ。生まれてきたのは男の子だったんだもの』――破綻した古い家庭の記憶を掃き清める努力を続けながら、静かに歳を重ねているだろう。そこで彼女は〈アンナ〉を得たかもしれない。とっておきの名前が再婚した彼女に生まれた娘に、それとも彼女が名付け親をやるだけの近しさがある誰かの娘に麗々しく贈られたかもしれない。 幼児の頃からバレエを習わされて、縁飾りのついたふわふわのチュチュを着てアンナ・カレーニナを踊っている娘の姿を想像しようと試みたが、知らない物語のあらすじも架空の妹の顔もうまく思い浮かばなかった。ひときれのシーンさえ。 十代は考えるのを止めて、メアリー・ゴーランド役を一時降りた海馬モクバのノートパソコンを覗き込んだ。かすれたアルミニウムのボディに自社のロゴマークが入っている、今秋発売されたばかりの最新モデルだ。シルエットが特撮映画に出てくる地球防衛基地のコンソールのようで恰好良いし、動作もすこぶる快適そうだ。この珍事が終わったら買い替えてもいい。初めて持ったノートパソコン――友達にもらったお古のブラックは、夏に南欧で遭遇したペガサス暗殺未遂事件が終息したころにはもうぼろぼろになっていたのだ。 フラットな液晶画面に、無心にキーボードを叩く女性の顔が映り込んでいる。十代は上目遣いで、モクバの西洋白磁の肌と、薔薇色の濡れた唇と、はりねずみの背中の針のようにぴんと立ったまつ毛を観察した。完璧な変装だ。どこから見ても二十代半ばの成人男性には見えない。胸の谷間に振りかけたいちじくのにおいのする香水が鼻先を漂っていた。 「モクバさんって女装の天才ですね。全然違和感ないです」 「お前には言われたくない」 モクバがスプレッドシートから目を離さずに言った。十代は鏡台を無意識に見て、またモクバの最新型ノートパソコンへ視線を戻した。本体カラーのバリエーションに赤はないだろうか? あとでカタログを見せてもらおう。 「褒めてるんだ。少なくとも笑えないレベルには達してるぜい」 キーボードを叩くかちかちという音が響く。十代は下を向いて脚を揺らした。 「……なんか、全然嬉しくないです」 「気が散るから、黙っててくれよ」 「あの。オレがこんな恥ずかしい恰好してたって、絶対に遊戯さんに言わないで下さいよ」 「お前こそオレの恰好のこと、兄サマに絶対言うなよ」
|
||
 |
 |