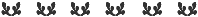|
 | |
|
旅の途中で再会した武藤遊戯を追い駆けて日本へ帰ってきたばかりの頃に、海馬モクバに出会った。あの晩、海馬コーポレーション系列のホテルのコーヒーハウスに同席した十代は、渾身の本塁打がプレイング・フィールドを抜け、硬球が隣家のガラス窓へ吸い込まれていくところを途方に暮れながら見つめている野球少年に似た心地だった。モクバを見ているとそんな気分になる。賞味期限が切れ、古くなってさらに発酵が進んだ罪悪感。 店内には丸みを帯びたダイニング・チェアが空っぽのラバーウッドのテーブルに並んでいて、客は三人だけだった。ウェイターが十代の前に分厚いドリンクメニューを広げ、新作のレッドアイズ・ブラックティーはジャムを加えるかストレートで飲むのがおすすめなのだと教えてくれた。アルコールを勧められたふたりの大人は丁重に断った。 薄いカーテンで区切られたテラスの窓から、七色にぴかぴか光る観覧車と、そのうしろに黄色い明かりを灯した高層ビル群の無数の窓と白く発光する夜空が見えた。旅先で今にも雨あられとなって降り注いできそうな南半球の逆さまの星座を仰いだときの、銀河フィラメントのただ中に放り出されたような浮遊感はなかったが、この街の星空だって今の十代の眼には充分に賑やかだ。 フルーツパフェに長細いスプーンを突っ込んだまま口を半開きにして、向かいに座った男のボリュームがある栗毛に視線をぴたりと定めていた。なにしろ落ち着かなかったから、言葉をひとフレーズも聞きとめておくことができなかった。はすむかいの席でチョコレートパフェを頬張っているモクバに足を踏まれて、ようやく我に返る。 「ええ? なんですか?」 「ちゃんと聞け、くそガキ」 相手の男は注意力散漫のドロップアウト・ボーイとは長い付き合いだったから、よく心得ていて、落ち着き払った態度でもう一度ゆっくりと言い直した。 「君には盗まれた武藤遊戯のデッキを、何としても取り戻して欲しいのだ」 ふさふさの巻き毛を頭に載せた鮫島校長が言った。豆電球のような頭部を見慣れている十代は目をしばしばさせた。 「デッキって、盗まれたって、あのブラック・マジシャン・デッキがですか? そんな、まさか」 「決闘王武藤遊戯さんのデッキの巡回展示を、今年は全世界のデュエル・アカデミアで行なっていたんだ。今夏、本校での開催を皮切りに、ノース、サウス、イースト、ウエスト、アークティック、各校を順繰りにまわり、そして再び本校でアンコール展示が行われ、会期の終了とともにデッキはすみやかに遊戯氏のもとへと戻るはずだった」 「さすが遊戯さん。心が広いっていうか、人が良過ぎるっていうか」 十代には自分自身の魂のデッキが長期にわたって手元を離れ、比喩ではなく命そのものの大切な仲間たちが展示会場のショーケースの中に囚われたもしもを思い描くことさえ苦痛だった。半分呆れまじりの悪寒が背中のうぶ毛を逆立たせている。 「デュエル・アカデミアは海馬コーポレーション、とりわけオーナーの海馬瀬人氏の個人的なコネクションを通じて、武藤遊戯氏とは一定の信頼関係にある」 「兄サマの前で、それ、言わないほうがいいと思うぜい」 モクバが、バナナチップのささった生クリームをいとおしそうにスプーンですくっている。 「遊戯たちとオトモダチ扱いされるのは、死ぬほど嫌がるから」 「は、はあ。面目ない」 鮫島は海馬モクバに頭が上がらないでいる醜態を教え子の前に晒していることに赤面し、ごまかしの咳ばらいをした。 「アカデミアは氏の信用とともに、金銭には替えられぬ途方もない価値を持った四十枚のカードを預かったのだよ。もちろん我々は磐石の備えで臨んだ。だが、氏のデッキは何者かに盗まれてしまったのだ」 鮫島が化学繊維でできた作り物の頭を抱えてうめいた。 十代は驚かなかった。デュエル・アカデミアに在籍していた頃、鮫島の耳にはとうとう入ることがなかった、格上寮のラー・イエロー生徒が引き起こした決闘王デッキの盗難事件を思い出す。本物の伝説のカードたちに相対したあの夜のめくるめく興奮は今でも忘れないが、未成年の子どもに過ぎない在学生徒が、ただの一個人の力で盗みをやりおおせたデュエル・アカデミアの万全の警備体制とやらを、頭から信用する気にはなれなかった。 武藤遊戯のデッキには、決闘者たちの弱い心を揺さぶり、惑わせるだけの魅力がある。力の誘惑を囁きかけ、かのデッキの力さえあれば、自らもまた決闘王のように強くあれるはずだと錯覚させる。 しかし所詮は他人のデッキだ。いくら人並み外れた記憶力の持ち主が遊戯の決闘をパーフェクトにトレースし、強力なカードを手足のように扱うふりができたとしても、デッキを組んだ武藤遊戯本人にはなれない。 海馬モクバの手前だ。もちろん、できるだけわざとらしく聞こえないように、意外そうな演技をした。 「信じられません。一体誰がそんなばかな真似を?」 「もちろん、我々だって黙って見ていたわけではない。非常警報を聞いたガードマンが犯人と思しき人物を追い詰めたとき、確かに逃げ道はどこにもなかったんだ。だが皆が見ている前で、まぼろしのように消えてしまった」 鮫島が当惑がちに繰り返した。 「まるで瞬間移動でもしたかのようにね」 「インチキな手品師の仕業か、それとも本物の魔法使いが犯人なのか。魔法――オレはデュエルモンスターズの力を現実に具現化させる決闘者を今までに何人も見てきたよ。あいつらならカードの力で追手からうまく逃げおおせるのもわけないだろうな」 モクバの疑惑が皮膚を刺す。十代は、もどかしく反論した。 「精霊に愛された人間が、カードの力を悪用するようなことがあるもんですか。オレは、架け橋の力はいつだって正しい方を向いているって信じていますから」 顔も知らない同胞たちへの信頼の姿勢とは裏腹に、十代の直感はモクバの憶測を肯定していた。同じ穴のむじなたちは、十代もまた身に覚えがあったが、力を過信しやすく、更なる高みへの渇望から心の暗い部分へずぶずぶと沈み込んでいく。闇に取り込まれ、もとからいた人物とはまったく別の姿をした怪物になり果ててしまう。 変質の線引きの瞬間を知っている。ひどく単純だ。断崖絶壁の上で、ほんの少し高く飛びあがればいいだけだ。あっという間に谷底へ墜落していく。険しい岩の壁の間を流れる黒い地下水脈の激流に身を任せ、再び息ができる陸地に打ち上げられた頃にはすべてが洗い落とされている。何も残らない。何も考えられない。静謐なまでに凍えきっていて、すぐには立ち上がることもできない。 「なにをそんなにむきになっているんだ?」 「べつに、なってません」 モクバが空になった筒型のグラスを横へやって十代を睨んだ。彼の背後から、カードを悪用する決闘者への嫌悪がたばこの煙のように立ち昇っていた。彼は今でも十代を憎んでいる。 「私の管理不足だ。氏のデッキの紛失が世間に知れれば、みなこぞってデュエル・アカデミアを非難する」 鮫島がうなだれた拍子に、栗毛のかつらがテーブルの上に滑り落ちた。十代とモクバは反射的に息を呑みこんだが、当人はもうそんな茶番はどうでもいいらしく、偽物の頭皮をつかんでコートのポケットに突っ込んだ。 「生徒たちは、いや、決闘王に憧れる世界中の子どもたちが大きなショックを受けることになる。ヒーローが剣を失くすなど、決してあってはならないことだ」 「だが、オレたちは無能じゃない。この海馬モクバの情報処理能力を舐めてもらっちゃ困るぜい」 モクバがコピーペーパーにゼムクリップで留められた写真を十代に差し出した。壮年の男性のポートレートが写っている。 「警備会社とアカデミア倫理委員会の証言をもとに怪しいやつらを洗っていくうちに、とある人物に行きついた。ミスター・ディヴァイン。シュレイダーやルブランと肩を並べる欧州でも有数の名家の現当主だ。資料にあるように、現役の政治家でもある」 歳は十代の父親と同じくらいだろう。白髪まじりの燃えるような赤毛と四角く張った顔つきで、鼻筋がはっきりと高く、若い頃はそれなりの美青年であったことをうかがわせる。くすんだ緑色の眼は濁っており、得体の知れない残酷さを秘めていた。 「この男は例のドゥームズデイ・カルトに関わりのあった人間だ。今でも変な力を持った知り合いがいるのかもしれないな」 鮫島が大きく開いた目で十代を見た。顔色が変わる。慌てふためき、モクバに向かって唾を飛ばした。 「モクバさん! その話は彼の前では――」 「オレが聞いていると何か都合が悪いんですか。鮫島校長」 「い、いや。十代君」 鮫島の目は泳いでいた。 「そうではないんだが」 十代のもとに、最近ではもうおなじみの感覚が訪れた。掛け値なしの馬鹿な子どもだった頃は知らないふりを通していた、力が及ばない、知恵も届かない、無力な両手への苛立ちがもたらす偏頭痛。ひどくもどかしい。自分ひとりだけが何も知らない道化のようだ。十代は遊戯と彼を取り巻く大人たちの前に立つたびに、廃棄したはずの幼稚さのなれの果てが自分の腹の中でまだ確かに息をし続けているのだと知る。 部屋の模様替えのさなか、蓋の表面に埃の層がこびりついた、憶えがないほど古くて薄汚い虫かごを見つけてしまったときのような――中身はとっくに死んで腐っているだろう。一体いつからそこにあったのだ?――ぞっとする感覚だった。 武藤遊戯と三年ぶりに再会し、真の卒業試験を行なったあの夜、十代は大人に成長する過程で見失っていた決闘を楽しむ心を取り戻した。腑に落ちないのは、それは子ども返りをするという意味では決してなかったはずだからだ。 「覚えていないか?」 気が付くとモクバが十代をじっと見つめていた。困惑する。 「え?」 「いや、いいんだ」 ミスター・ディヴァイン。ドゥームズデイ・カルト。覚えがないし、聞き慣れない言葉の羅列ばかりだ。それらは遊戯のデッキの行方に、また遊城十代自身になにか関わりがあるのだろうか。無意識に顎を上げて、十代は異変に気が付いた。 「先生、汗、すごいぜ」 「いや、私は何ともないが」 鮫島が不思議そうに顔面を手で触った。 「いや。校長先生じゃなくて、大徳寺先生が」 「大徳寺先生は、四年前に亡くなったはずだが」 「真っ青だ。どうしたんだろ、幽霊なのに」 「じゅ、十代君。一体、どこを見ているんだね?」 鮫島は天井を見上げて、目に見える異常がひとまずは見当たらないことに安堵し、しかし彼は十代の視線の先に何者かが――かつてオシリス・レッドの寮長を務めていた教師の亡霊が確かに息づいていることを悟った。モクバが童顔をしかめて、テーブルの下で十代のすねを蹴った。非科学的な話題はお気に召さないようだ。 「やめてくれ、そういうの。話を続けるぞ。異存は?」 「ありません」 「デュエル・アカデミア本校が設立される前の話だ。当時は名もない無人島だったアカデミア本島の掌握と、地下の遺跡に封印された三幻魔の奪取を企てたやつらがいた。闇の力で七十二柱の悪魔を操る古代イスラエル王の復活を悲願とする悪魔崇拝者どもさ。終末論を聖書がわりに、得体の知れないオカルトの研究を行い、レアカードの組織的強盗、児童誘拐、監禁洗脳、ろくでもないことをいろいろやってたカルト集団だ。母体は十二年前に解体されて、今はもうないが」 モクバが写真にうつった赤毛の老人を顎で示した。不死を渇望したかつての影丸に似た、金と権力と延命の野望を夢見るうつろな目つきだ。 「ミスター・ディヴァインは、やつらのスポンサーのリストに名を連ねていた。この男は潤沢な資産をつぎ込んで学園の設立も行っている。〈決闘淑女養成校〉デュエル・アルカディア。いわばアカデミアの商売敵だな」 「このデュエル・アルカディア校に、武藤遊戯氏のデッキが運び込まれたという情報があるんだ」 鮫島が切り出した。 「決闘王のデッキはあまりにも有名すぎて、どこにあっても完全な隠蔽は難しい。小等部の生徒でもブラック・マジシャンの名前を知っている。人の口に戸は立てられないというからね。先方とは、実はこれまでにもなにかといざこざがあったんだ。今回の一件はデュエル・アカデミアの管理不足をあげつらい、ネームバリューの失墜を狙ってのことなのかもしれない」 「だけど、あの遊戯さんのデッキに手を出したなんてばれたら、そいつらの方がまずい立場になるはずです」 「私にもわからないよ。たしかに単なる嫌がらせにしては度が過ぎている。もしかすると彼らは、武藤遊戯氏のデッキに付随する『何か』を求めているのかもしれない。遊戯氏本人にまつわる謎めいた噂もさることながら――例の千年アイテムと闇のゲームに関する噂だ――彼のデッキには、人知を超えた不思議な力が宿ると言われているのだ」 「情報が確かなら、デュエル・アカデミアはデュエル・アルカディアから穏便に決闘王のデッキを取り戻す必要がある」 モクバが言った。 「あそこは全寮制だ。入学した生徒は、外界から隔離された山ひとつぶんの敷地のなかで三年間生活を送る。陸の孤島だ。よそからやってきた人間はもれなく監視機構に厳しいチェックを受けるんだ。ただ、いくらか警戒が甘い層がある。学園の新入生さ。今のオレたちには、アルカディアの生徒として入学できるくらいの年齢で、信頼が置ける上に海馬瀬人への忠誠を『誓っていない』有能な人間が必要だ」 十代は驚いてモクバを見た。 「モクバさん。もしかして、海馬さんにまだ知らせていないんですか」 「遊戯はオレたちを信じてデッキを預けてくれたんだ。今回の件があのふたりに知れたら、兄サマは遊戯に返しきれないほどのでかい借りを作ることになる。オレは海馬コーポレーションの副社長としてデュエル・アカデミアを護る義務がある。そして海馬モクバ一個人として、兄サマの顔に泥を塗るわけにはいかない。今回ばかりはオレひとりの力でかたをつけなきゃならないんだ。そこでだ、十代。お前には貸しがあった。そいつを今返してもらう。忘れたとは言わせないぜい、十二年前の集団昏睡事件の主犯、遊城十代。あの時はどれだけ迷惑を掛けられたと思ってる」 「あの時のことは、オレだって悪いと思ってます」 十代は膝の上で両手を固く握り込んで、うめいた。 「ふたりとも勝手だ。モクバさんも鮫島校長も自分たちの保身のことしか考えてねぇ。海馬さんやアカデミアの生徒たちだってそりゃ困るだろうけど、一番つらい思いをするのは遊戯さんです。大切なデッキを商売敵同士が相手を陥れあう道具にされるなんて、ブラック・マジシャンも、ブラック・マジシャン・ガールもクリボーも、みんなきっと歯がゆい思いをしているはず」 「お前のほかにも、何人か目星をつけたやつに当たってみるつもりだ。だけどあいつらに荒事は期待できないぜい。お前みたいないかがわしい化け物と違って、普通の人間だから」 「モクバさん! 取り消して下さい!」 鮫島がテーブルを叩いて立ち上がり、これまでのへりくだった態度を忘れたかのような剣幕で怒鳴った。 「遊城十代君は我が校自慢の立派な卒業生だ。断じて、化け物などではない!」 恩師の気持ちは嬉しかった。十代は頭を振って、ゆるい苦笑いを浮かべた。 「校長、ありがとうございます。でもいいんです。オレはそう呼ばれたってしょうがない」 「十代君……」 「モクバさん。貸し借りなんて関係ない。遊戯さんのためなら、オレはどんなことでも喜んで協力します。遊戯さんと海馬さんの熱い友情に罅が入るなんて、絶対にあっちゃならないんだ」 「だから城之内じゃあるまいし、あのふたりにそういう暑苦しいのはもともとないと思うぜい」 モクバが気だるそうにぼやいた。 「オレは正直言ってまだお前のことが憎いんだ、十代。兄サマを、遊戯を、お前のことを信じたやつらを平気で騙して傷付けた悪魔なんて一生信用できるもんか。だけど今頼れるのはお前くらいしかいないんだ。歯がゆいっていうなら、オレだってそうだ」 「待ってください。たしかにオレは、あの頃ユベルの力でたくさんの友達を苦しめてしまった。だけど何があったって、遊戯さんだけは決して傷付けたりしない。そんなことをするくらいなら、消えたほうがましだ」 「気に入らないな。どの口がそんな嘘を言えるんだ?」 「そっちこそ。子どもみたいに突っかかってくるのはよしてください」 「誰が子どもで、誰に突っかかってるって」 今にも火花が弾けそうなほど張り詰めた空気のなかで、やぶにらみの目線が交わる。鮫島が険悪にしているふたりの間に割って入ってきた。 「ふたりとも落ち着いてください。口喧嘩をしている場合ではない。ちなみにそのアルカディアなんだが、困ったことに学園全体が男子禁制の女子高でね」 「……だから、なんなんですか」 十代は訝しんだ。 「頭の回転の鈍いガキだな」 モクバが必要以上に呆れた顔で十代を見下し、ふてぶてしく言い放った。 「ようするにお前は今日から、デュエル・アルカディアの女子高生になるんだよ」 葬儀は粛々と執り行われた。のっぺらぼうの聖人の行列を描いたステンドグラスを通して灰色の弱々しい光が射し込んできているが、近代的な照明を持たない石の教会のなかは暗く、美しい黒に支配されている。無垢のベンチが大勢の女生徒で埋め尽くされ、むっとした熱気が立ち込めていた。聖餐台の上で金の枝つき燭台の火がたよりなく揺れている。
神月カンナは暗視がきく眼で、幅の広い通路を隔てて座っている年長の女生徒たちをそっと覗いた。牧師の説教を浅く流れの速い川の水のように聞き流し、いまのところは進路と定期考査で頭がいっぱいだという顔をして、気だるそうに髪の束を指でもてあそんでいる。そこには同情も悲嘆も見出せず、無関心な事柄に貴重な時間を奪われていく苛立ちが感染力の強いウィルスのように増殖していた。 この学園の理事長は生徒たちに愛されることも憎まれることもなく、舞台に降りたぶあついカーテンの裏側で、誰の目にも触れないまま謎めいた登場と退場を済ませたのだ。 花で飾られた遺骸が出棺されていく。今日はくしゃくしゃのアルミホイルのような曇り空だ。まだ秋のさなかだというのに、身震いするほど肌寒かった。大気に水のにおいが濃い。じきに雨が降り出すだろう。そうすれば高原の空気はさらに冷ややかさを増すはずだ。 「どうかされたんですか? 神月さん」 モクバがくすぐったい裏声で囁いた。いや、今はミス・メアリー・ゴーランドだ。ホーリーエルフ寮の寮長を務めるデュエル・アルカディアの新任養護教諭。この三文芝居にまだうまく慣れないでいるカンナはかすかに肩をこわばらせたが、平静を装って頭を振った。 「いえ、すこし気分がすぐれなくて」 「そうね。無理もありません。入学早々こんなことになって」 ゴーランドは孤独な老人の変死体を納めた棺桶とゆりの献花を一瞥し、演技からではない溜息をついた。あたりじゅうに、鼻がかゆくなりそうなほどにきつい花の香りが漂っている。 「それに随分冷えてしまっているわ。高地の空気は身体に障りますよ。医務室へおいでなさい、ミス・神月。貴女はすこし暖まったほうがいいわ」 女教師の作り物のように白い手が肩を抱き寄せる。重たい修道服を引きずりながら校舎へ戻る道すがらに、カンナはゴーランドの耳のそばで囁いた。 「どういうことですか?」 「こっちが聞きたいぜい」 戸惑いと気だるさを含んだ地声が応えた。 デュエル・アルカディア学園の理事長ミスター・ディヴァイン――盗まれた決闘王のデッキを人知れず所持していると目された男が死んだのは、十月度の入学式から半月も経たない雨の日だった。 鋳鉄製のずんどうのストーブの奥でりんごの薪が勢いよく燃え上がり、薬品の苦いにおいが漂う医務室を温めはじめた。新任養護教諭ミス・ゴーランドの居城。じきに天板に乗ったほうろう鍋の中から湯の煮える音が聞こえてくる。 ストーブの脇に置かれた丸椅子に座らせられた十代は、魚網を投げるような大雑把さでウールのひざ掛けを押し付けられて、驚いてモクバをなんべんも見た。彼はそっけない。収まりよく物が詰め込まれた猫足のキャビネットから細かい茶葉が入ったガラスキャニスターを出してきて、鍋の湯でポットを温めている。 「勘違いするなよ。お前はまだ十九歳で、未成年の子どもだ。ガキを連れ回してる大人には社会的な義務が生まれるんだ。そうじゃなきゃ、兄サマや遊戯に頼まれたわけでもないのに、誰が好きこのんでお前なんかの面倒を見てやるもんか」 「子ども子どもって言うけど、モクバさんだってオレとそう変わらない歳じゃないですか」 「オレはお前より五つも年上だぞ。口答えばっかしてないで、少し黙ってじっとしてろ。顔色が悪い。ほんとに冷えたんだ」 モクバはキャスター付きのスチールラックの上にふたりぶんのティーカップを並べて熱いアッサムティーを注ぎ、角砂糖とたっぷりのミルクを入れた。浮かび上がってくる湯気の香りが甘いものへと変わっていく。 「ミスター・ディヴァインが死んだ。表向きには事故死ってことになってる。そうだな」 ラテン語で書かれた医学書が並んだ書棚を背にして椅子につき、モクバが自分自身に事実の確認を取るように言った。十代は、ラックの半分を占領している消毒液のポンプと水だらいを横へ除けながら頷いた。 「生徒たちはそう知らされています」 「信じてるのか?」 「顔もよく知らない男が死んだくらい、理由なんて誰も気にしていない」 「教師の間じゃ、理事長はどうも自殺したらしいって噂になってる。嫌な死に方だよ。私利私欲まみれの人生にしがみついてきた男が、あの鉛筆みたいな鐘楼台から飛び降りた」 学園本校舎の西に広がるぶどう畑を北側へ抜けると、薄桃色の花をつける低木が群生する荒れ果てた丘陵に、黒い湖を背にして、風化しかけた積み木を思わせる穴ぼこだらけの城が現れる。 かつてはこの土地を支配していた貴族が暮らしており、灯台のような形をした先細りの鐘楼台が付設されている。往時は周辺の住民に礼拝の時刻を知らせるために用いられていたようだ。現在では老朽化が進んでおり、学園生徒はこの廃城へ近寄ることを固く禁じられている。 「いまいち納得がいかないんだよな」 モクバが面白くなさそうに言った。 「お前の仕業じゃないのかよ、下っ端」 「モクバさんはなんでもかんでもオレのせいにしたがるんだから」 「変な話だぜい。不老不死の研究に手を出すような人間が、間違ったって自殺なんてするもんか」 「なんか、どっかで聞いた話ですね」 モクバは両手でティーカップを包み込み、紅茶を吹いて冷ましている。猫舌らしい。 「そりゃ聞き覚えはあるだろうさ。前にも言ったけど、ミスター・ディヴァインはとあるカルトの信奉者だったんだ。手にした人間に永遠の命を授けてくれるっていう三体の悪魔を崇め、人類の滅亡を信じていた。幻魔信仰。教団の創立者のひとりは、昔お前が決闘で負かした影丸だ」 童実野町でモクバに出会ったあの夜、彼の口からアカデミア本島と三幻魔を渇望するうさんくさい教団の実在が語られたときに、かつて不死の夢に溺れていた旧知の老人の影がそこへ密接につきまとっている事実に感付いておくべきだった。この国へ帰ってきてからというものの、うまくいかないことばかりだ。 大徳寺は姿を見せない。あの恩師は都合が悪いときに良くそうするように、猫の胃袋の中で嵐が過ぎ去っていく時をじっと待っているのだ。 「その『なんで今まで言ってくれなかったんだ』って顔」 モクバは呆れているようだった。 「べつに、そんな顔」 「昔、オレの仲間のひとりなんだけど、お前にさらに輪をかけて馬鹿な男がいてさ。そいつがよくやってたんだ、その顔。まあ、そんなことはどうだっていい」 モクバが、張り替えられたばかりの染みひとつない壁紙に漠とした目をやって、片手でぼさぼさ頭をかき混ぜた。 「オレの調べじゃ遊戯のデッキを盗んだ犯人は間違いなくあのディヴァインってじじいだったんだ。やつが死んじまったんなら、デッキは一体どこへ消えたんだ? まさかあの世まで持っていったはずないし、そんなら絶対に『あいつ』が黙っちゃいないだろうし」 「『あいつ』って?」 「あいつはあいつだ。お前もよく知ってるあいつさ」 「はあ」 「今回の一件は、警察の立ち入りを好まない学園側が適当な理由をつけて早々に片付けたって感じだな。本当にただの事故だったのか、それとも公にはしたくない事情があったのか。たとえば、私怨を持った誰かにやられたとかさ。今の時点じゃ、正直オレにも判断がつかないぜい。偏屈者のカルトじいさん、勝手やってばっかりで敵も多かったみたいだ。はじめから関係者を洗い直す必要があるな」 「あの。モクバさん」 「なんだ、下っ端」 「理事長のじいさんが恨みを持った人間に殺されたにしても、ただの事故死だったとしても、どっちにしたってあの人のデッキは今、家主がいなくなった家のどこかに隠されたままでいる可能性が高い。ならオレが、すぐにじいさんの家に乗り込むぜ」 十代は軽く拳を握って椅子から身を乗り出した。向かい合ったモクバと鼻先がくっつきそうになる。 「オレにまかせてください。遊戯さんのためなら、オレはいつだって力の出し惜しみなんてなしだ」 「近い。うざい。暑苦しい。あらいやだはしたないですわ、ミス・カンナ。お前って、なんだかそのうち遊戯のために身を滅ぼしそうだな」 事務机の書類の束の上に肘をつき、モクバが溜息まじりに不吉なことを言った。 夜が訪れ、星空の高いところから細い月が荒涼とした土地に銀色の光を投げかけている。遮蔽物のない丘陵を背の低いエリカが覆い尽くしており、薄桃色をした無数の花々が、鋭く凍てついた風に撫でさすられて従順に頭を垂れていた。 『なんだい。柄でもない気の遣い方なんかして』 ユベルが不定形の闇の翼で十代を包み込み、軽蔑もあらわに鼻を鳴らした。 「だって、しょうがないだろ」 十代は言い訳がましく口を開いた。 「モクバさんはおまえを見たらきっとびっくりするからさ」 『最近のキミは変だ。あの頃みたいな、優しく甘やかして欲しがっている子どもの顔をしてる』 「おかしなことを言うんだな」 内心ぎくりとする。子どもがえり。幼稚で孤独な遊城十代の再来。 『図星だな』 「べつに、そんなじゃ」 十代は口をつぐんだ。今は口喧嘩をしたい気分ではなかった。ユベルも心得ていて、愛すべき脆く壊れやすい生き物を慈しむ視線を一度くれただけだった。 『その罰当たりな修道女の仮装、なかなか似合っているじゃないか。そこいらの小娘どもよりキミが一番美しい』 「よせよ。からかうな、ばか」 『ふふ、照れるな。ボクの目は確かだ。本心さ』 「無駄口は終わりだ。行くぞ」 奇妙な飾りが彫られた一対の象牙色の柱の間に、黒い鉄の門がそびえ立っている。その脇に、長いローブをまとって椅子に座った老人の像が建っていた。石の本を抱き、夜風にあたってくつろいでいるような気取らなさで、不毛の荒れ野を向いている。 門を飛び越えた先には、生け垣に挟まれた赤い舗装路が伸びていた。よく手入れされた芝生の広場へと続いており、夜風に乗って庭園に植えられたラベンダーのにおいが漂ってくる。まるい石造りの噴水を囲んだ迷路園を抜けると、赤煉瓦の邸宅の正面に出た。 主を失ったディヴァイン邸は孤独にたたずんでいた。四階建てで、この学園にはよくあるように鐘楼を備えている。重苦しい威圧感を放つ壁面を、レース編みに似た透かしが入った石柱が飾っている。左右四対に並ぶアーチの中央に玄関が設けられており、デュエル・アルカディア監視機構の制服を着た女がひとり、直立不動の姿勢で見張り番をしていた。 「ユベル」 『ああ』 ユベルの虹彩異色の瞳が、深海生物の誘引光に似た冷たい輝きを放った。悪魔の力が見張りを昏睡させる。倒れた女のポケットから鍵を奪い、ごく穏便に屋敷のなかへと侵入した。 玄関ホール正面の黄土色の壁には、馬に乗り剣を振り回して闘っていた時代の戦争を描いた四枚の絵画が掛けられている。長方形の平らな木板を張り合わせた飾り天井は高く、扇形にくぼんでおり、礼拝堂のような印象があった。屋敷のつくりそのものは学園校舎と似通っている。 メザニンを経て二階へ上ると、歩く度に木の床が甲高い音を立てて軋み、冷や冷やした。玄関先でのびている見張りのほかに人の気配はない。よく磨かれた廊下が、縦長の窓から射し込んでくる星の光を受けて白く輝いている。 目についた扉を開けると、部屋は屋敷の主の書斎のようだ。ディヴァイン一族歴代当主の黴くさい肖像画が並んで飾られている。 さっそく家捜しに掛かった。黄色い電話帳の上に乗った骨董品のような黒電話、半分水が入った水差し、デスクの引き出しには手垢のついた万年筆が入っている。とくに目立ったところはない。暖炉の上に銀の盆と燭台、みずみずしい山百合の花瓶。これも関係ない。 部屋のあちこちに乱立している写真立て。被写体のなかには肖像画の人物も幾人か見受けられた。生前のミスター・ディヴァインも写っている。彼は妻と思しき日傘を持ったドレス姿の女性の肩に手を回していたり、ミニチュアメダル付きのブラックタイを着用した男とかたい握手をしていた。 多くの退屈なポートレートの集合体のなかに、顔を黒く塗りつぶされた子どもの写真を見つけた。十代は異様な写真立てを手に取って怪訝に目を細めた。背景が色褪せている。十年は昔に撮られたものだろう。 「なんだ、これ」 この家の子どもだろうか。上等の服を着て姿勢を正し、利発そうに振る舞っている。だが顔立ちも髪の色も油性マーカーの黒一色で覆われており、正体はわからなかった。
|
||
 |
 |