 |
 | |
|
『あの方が私に、口づけしてくださったらよいのに。』 (旧約聖書『ソロモンの雅歌』 一章二節) 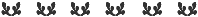 氷漬けの青魚や身が詰まった硬い冬の果物や、蒸れた人の体皮が放つ汗のにおいが混ざりこんだ熱い空気のなかで、スピーカーがスーパーマーケットの陽気なテーマソングをがなりたてている。
店内はつめ掛けた買い物客でいっぱいだ。ショッピングバッグを抱えた黒い群れのなかから苦労して抜け出した十代は、〈ゴーゴーストア〉のロゴが入った買い物袋を片腕にまとめて下げ、空いたほうの手で折りこみの広告をひろげた。 特売品にマーカーで印がつけられている。トイレットペーパーと電球。ボトル入りのシャンプーと洗剤、四人分の食料品。これで伯母からの頼まれものは終わりだ。 双六は武藤家に男手が増えたことを手放しで喜んでくれた。目じりの皺を深くして、温厚そうな笑顔を浮かべている。 「ワシゃ、まだまだ力持ちじゃ。水ものの袋をひとつ持とう」 「無理すんなって。じーちゃんは腰が悪いんだから」 「それじゃ若者の厚意に甘えるとするか」 「それにしてもじーちゃん。二年前にオレが修学旅行で童実野に来たとき、ひさしぶりだとかなんか言ってくれればよかったのに。急にほんとのじーちゃんだって言われても、まだからかわれてる気がする」 「七つの子どもを十年も見とらんかったら、ワシだってわからん」 「オレが七つのときに会ったの」 「十代や。時を待つのは大事なことじゃよ。遊戯だって、何年もの長い時間をかけて、あのパズルを完成させたんじゃから」 双六は含みのある言い方をして、片目をつむった。 かの有名な、途方もない闇の力が宿ると噂されている千年アイテムのことだろうか。 十代が、未来からやってきた男のバイク型デュエルディスクに乗って過去の世界へ飛んだときには、逆さピラミッドの形をした黄金のパズルが高校生の遊戯の胸を飾っていた。 現在の遊戯があのパズルを下げている姿を見たことがない。パズルの行方を双六に尋ねると、面食らったような顔になった。 「遊戯からなにも聞いとらんのか」 「え、なにって。もしかしてなくしちゃったのか?」 「まあ、それはそれとして、どうじゃ十代。腕が痛くなければ、遠回りをして帰らんか」 はぐらかすような誘い方だが、十代はたいして気にとめずに頷いた。 「うん、大歓迎だぜ」 二年前のように、双六が少年時代の遊戯が繰り広げたあまたの決闘譚を聞かせてくれるのが楽しかった。それは子どもが寝入りばなに毛布の中で読む、希望の光が星のようにちりばめられたおとぎ話に似ていた。 しかし話の種が武藤遊戯を巡る女性関係のゴシップに傾くにつれて、双六の声は伝説を語るときよりも張りが増して大きくなり、だんだんきまりが悪くなってきた十代にもお構いなしだ。 「さっき、アレを取りあっておる女の子たちに会ったじゃろう。遊戯もすみに置けんからの。遊戯は杏子ちゃんを想っておったんじゃが、レベッカはそんな遊戯を慕っておった。三角関係だったんじゃよ。もしおまえなら、いったいどっちを取るんじゃろうな」 「あ、いや。オレ、そういうのよくわかんなくて」 「最近の若いもんは覇気がない。杏子ちゃんもすごいが、成長したレベッカもなかなかじゃ。こう、胸のあたりがとくに……若い男には刺激的じゃったろう」 「うーん。なんか、すごいんだな。あの遊戯さんに想われるって。杏子さんは知ってるのかな?」 「とっくにふられておるよ、遊戯は」 双六が平然と言った。十代は耳を疑い、袖に引っかけていたレジ袋を取り落としそうになる。 ――あの武藤遊戯が女性にふられた? 「杏子ちゃんがアメリカへ発つ日に告白してな……」 「まさか。そんなのありえないって。信じらんねぇ!」 「難しい話なんじゃが。杏子ちゃんはの、遊戯にうりふたつのもうひとりの男が好きだったんじゃよ。じゃがその人物が遠くへ旅立ってしまうと、あの娘も積み重ねた思い出を吹っ切るようにこの街を離れていった。今帰ってきておるということは、心の整理がついたのかもしれんな」 「遊戯さんは今でもその人が好きなの」 「そりゃそうじゃ。ああ見えてワシに似て一途な男じゃから、一度惚れた女を忘れられるはずもない。ずっと待っとったのかもしれんな。さて、どうなるか。杏子ちゃんがとうとう遊戯に振り向いてくれるか、はたまた遊戯がレベッカを受け止めてやるか。ワシが生きとるうちに、ひ孫の顔が見れる日が来るといいのう」 「そっか……。そういうことなら、オレ、遊戯さんを全力で応援する」 「おお、ありがとうよ! あったかく見守ってやってくれ」 双六は無邪気に微笑みながら握り拳を掲げようとして、不自然な姿勢で凍りついた。腰を押さえて、くぐもった唸り声を上げはじめた。皺だらけの額に脂汗が滲みだしてくる。 「じ、じーちゃん。大丈夫か?」 腰椎が軋む音。ぎっくり腰だ。 高校時代の友人たちと出かけた遊戯は、夜更け過ぎに帰ってきた。武藤家の玄関が開いたとたんに、アルコールの甘ったるい匂いが廊下を漂う。遊戯は迎えに現れた十代を見ると、体裁が悪そうに首をすくめた。 「十代くん。まだ起きてたのか」 「じーちゃん、腰が痛くて眠れないみたいで。オレが看てるんです」 「母さんは?」 「もう寝てます」 「よかった」 遊戯はひとりではなかった。すりきれたダウンパーカの背中に杏子をおぶっている。 彼女は酔いつぶれていた。四肢が海棲の軟体生物のようにぐにゃぐにゃに脱力しきっている。ベルテッドコートの隙間からゆるやかな曲線を描く細い首と豊かな胸が覗いており、十代は昼間の双六とのやりとりを思い出して、遊戯に気がとがめてそっと視線をそらした。 いつもより顔が赤くアルコールの匂いもするが、階段を上っていく遊戯の足取りはしっかりしている。杏子ほど無茶な酒の飲み方はしていないだろう。彼女を自室に運んで子ども用のベッドに寝かせると、ドアの前に所在なく立っていた十代を見返った。 「悪いけど、杏子を任せていいかな。じーちゃんはボクが看るから」 「遊戯さんがついてられないんですか?」 「本当はそうするべきなんだけど、怒らせちゃったんだ。顔も見たくないって言われた」 遊戯は、ばつが悪そうに微笑んだ。 「あなたにそんなふうに言える人いるんですね」 「ああ、子どものころから彼女のそういうところに憧れてる。ボクは居間にいるから、何かあったら呼んでくれ」 「はい」 遊戯が部屋を出て行ってから、初めて彼の領域に入れてもらったのだと思い当たった。どぎまぎしながら室内を見回す――棚に飾られたラジコンカー、うっすらと埃をかぶったクリスマスのスノードームや、机上のブックスタンドに差さっている黄ばんだ学校の教科書。十代よりもひとまわりほど年上の大人には似つかわしくない、多くの玩具が置かれている。 まるで子ども時代の博物館だ。家具のほとんどは主の背丈に合わない高さで、遊戯がこの部屋で生活している姿を想像すると、小人の部屋に間借りする巨人のようだった。 本棚の上に、見たことがない顔の男の写真が飾られている。頻繁に出張で家を空けているという伯父だろうか。うろうろと迷走していた十代の関心は、壁に飾られた額入りの絵の上でとまった。 星形の人物画だ。致命的に下手だが、描かれているのは遊戯だろう。幼児の手によるクレヨン書きで『ハッピー・バースデイ』と添えられている。『いつも応援しています。十代』。 まったく描いた覚えのない絵だが、紙の端には十代自身の署名が入っている。奇怪な装置に頭の内側をいじられ、大切な隣人を忘れて十年もの月日を何食わぬ顔をして過ごしてきた十代は、自身の不良品の記憶に二度目の失望と不信感を抱くことになった。 ベッドの上の杏子が身じろいだ。彼女は枕から首だけ起こして頬をこすっている。 「……遊戯?」 目が合ったとたんに、杏子は幽霊に出会ったかのように息を呑んだ。唇をわななかせ、みるみるうちに長いまつ毛の上に涙が溜まっていく。 「――アテム!」 聞き覚えのない名前を叫んで、十代にしがみついた。 「会いたかった。会いたかったよ――」 困惑してこわばってしまった十代の肩を、温もった香水の匂いのする身体が包み込んだ。涙がやってくる前の乾いた喉でしゃくりあげている途中にふと顔を上げ、彼女はようやく人違いに気づいた。 「あなた、誰?」 「えっと、遊城十代です。遊戯さんの……その、今は武藤の家に下宿させてもらってて。アテムさんって人じゃなくてすみません」 しばらく待つと杏子は落ちついて、勘違いを恥ずかしそうに詫びた。だが、酩酊の雨雲は執念深く彼女の頭上に滞留していた。初めて見たときよりも饒舌になっている。 「不思議な子ね。彼と同じ匂いがするなんて。遊戯は、きみをそばに置いておきたがったでしょう」 「どういう意味ですか」 「鏡を見てみるといいよ。私たちの大切な人に似てるの。私も、憧れてた彼に恥じない女になるんだってがむしゃらに頑張ってきたんだ。今の自分を彼に誇れる――だけど私の思い描いた彼のまぼろしに認められたからってなんなの? わけがわからないままあの人を失って、今でもわけがわからないままで、怖いのよ。わからないものは怖いの」 理性が選ばなかっただろう言葉がどこまでも上滑りしていく。酒の匂いをまとった熱っぽい呼気だけで、十代まで酔っぱらってしまいそうだった。 酒に溺れている彼ら、あるいは彼女らは、ひとときだけ違う星の生き物になる。世界中を旅するうちに、酔っぱらいの相手とはそういうものだとわきまえるようになった。 「遊戯はあの時の選択を一度くらいは後悔したのかな」 杏子は銀のバングルを飾った手首で額を覆った。長い年月をかけて水流に磨かれた石を思わせる、白くてきめが細かい肌だった。 「喧嘩したって本当ですか」 十代は静かに切りだした。杏子は悪びれもせず、「まあね」と頷いた。 「変?」 「いえ。遊戯さんも喧嘩なんかするんだって、びっくりしたんで」 「同じ学校の仲良しの友だちと喧嘩したことくらい、あなたもあるんじゃない」 「……あります。怒鳴られたり口もきいてくんなくなっちゃったり、置き去りにされてひとりぼっちになったり」 「よっぽどショックだったんだね。すごい顔してるよ」 気の強そうな瞳が細くなった。彼女の青い虹彩はリバティの女神像のようなしなやかな自信に満ちている。 「今考えるとオレが全面的に悪いんですけど、その時は何が悪かったのかわかんなかったんです。それでいじけて荒れちまってたら、友だちが命がけで迎えにきてくれて」 「いい友だちだね」 「はい。オレにはもったいないくらいのやつらです」 「似た話知ってる。城之内がね。遊戯と友達になる前のあいつもそんなだったの」 「そうなんですか。あの城之内さんも闇に堕ちて覇王に……」 「はおう?」 ひとりで頷いている十代を不思議そうに眺めて、杏子は首をかしげた。冷えたスポーツドリンクを豪快にあおり、深いため息をつく。 「喧嘩じゃないわ。ただの八つ当たり。遊戯には迷惑な話ね。私は彼の厳しさと向き合うことができなかった。だからずっと何年も見ないふりをしてきたんだって、さっきひさしぶりに顔を見たらわかっちゃったの」 まるい肩が自己嫌悪の重石で下がっている。 「昔はこうじゃなかったんだけど……何にだって体当たりで向かっていく怖いもの知らずだったわ。あの人がいないだけで、なんだかおかしくなっちゃって。みんなだってあの頃は全力で走った気になってたけど、なんか違うの。だってあの人は少年のまま、気が遠くなるくらい昔に大人になることもできずに死んじゃったんだもの。幽霊だったのよ」 人知を超えた十代の瞳は、『あの人』と呼ぶ人間を語るときにだけ、杏子の魂が軽やかな少女の姿にうつろうことに気がついた。 「幽霊に恋した人の気持ち、わかるかな。わかんないよね」 「それはわかんないですけど、四六時中愛をささやく幽霊みたいなものとひとつになった人間の気持ちならわかります。うるさいんですよ」 首筋を無数の嫉妬の針が刺す。異様な悪寒を感じながら、十代は言った。 「オレ、じつは前世はとある王国の王の息子だったんです」 十代の告白を場違いで脈絡のない冗談だと受け取った杏子は吹きだした。 「へぇ、王子様だったんだ」 「オレには従者がいたんです。そいつはオレのために自分の身体を改造して、竜になってまで守ってくれた。でもオレは人間のままだったから、そのうちぽっくり死んじまった。従者は竜だから寿命で死ぬことはないし、誰かに殺されることもない。オレが生まれ変わるまで待っててくれたんです」 「再会はできたの?」 「はい。色々あって王子と従者の魂は結ばれました。一心同体になってここにいます」 十代は胸に手を添えた。杏子は口元に手を当てて笑いをこらえている。 「あなた、作家の才能があるよ。あなたの書いた脚本で一度踊ってみたいな、私。ねえ、もし……」 沈黙が落ちた。古びた玩具が積まれた部屋に、ぬるい藻と苔のにおいに似た臭気が漂っている。 「もしもよ、出会えた王子様と従者がまた離れ離れになっちゃったらどうするわけ?」 「一度、王子は従者の行き過ぎた愛が怖くなって、遠いところへ追放してしまったことがあるんです」 「勝手だわ。ひどいことするね」 「ほんとですよ。王子は悔いて、魔法の力でふたりの身体をひとつにしたんです。もう死さえふたりを別つことはできない。王子は従者で従者は王子になって、次に離れ離れになるのはひとつになった魂が消滅したときです」 十代が語るおとぎ話の結末に、杏子はあきらかな不満の色を示していた。 「荒唐無稽っていうのかな。王子様と従者だけそんなのずるいわ。死はどんな絆だって、知らん顔して断ち切ってしまうの。あとに残るのは思い出だけ。あなたの話はなんだかルール違反よ」 「王子と従者はひとりの異物になったんです。現世のルールから弾かれて、あとは歳を取ることもなく、不死身の肉体のせいで死ぬこともない。仲間達が冥界に向かう姿を見送りながら、みんなとの絆が紡いだ世界を護り抜くために闘い続けるんです。世界のどこかには自分を受け入れてくれる人がいるかもしれない。同じ運命の人がいるかもしれない。そう希望を抱いて、ずっとこの星を放浪するんでしょう。先に果てはあるのか、何もないのか。前を向いたら眩し過ぎて、後ろの道は真っ暗だ。なにもわからない。でも走り続けるしかない」 「もうやめて。聞きたくない」 制止の声には憎しみすらこもっていた。肺から吹きあがってくる熱を帯びた吐息が、どこかのヒーローの救いようのない迷走を語り聞かせる十代を恨んでいた。 「わかってる。遊戯があの答えを選ばなければ、彼はあなたが言うふうに仲間達と一緒に年をとることもできない永遠の少年のままだったわ。いつかはみんなに置き去りにされて、ひとりぼっちでこの世界を走っていかなきゃならなかった。誰も想像さえできない孤独を受け入れなきゃならなかった。遊戯はアテムを救ったのよ」 杏子の青い目の焦点はまだぶれたままだったが、今の彼女が逃げこめる最後の砦だったアルコールの濃霧は、夜明けを待たずに過ぎ去りはじめていた。 「どうしてあなたはそんな絶望しかない物語を思いついたの」 赤みを帯びた眼球がじっとりと湿っている。杏子の長い爪が、上着ごしに十代の肩の肉に食い込んだ。不用心に開け放たれた自我の扉の隙間から、女の心の闇があけすけに覗いている。彼女の凝り固まった未練が、無数の石のつぶてになって十代の皮膚を叩いた。 「私だけが結局最後までなにもわからなかったの。遊戯も城之内も本田も海馬くんもアテムも、みんな受け入れられるはずもないことを黙って受け入れて、私の中ではまだ始まってすらいなかった物語を綺麗な光の中で完結させてしまった。私、男同士の友情だとかロマンだとかにはついていけない。だからいつもひとりだけテンポがずれてたの」 杏子は筋の柔らかい背中を曲げて、膝に額をつけて静かに泣いた。彼女の心の闇はリキュール入りのコーヒークリームのような味がした。 真崎杏子は青春時代に見た一瞬のまばゆい光の果てに、もっとも選びたかった未来のカードを落っことしてきた。それ以来彼女の人生にはやるせない喪失感が常につきまとっていた。挫折と再挑戦を繰り返した末に輝かしい栄光をつかんだときにも、鏡張りの心の部屋の真ん中には黒い風船の形をした痛みが浮かんでいた。 「ごめんなさい」 かすれ声で言った。 「いいんですよ」 「あの人が戻ってきた時に帰る場所を間違えないように、遊戯はずっと思い出の家で彼を待ってるわ。でも私、あなたみたいな子どもから見たらもうおばさんだよ。もし今帰ってきてもつり合うわけないよ。遊戯も、早く誰かと結婚しちゃえばいいのに。レベッカでもほかの女の子でも、誰だっていいよ。私、遊戯をアテムのかわりにする最低な女にだけはなりたくない」 まだ穏やかな嗚咽が続いているうちに、十代は立ち上がろうとした。杏子の脆い部分に踏みこむべきではなかったし、これ以上は彼女の涙の意味を知らない男が見ていいものではない。 形の良い手がハイネックの裾をつかんで引きとめた。十代はぎくりとした。 誰かを慕い、求め、祈る者の目が見上げてきていた。苦手な瞳だ。そこに宿っていたはずの信頼が失望に変わり、敵意にひらめく瞬間を今でも夢に見るからだ。 「どうしてそんなに暗い夜の匂いがするの。あなたじゃないの。そうならそうって意地悪しないで教えてよ――」 言葉の魔力を畏れる迷信深い古代の民のように、動物的な怯えとかすかな喜びが、杏子のぶれない瞳に宿っている。 「あなたは、生まれ変わったアテムなんでしょう」 女の腕が高貴な蛇を思わせるしなり方で十代の首に巻きついた。遊戯が好む温かい手に顎をとらえられ、艶のある赤に塗られた爪が皮膚のなめらかな部分をひっかいた。 「もし本当にあなたなら、こんなかっこわるいところ見せて……私、みじめで死んじゃう」 泣き声と、湿った熱い吐息が頬にかかる。触れた彼女の唇は塩の味がした。 白い煙が細い筋になって夜空へ昇っていく。遊戯が窓枠にもたれかかって星を仰ぎ、慣れない仕草で火がついた紙巻き煙草をくわえている。咳きこんだ彼の肩のうしろから手を伸ばし、十代はラッキーストライクをつまみあげて唇にはさんだ。 遊戯よりはうまく肺に吸いこんで、苦いにおいのする息を吐き出す。いつもは穏やかな宵の色の瞳が、呆れを含んで十代を咎めた。 「こら。だめだぞ、未成年」 「吸いません。べつに好きじゃない」 「いつから吸ってるの」 「中坊のころ家にあった父のをこっそり吸いました。煙たいだけだし、オレには合わないって思ってそれきりです。父は気づいたのかな。それとも煙草が一本なくなってることを知らないままだったか」 幼年時代の思い出を消し去られてからは、整合性を失った時系列を無意識に取り繕いながら年を重ねてきた。ワーカホリックの両親は家族の再構築をなかば放棄していたから、親に叱られる子どもというものに憧れていた。その後入学したデュエル・アカデミアでは、ドロップアウト・ボーイと呼ばれ、充分すぎるほどに与えられた不名誉だった。 「杏子は寝たの」 「はい」 「口紅がついてる」 十代は唇に人差し指で触れ、遊戯を見上げて言い訳をした。 「チューされました。人違いされてたみたいです」 「じつはボクもやられた。さっき」 「か、間接キスですか」 「それ、そういう使い方するのかな。酔うとああなんだ、彼女。えっと、聞くけど、初めてじゃないよね」 「はい」 「もてるもんね、きっと。そんなにかっこいいんだから」 「親友が外国人で」 「うん」 「男なんですけど、挨拶がわりに。日本じゃしないのかって驚いてましたけど」 「わあ、ご愁傷様」 遊戯は笑いながら十代の髪を軽く撫でた。 「ごめん」 「遊戯さんの恰好悪いとこ初めて見ました」 「ひどいな」 かがんだ遊戯が、十代の唇を柔らかくついばんだ。 「挨拶ならボクも。間接キスかな」 固まりきった十代を見下ろして、悪戯っぽく目を細めている。 「なんて。仕返し」 「どれのですか。恰好悪いって言ったことですか。それとも杏子さんのことですか」 「さあな。ちょっと意地悪がしたくなっただけかもしれない」 「キスなんかしなくても、遊戯さんが怒ったのならちゃんと謝りますから。ふつうに」 「キミはモクバくんみたいだな。大人に困らされてばかりだ。変な背伸びをするなよ。おじさんにはお見通しだ」 燃え尽きた白い灰が指の先からぱらぱらと散っていく。混乱している十代から、遊戯が赤い光を放っている煙草を取り上げて火を消した。 遊戯の意図がわからなかった。それほど酔っているふうではないが、見た目よりもアルコールがまわっているのかもしれない。 彼の心は悪魔の眼を容易にはね返すほどの強い力に守られている。記憶の世界に年下の青年を立ち入らせることはなかった。だから十代には、彼の表情や仕草の端々に滲みだしてくる感情の欠片を拾いあげて機嫌を推し測ることしかできない。 「オレ、アテムさんって人に似てるんだって」 声の震えに気づかれていないだろうか。いつもどおりに振る舞えているだろうか。 憧れの遊戯に、茶化したキスひとつで取り乱してしまう子どもだと思われるのは嫌だった。 「遊戯さんもその人が帰ってくるのを待ってるんだって。そうなんですか?」 「杏子から聞いたのか?」 「はい」 「たしかにキミはボクに似ている。だけどボクじゃない。杏子はそういう存在をずっと追い駆けてるんだ。ボクだってそうなのかもしれない」 「よくわからないけど、オレがその人になれたらよかったのに」 「ボクもそう思ってた。ボクが彼になれたらいいなって。でも人は誰かにはなれない。彼言ったよ、ボクはボク以外の誰でもないって。杏子も頭ではわかってるんだ。だけど理詰めで心を納得させることはできない。望むだけで心の部屋のイメージを塗りかえることはできない。彼女にとってボクはアテムを殺した殺人者なんだ」 遊戯は不思議な瞳で十代を射た。もう二度と帰らない者を悼み、別れを告げるときのまなざし。 彼にそんな目で見られると、遊城十代という存在そのものが、夜明け前の頼りない夢のように透きとおっていく気がした。 遊戯は日常のふとした場面で、遊城十代の人知を超えた身体能力に感心させられるときがある。新作のデュエルディスクが入ったダンボールを、華奢な腕の中に積み上げていく。とんでもなく重いはずだが、ショーケースの前をきびきびした動きで行き来する足元は危なげない。 「こっちじゃ、十代。箱を展示台の下に置いてくれ」 カウンターから双六の小気味良い指示が飛ぶ。祖父もずいぶんな歳だ。立ちあがって店を開けられるほどに腰の痛みは引いた様子だが、昔から無茶をしがちなところがあるからひやひやさせられる。 オレンジ色の看板が玄関先に出ているだけで、武藤家から寒々しい気配は消え失せていた。ここは空き家ではない。遊戯は安堵し、危なっかしい双六の助けになってくれている十代に心から感謝した。 ワゴンの上で帳簿を開いている遊戯のもとまで、ふたりの楽しそうなはしゃぎ声が聞こえてくる。 「十代や、ほれ、カプモンやらんか。遊戯が昔集めとったやつじゃ」 「うわ、やるやる!」 声のトーンが軽快に上がる。きっと十代が目を輝かせてお下がりの玩具に飛びついたのだ。 昼前に杏子が遊戯の家を訪れた。お互いが高校生だったころを思い出し、遊戯もなるだけ昔のように振る舞う努力をした。それは日の下では思っていたよりも簡単にできた。 「おじいさん、子どもっぽいとこあるから。なんだか対等に遊んでる感じしない?」 「若い子と一緒だと張り合い出ちゃって。まだ本調子じゃないのに、無理ばかりするから困るよ」 杏子の来宅を知って十代がやってきた。床に膝でもつきそうなうやうやしさで頭を下げる。 「おはようございます。おふたりとも、仲直りされたんですか?」 「うん、まあ」 杏子が作り笑顔で頷いた。十代は純朴な安堵に顔をほころばせている。 「よかったァ。やっぱり、遊戯さんが友だちと喧嘩なんてありえねぇし」 「すこし休憩にしようか。じーちゃんを呼んできてくれる?」 「はいっ」 揃えた指をこめかみに当てて敬礼し、新品の赤いエプロンを軽やかにひるがえした。 「子どもに心配されるなんて。ほんとだらしないね、私たち」 十代が戻ってきた。彼は、そこだけは譲れないというふうにむくれている。 「子どもじゃありません」 「子どもじゃよ」 腰をかばってゆっくりとやってきた双六が、横から口を出した。 「じーちゃん」 「決闘を楽しむものは、みんな子どもに戻る。遊戯もワシも、もちろんお前もじゃ」 十代は、遊戯とひとくくりにされたことがよほどくすぐったそうに首をすくめた。母親が呼ぶ声に元気よく返事をして、機嫌のいい足音をたてて駆けていく。 「十代ちゃん。ママ、ちょっとお買い物に行ってくるわね。あとで宅配便が届くと思うの。ハンコはテーブルの上に置いてあるから、受け取っておいてくれる?」 「はい、遊戯さんのママさん」 「おばさんでいいのよ、昔みたいに」 「お、おばさん」 「すっかりイケメンになっちゃって」 「そんなじゃないです。オレなんて、遊戯さんに比べたら」 「あら。十代ちゃんのほうが顔はいいし、素直だし、真面目だし、頭もよくて気がきくし。あの子も十代ちゃんくらいしっかりしてくれたらいいのにねぇ」 玄関から聞こえてくるふたりのやり取りは微笑ましい。杏子が柔らかく目を細めた。 「すれてないのね。このあたりの子じゃないのかしら」 「気を遣いすぎる子だから。それに演技がうまいんだ。どんどん真に迫ってくるな」 「どういうこと?」 遊城十代は、デュエル・アカデミア受験当時を思わせる幼さを濃く残した少年の顔を見せている。そんな仮面は、とうに身の丈には合わなくなって棄ててしまったものだ。遊戯と杏子が仲たがいをしたと知って、彼なりのとりなし方を思いついたのだろう。 「あの子はデュエル・アカデミアの純粋培養じゃからな。もともと箱入りじゃし、俗世間から離れた全寮制の島でずっと暮らしておったんじゃ」 意外に目ざとい双六は、十代の本質を見抜いているだろうか。それとも忘却があの子どもの生来の悪を洗い流した十二年前の結末を信じ、等身大の善なる剽軽者を受け入れているのだろうか。 「たしかにどこかのお坊ちゃんなんだろうなとは思ってたわ。ちょっと落ちつきがないところは城之内に似てるけど、無邪気で明るくて気持ちのいい子ね」 「杏子ちゃんはどうして日本に戻ってきたんじゃ? もしや、そこの遊戯の想いを受け入れてやる気になったとか」 双六が口をすぼめて杏子の成熟した胸を見上げた。彼なりの様々な基準と照らし合わせてから、満足そうな溜息をこぼした。杏子の赤い唇が引きつっている。遊戯は下世話な探りを入れはじめた祖父を慌てて止めた。 「じーちゃん。やめてくれよ、その話」 「いや、大事なことじゃ。十代も、おまえさんたちふたりを精一杯応援すると言っておったしな」 「嘘だろ。あの子に教えたのかよ」 どんなとりとめのない逸話でも脚色して武勇伝に仕立てあげる癖がある双六のことだから、あることないこと織り交ぜて十代に吹きこんだのだろう。あの青年は双六の悪癖をまだ知らない。すべてを鵜呑みにしたはずだ。 「遊戯や。いい歳をしたおまえにごっこ遊びは似合わんよ。あれにはもう家族のことで寂しい思いをさせるな」 一見女性に目がなく軽薄な印象がある祖父だが、いつも物事の肝心な部分を誰よりも早く見抜いている。遊戯は頷くしかなかった。 杏子がエナメルのハンドバッグから、今朝書店に並んだばかりの週刊誌を取り出した。薄っぺらい表紙を飾っているのは、見覚えのあるツーテールの少女だった。 「この娘に用があるの」 「おほぉ! この娘は――」 夢中になっている偶像の姿を見つけた双六が嬉しそうな悲鳴を上げた。しかし、間もなくぷっつりと黙りこんでしまう。大きな原色の黄文字で、『神月カンナ、武藤遊戯と熱愛発覚』と見出しがつけられていた。カンナを崇拝する祖父のじっとりとした嫉妬の視線を、遊戯は複雑な気持ちで全身に受けた。 「杏子ちゃんやレベッカというものがありながら、ワシのカンナちゃんにまで手を出したのか」 双六がしわがれ声で言った。憶測とでっちあげで構成された記事の横に、童話の挿絵のように調和のとれた写真が掲載されている。『神月カンナ誘拐事件の結末』――焼けた洋館の跡に、ひだが広がったシーツを羽織ったカンナが座りこんでいる。さしむかいにひざまずいて彼女と見つめあう遊戯の姿があった。ふたりの距離は唇が触れあいそうなほどに近い。 決闘王とトップアイドルのスキャンダルはゴシップ誌を沸き立たせていた。モクバの懸念は現実になってしまったのだ。後日、あの青年にどやしつけられることを覚悟しておいたほうが良いかもしれない。 「神月カンナ。今回のKCグランプリのMCに選ばれた娘ね。しばらく童実野町に滞在してるって聞いて……私、日本には彼女を口説きにきたんだ」 杏子が淡々と告げた。 「うちのスポンサーにカンナのファンが多いのよ。彼女の作品をいくつか見せられたわ。くやしいけど歌もダンスも素晴らしかった。まるで人間じゃないみたいに自由に踊るんだもの。あんなに伸びしろのある女の子を放っておけるわけないじゃない。いっしょに仕事をしてみたいの」 杏子は一度決めたら意志を曲げることはない。カンナを攻め落とすまで諦めないだろう。だが、『神月カンナ』が女優としての華々しい成功を望んでいるとは思えない。頭が痛くなってきた。 「プロデューサーのモクバくんに逆らえないだけで、カンナちゃんはアイドルなんてやめたいと思ってるかも」 「半端な覚悟でアイドルを目指す女の子はいないよ。断言できるわ」 「そりゃ、女の子はいないかもしれないけど」 「彼女に海の向こうの世界へ羽ばたいてみたくはないか尋ねてみるつもりよ」 トップアイドルの神月カンナにほどこされた特殊メイクの下には、十九歳の破天荒な青年決闘者の顔が隠されていた。遊戯が真実を知ったときは事件の渦中にあって、驚愕と熱狂的なファンとしてしかるべきパニックを後回しにせざるを得なかった。うやむやのまま日にちが過ぎていき、今に至っている。 「熱愛発覚らしいね」 杏子は含みを持たせた目で週刊誌の表紙と遊戯を見比べた。 「いろいろと事情があるんだよ」 「遊戯。おじいさんに似てきたって言われない?」 「何回かあるな。不本意だけど」 杏子にこれみよがしの溜息をつかれると、自分の背丈が昔のように小さく縮んだ気がした。 「彼女はまだあなたの半分しか生きてない。そっちはどうだか知らないけど、十代の女の子はいつでも本気よ。いい加減な興味は子どもを傷つけるだけ。覚えておいて」 これまでにも何度か受け取った杏子の忠告が、今日はとくに胸に染みた。彼女の不信と非難はもっともだ。気まずい沈黙が落ちるなかで、遊戯は十代のことを考えていた。 たしかにあの子どもを傷つけてばかりいる。十二年前から、彼の歩く道筋を選んで石を置き続けてきたのだ。 日が落ちないうちに、十代はガラス戸の水拭きに取りかかっていた。冬の凍てついた外気のなかでは厳しい作業だ。主人の腰の具合がかんばしくなかったせいで、満足に整えられなかった店の外観は薄汚れている。 双六が毎日そうしていたように、水を張ったバケツに白い腕を入れて雑巾を絞っていた。傷つきやすい宝石を磨くような丁寧さでくもったガラスの表面をぬぐい、雨の飛沫がはね散らかした泥を落としていく。 彼は文句ひとつ言わずに武藤家に尽くしてくれる。年下の青年にばかりつらい作業を続けさせるわけにもいかず、遊戯は手伝いを申し出たが、いつもは従順な十代がそこだけは頑として譲らなかった。 「決闘王にそんなことさせられますか。とても綺麗な手なのに、荒れたら困ります」 三十路も近い男を前にして、十代は繊細な女の子を扱うような態度だ。もしも遊戯が十代と同じ年頃で、デュエル・アカデミアの女生徒だったとしたら、きっとひとときも目が離せなかったに違いない。灰色の雑巾を絞る仕草さえ様になっている男など、彼のほかには見たことがないからだ。 「十代くんには好きな子とかいるの?」 十代の動きが止まる。 「遊戯さんってけっこう意地悪です」 「ん……そうかな」 遊戯を振り仰いで十代が微笑んだ。その笑い方をする人間を見たのは、じつに高校以来だった。同じ未来が決して手に入らないと知ったときに、今はなき半身が見せた寂しげな微笑によく似ていた。 「子どものころは手を伸ばしたら欲しいものがなんでも手に入るって思ってました。でも大人になって、そうじゃないってわかった。この手で触って汚してしまうくらいなら、オレは誰かと笑っているその人を見ているだけでいい」 十代が立ちあがり、組んだ後ろ手につかんだバケツを揺らして歩き出した。 「いますよ。好きな人。でも、無理なわがまま言って困らせたくないんです」 午後の陽光が降り注ぐ短い時間が終わり、あたりは青くなりはじめていた。点いたばかりの家の灯りに吸いこまれていく後姿を見送って、遊戯は立ち尽くしていた。 愕然としていた。思慮の浅い子どもに戻ったような気分だった。あの青年に嫉妬をしてほしかったのだ。 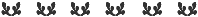 〈「アテムとソロモン(2)」につづく〉      このコンテンツは二次創作物であり、版権元様とは一切関係がありません。無断転載・引用はご容赦下さい。 −「スクラップトリニティ」…〈arcen〉安住裕吏 12.01.31− |
||
 |
 |
