 |
 | |
|
ディヴァイン家は代々護国卿に連なる貴族の名家と名高く、おおくの偏屈者ぞろいの政治家を輩出してきた。ディヴァイン青年の気性の苛烈さと自意識の高さは、元来の国民性に加えて、近親姦を繰り返してきた血縁異常にも原因があったかもしれない。 ヒースの荒野に屋敷を構えており、ディヴァインは子どもの頃、やまない雨と凍てついた高地の風になぶられて、ティーカップのなかで溶けかけている角砂糖のような形になった廃墟でよく遊んだ。 両親に化け物扱いされ、友人に恵まれず、孤独は賞賛を渇望する敵意に変わった。傷つけることでしか他人と関われない。特殊能力を持たない者たちへの残酷な侮蔑は、数と言論の暴力を秘めた、死に至るほどの大きな黒い波に攫われた彼の恐怖心から発生したものだ。 囚われの超能力者たちが父に搾取されている無惨な姿を見たとき、彼は自分の胸のなかから棄て去ったつもりでいた弱者の嘆きを感じ、激しい同類嫌悪に陥った。 それからは、ただの人間にもそれ以外の者にも平等に壁をつくり、誰彼かまわず噛みついていた。 神月カンナに出会っていなければ、彼女の神託が下らなければ――彼は父の領土にそびえる古城に幽閉されたまま、狂犬として一生を終えていたかもしれない。 ディヴァインはまず、神月カンナの、親に拒絶された境遇に共感した。彼女の中にとてつもなく濃い闇を見て、初めて人を畏れると同時に、子どもがロボット番組の新作のおもちゃを欲しがるような純粋さで手に入れたくなった。 顔も声も指の優美さも、無駄な肉のついていない身体の半陰陽の特徴も、うまそうな色の眼球と嘘つきの唇も、綺麗に色が分かれたくせ毛も、すべてが。 同類への憐れみまじりの奇妙な優しさと、ぬるい馴れ合いと生理的な反発と、相手ごと自律に含めるその境界線の曖昧さと、偶像として頂点に立つ名声、そういうもので構成された神月カンナを愛している。 彼女には赤が一番似合う。汚れた血と慈悲の炎の色。ディヴァインがカンナに感じる好意は、まぎれもない自己愛だった。 ディヴァインという男がもしも女なら、神月カンナになるはずだと信じた。彼は鮮やかな蝶に自己投影をすることで陶酔を得る、土の色をした夜蛾だった。 彼女を隣にはべらせていれば、比喩ではなくこの世界を征服できる。そのためのツールとして、彼の中ではカンナと世界は等価だ。 この世のすべてを手に入れるには、ディヴァイン個人の運命はあまりにも非力だった。たとえ世界の支配者の玉座を得たとしても、神月カンナの大いなる力が手元になければ、人類の数の脅威に怯えて暮らすみじめな末路が待っている。 彼はまぎれもなく虎の威を借る狐だ。上っ面こそは孤独な魔女をつつみこむ度量のある男を演じていたが、実のところは少女の薄くて柔らかい肩に依存しきっており、手を触れていなければ発狂しそうなほどの不安に襲われてしまう。 ディヴァイン青年は、そんな愚かな男だった。 「十代くん! ディヴァイン!」 遊戯の呼び声が倒れた材木の向こうから聞こえた。部屋は炎に包まれている。 アルコーブの書庫から立ちのぼるしけった木と古い紙が焼けるにおいを媒体に、子どもの頃の情景が断片的に呼び覚まされた。ひとりで繰り広げる決闘ごっこの背後で燃えていた、薪ストーブの慰めるような熱。ディヴァインの決闘の思い出は、すべてが痛みと孤独の記憶にかたく結びついている。 父親との決闘のさなかに、幼いディヴァインの〈ファイヤー・ボール〉のカードが実体化しなければ、まだ少しは救いがあっただろうか。空から災厄が次々と降り注いでくる絵柄を覗き込んで、無意味な自問を打ち消した。 あのとき父親は息子を化け物と呼び、ディヴァインは決闘を憎む大人に成長した。今更、詮無いことだ。 炎に照らし出されたディヴァインの足元から伸びる影が、角柱の残骸でふさがれた木の床に落ちている。それは水棲の生き物のようにぬるりと動くと、ツーテールの若い少女の姿になった。神月カンナだ。 カンナは微笑を浮かべている。ディヴァインが柔弱な迷子だった幼少期の無力感を思い出したとき、彼女は決まって訪れ、共感と信頼を示してくれる。決闘を憎み、人を軽んじ、より歩きやすい道を指差してディヴァインをそそのかす悪魔だ。異端の宣教師めいたとりすました口ぶりもあるが、男のように言葉を荒げたりはしない。 「カンナ、なぜだ。なぜあんな男をかばう」 ディヴァインは、自分の影から現れたカンナに向かって叫んだ。 「遊戯はきみの天敵だぞ。おれの言うことを聞いていればきみはもっと輝けるのに、なぜ自ら蝋燭の芯をすり減らすような真似をするんだ。答えろ、カンナ」 くずれ落ちてきた天井板を突き破って、白い指が伸びてきた。カンナの長い髪をとらえて、馬の手綱のように引く。 カンナの背後から現れた人間は、ディヴァインの白昼夢に現れる薄笑いを浮かべた不可侵の少女とは似ても似つかないが、彼女もまた神月カンナだった。藪にひそんで小鹿を狙う肉食獣の金の瞳が、能面の中央で冷たく輝いている。 カンナがカンナの後頭部を掴んで吊り上げる。まっすぐに肘を伸ばした彼女の腕のかたちを見て、ディヴァインは喉の奥で空気を圧縮するような無音の悲鳴を上げていた。うろこだ。赤黒いうろこがびっしりと彼女の腕にはりついている。 カンナは自分と同じ姿の少女の僧帽筋のあたりに、ぶあつくて錐のように尖っている黄ばんだ爪を突き立てた。柔らかい果実の皮を剥くかのように、無造作に人体をこじ開けていく。 女が解体されていく工程を目の当たりにしたディヴァインは、こみあげてきた酸い胃液を黒こげのラグの上に吐き出していた。 血は一滴も零れない。ディヴァインの影から現れたほうの神月カンナは、肢体が一枚の表皮で構成された張りぼてだ。内側は空洞になっており、醜悪な矮人がおさまっていた。 異様に大きい頭部を守る、電球をいくつもつけた鋼鉄製のヘルメットの下から、もじゃもじゃの白髪がこぼれている。灰色の死人の肌につぶらなガラス玉の目がはまっていて、耳まで裂けた口のまわりに道化めいた厚ぼったい紅をのせている。 金の瞳をしたカンナは、汚物に触れるときの仕草で幼児と老人のコラージュをつまみあげ、「おまえ、知ってるぞ」と言った。 「昔、オレに取り入ろうと城の前をうろちょろしていたやつだ――〈カバリスト〉。星ひとつの雑魚モンスターだったな」 神月カンナの蔑みは、不要なカードなど存在しないと語る遊戯の信念と相反する。それが彼女の怒りの深さを暗示しているのか、それとも星の数による絶対階級制の肯定こそが本来の彼女の価値観なのかは知れない。 『邪魔な小娘だ。もうすこしで、このディヴァイン家の恥さらしをおまえの姿で籠絡してやれたものを』 〈カバリスト〉と呼ばれた年老いた小人は、甲高い声できいきいとわめき続けている。 『薄汚い手を離せ、売女。実体化したモンスターの軍勢を率いて、この世界を私が支配するのだ』 「笑わせるな、星ひとつが」 『だまれ』と老人がカンナを睨んだ、『人間のくせに』。 『惰弱な人間の肉体から抜けだし、私は力の権化たる精霊に生まれ変わったのだ』 金属質の耳障りな声は、ヒースの屋敷の使用人頭を呼びつけてわめきちらす亡父の声にそっくりだ。 夜毎に得体の知れない錬金術の実験を繰り返し、不老不死の在り処を追い求めた男の妄執は、いつしか人知れず報われていたのだ。そこにあるのは、人としての死によって肉体を失い、見せかけの慎みと礼儀正しささえも忘れ果て、底なしに堕落したディヴァインの父親の精神の具現化だった。 ディヴァインは呆然としていたが、きいきい声で叫ぶピエロの人形を見ていると、だんだんと怒りが湧いてきた。 ――おれは、こんな雑魚にいいように踊らされてきたのか? その男が多くの犠牲を払いながら目指した、人間の世界と精霊の世界をふたつの姿で行き来する究極の生命体の姿は、あまりにもみっともなくしぼみきっている。『おまえのせいだ』と老人がディヴァインに向かって唾を飛ばした。 『こんな馬鹿な女をのうのうとさせておくからだ。今すぐに超能力を使え。カードの効果で洗脳してしまえ。手足に鉄の枷をはめて牢屋に入れろ。豚のように孕ませて、膨らんだ腹を蹴飛ばしてやれ』 「おまえに訊きたいことがふたつある」 汚い言葉を吐き続ける老人を片腕に吊り下げ、カンナが、武藤遊戯に似た正しくて残酷な口調で言った。 「道具のように人を利用して、胸が痛んだことがあったか?」 『まさか。やつらは粘土の塊と同じだ。誰かがこねまわして形を造ってやらなければならん。価値を与えてやった私に感謝しているだろうさ』 「そこにいるディヴァイン家の息子を一度でも愛したことはあるか?」 『愛だと!』 老人は、この世でもっとも卑しい言葉を耳にしたとばかりにふんぞりかえった。 『神にも等しい創造主を殺したごみを、くずを、どうして愛せるものか。言うことを聞かん失敗作は必要ない。奴の犬のような脳味噌をほじくり出して、私が若い人間の肉体を利用してやるとしよう』 カンナは老人を黙って見つめている。赤ん坊のように小さな肉体を通して、誰かのまぼろしを見出しているようだ――彼女もまた、親のぬくもりを知らない女だった。 老人はカンナを侮りきっていたが、ガラス玉の瞳を上げて、ふと不安そうに表情を曇らせた。 『いやな眼だ。おまえの金色の瞳はどこかで見たことがあるぞ』 突飛な動作でいびつな頭をもたげ、『もしや。いやまさか』、顔色をどす黒く染めた。 『闇の世界の征服者、覇王十代様は、反乱軍どもに首級を取られたはずだ――』 「嘘でも頷いていれば、命は助けてやったんだぜ」 カンナがそっけなく言った。 老人は、自らが精霊たちの間で語り継がれているもっとも呪われた時代の体現を前にしているのだと理解した。目に見えて態度が軟化し、かつて人間だったころの名残りか、極度の緊張がもたらす喘ぐような呼吸を繰り返している。 『お、お許しを。まさか生きておられたとは知らなかったのです!』 老人は金切り声を上げて命乞いをしたが、カンナに一切の慈悲はなかった。金属製のヘルメットごと、不恰好な頭を握り潰した。首から下の白衣に包まれた部分が薄っぺらい音を立てて床に落ちると、裸足のつま先を舐めていた炎が、待ち構えていたように醜い死骸を呑み込んで灰にした。 ディヴァインは恐々とカンナを覗き込んだ。彼女が怖ろしかった。人間を棄てた性悪の老人を心の底から怯えさせる〈覇王〉とは、いったい何者なのだ。 「利用されているのでもいい」 カンナが囁いた。武藤遊戯のことを言っているのだと気がつくまで、すこし時間がかかった。 「知ってたなら、なんでわからないふりなんかしていたんだ」 「あの人は正しい。本当のオレの姿を許さない。嫌われるのは平気さ。だってオレは本当に悪い奴なんだもんな。でもあの人に、みんなみたいに目を逸らされるくらいなら、消えてしまったほうがましだ――」 邪悪な精霊をくびり殺した悪鬼が、遊戯を語り始めると気弱な少女のためらいを見せる。ディヴァインは呆れ果てた。何もかもがちぐはぐだ。不安定で、この女を見ていると胸がざわつく。 「これだから、女は馬鹿なんだ」 「そうだな。オレは馬鹿だよ。馬鹿でいい。もっと馬鹿になりたい。あの人はいつもどこか寂しそうだ。だから、遊戯さんが心から嗤ってくれるような道化になりたい」 「そんなに言うなら、私も今度試してみるよ。おまえみたいに馬鹿な女を見つけて、そいつに武藤遊戯の手口を実験してやろう」 「残念だが、そんなことはできない。おまえの使命はこれでおしまいだ」 「うそだよ。猫みたいな疑り深い目をしていて、孤独で、砕けて散ったガラスのように脆くて強い、赤い服が似合う愚か者の女――そんな女、この先現れっこない。いるもんか」 カンナは意外そうに金の目を見開いて、軽く首をかしげている。 「キミってもしかして、本当にオレに惚れてるのか?」 頬が染まった。しかし、赤い炎の照り返しにまぎれてしまっただろう。 「おまえなんか大嫌いだよ」 ディヴァインはぶっきらぼうに答えた。彼女はディヴァインの心を悪魔の力で強奪していっただけだ。 本当は、神月カンナなんて好きじゃない。 「カンナ。厚意で忠告しておくが、おまえ、これ以上遊戯に関わると死ぬぞ。いつか間違いなく、あいつのせいでむごい死に方をする」 カンナは当たり前のように頷いた。たいした狂信者だ。 ディヴァインが知る同年代の少女たちは、悪い大人に利用され続け、燃えっぱなしの蝋燭のようにすり減っていくことを悲しんで毎日涙に暮れていた。 神月カンナは違う。誰かに奪われながら、こんなに嬉しそうな顔を浮かべる女を知らない。 武藤遊戯は、世界一の詐欺師だ。 「死ぬなよ。たとえみにくい半陰陽でも、お前はこの僕の初恋の人なんだからな」 ディヴァインは〈サイコ・ソード〉を実体化し、脆くなった床に突き立てた。崩落がもたらす心もとない落下の感触を拭い去ったころ、頭上からカンナの声が降ってきた。 「バイバイ、ミスター・ディヴァイン」 気だるく返事をする。「バイバイ」。今は退いてやる。さよならだ、神月カンナ。 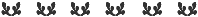 灰色の積乱雲は猛烈な雨水で地表を磨き上げると、わめき疲れて静かに眠り込んでしまった。雨足は徐々に弱くなり、引き裂かれた森の木々の上に月の光の筋が細く投げ掛けられていた。
現実世界に飛び出してきた魔法の炎は木造の洋館の一棟を焼き、いまだにいがらっぽい煙を噴き上げている。柱のなれの果てのわきにうずくまっている十代を、昏睡したモクバを抱えた遊戯が迎えにやってきた。 十代は拾い集めた四十枚のカードを差し出した。すすで汚れてしまっているが、表面に目立った傷はない。 「ありがとう、十代くん」 「なにも聞かないんですね」 「なんのことかな」 とぼけたふりをしているのだろうか。それとも、デュエル・アカデミアが預かる〈ブラック・マジシャン・デッキ〉が帰還する未来を疑いすらしなかったのだろうか。 遊戯のもとには、たしかにデッキが戻ってきたのだ。 「怪我はないか?」 「それより、オレのことより、モクバさんは。あなただって」 「彼は眠っているだけだ。予選大会のほうも心配はいらない。海馬くんがいる……お兄さんのほうが。ボクの出る幕はもうないぜ」 すみに丸く焼けた痕跡があるシーツが、スリップの上から十代の肩を覆った。 まるで軟体の生き物に魂が乗り移っているかのように、四肢が痺れて感覚が薄い。おそらくはあの工具めいた無骨な形の髪飾り――封印装置を力に任せて破壊したペナルティだろう。 遊戯が、女性に向ける柔らかいやり方で、空いた手を差し伸べてくれた。自身の姿をかえりみて、十代は苦笑いをするしかない。 「変ですよね」 「そんなことはないさ。よく似合ってる」 「いえ、あの。そうじゃないんです。あなたには、女の子の扱いをされてもぜんぜん嫌じゃないのが、その。あいつにされたときはすげぇ嫌だったのに」 妙なことを口走ってしまった後悔が、十代の首をゆっくりと絞めあげた。驚いたことに遊戯の失笑の気配はない。吐息の温かさが感じられるほど近くに彼の顔があった。 風の音が消える。胸の内側がさざめいていた。言葉にならない衝動のままに、瞼を閉ざす。 群れからはぐれた象を連想させる黒いヘリのローター音が、中庭の方角から響いてきた。 十代は瞬時に正気を取り戻した。顔を真っ赤にして、胡乱な予想を打ち消す――キスされるかと思った。 大柄なヘリの外装には、海馬コーポレーションのロゴが見て取れる。拉致された海馬モクバと神月カンナを救うために、グランプリの特設会場から飛んできた機体だ。遊戯の横顔をそっと覗くと、どこか照れくさそうに見えた。 「よかった。キミを取り戻せて」 シーツ越しに大きな手が肩を支えてくれている。温かい力が伝わってきた。 10
「きみの国の料理だろう」と男は微笑んだ。突然おにぎりを渡された少女は、困惑しているようだった。 「食べなさい。口に合うかはわからないが、そんなに腹が減っているのなら悪くはないだろう」 「おかしな男。おまえは私が魔女だと知って、どうしてつきまとう」 「私はきみには及ばないが、我々は少し似てるんだ。その力は、きみがなすべき使命を果たすために与えられた力。きみは選ばれたんだ」 男が言った。 「今のきみは怯えているだけだ。自分の力を理解しようとしない親に、力無きやつらみんなに、この世界じゅうにね。きみは孤独で、だけど孤独を貫ける程にきみ自身を信じてもいない。手にした力の来し方行く末を怖がっているきみが振るう拳は、本来ならきみ自身へ向けられるはずだった苛立ちに他ならない。誰のためのものでもない。八つ当たりさ。 きみの痛みはきみ自身に向けられるものではない。そんなもの、どこかにぶつけてやればいいんだ。その自傷行為を早くなんとかしないと、そいつはいつかきみ自身の肉体も魂さえも食らい尽くしてしまう」 少女は、けだもののようにすごんだ。 「そんな御託はどうでもいいの。私は壊したいだけ。全部ぜんぶ、何もかも!」 男は呆れたようだった。 「おばかさん」 「なんですって!?」 「きみの才能はたしかに素晴らしいが、きみ自身が使い方を知らないのでは無意味なんだ。これからきみは、もう他人に怯えなくていい。私が立って、小さなきみを心ない目から隠してあげよう。もう道に迷うことはない。私が正しい行き先を示してみせてやるから。頭の中に自分や他人を責める言葉しか思い浮かばないなら、もう考えるのはやめたまえ。そうしたって私はきみの父親のように叱らないし、デュエル・アカデミアの同級生たちのように迫害もしない。彼らの代わりに信じ、導いて、おまえのことを絶対に守ってあげるよ」 少女は驚いて、壊れた音響機器のように、「あなたが、私を守る?」――男の言葉を繰り返す。 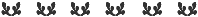 〈ブラック・マジシャン・デッキ〉の盗難騒ぎからしばらく経ったあと、昨日病院から退院したばかりの海馬モクバが、商談用のスーツ姿で武藤家の居間の硬いソファについていた。
「もう平気なんですか?」 「ああ」 十代から温かいココアを受け取ると、両手でマグカップを包み込んで吹いて冷ましている。 彼は、いかがわしいカードの魔力に精神を蝕まれていた間の出来事を何も憶えていないらしい。 操り人形に貶められていたとはいえ、もしも人の形をした生き物に向かってトリガーを引く感覚が指に残っていたなら、生々しい罪の意識が彼を打ちのめしていただろう。モクバに多くの引け目を感じている十代は、彼の生白い両腕に重い荷物を預けずに済んだことに安堵した。 今朝の新聞には、シュレイダー社によるデュエル・アルカディア学園の買収に関する記事が小さく掲載されていた。レオンが学園理事会の老人と握手を交わしているモノクロ写真には、短いキャプションが添えられている。『〈デュエル・アルカディア〉、気高き決闘淑女を育む薔薇と純潔の園』。 「レオンには、友だちを騙すような真似をさせて悪かったと思ってるけど」 モクバは、ばつがわるそうに言った。 「あいつ、ディヴァインの助けになりたいってのも本心だったんだろうと思う。口先だけの嘘じゃなくてさ。本気でデュエル・アルカディアの後ろ盾になるつもりでオレたちに協力してくれたんだ。相手には伝わらなかったようだけど」 郊外の屋敷の焼け跡から姿を消したディヴァインは、学園には戻らなかった。彼の行方はわからないままだ。 「見つけたらぶん殴ってやりたいぜい」とモクバが言った。まだ熱いココアを諦めて、安物のチョコレートスナックを皿の上にあけている。 「じーさんは、なんで遊戯さんのデッキを盗んだりなんかしたんでしょうか」 「あのデッキには、闘いに明け暮れる戦士の魂を鎮める力が宿ってるって噂されてるからな。まあ、実際、そんなこともあったんだけど。ディヴァイン老人を擁護するつもりはまったくないが、あの男が手掛けていたサイコ・デュエリストとやらの研究は、もともとは息子から変な力を切除して普通の人間に戻すために始めたようだ。それが、やがて大きく脱線していった」 わけのわからない超常現象の正体を追い求めるうちに、デュエルモンスターズが孕む美しいまでの強さに魅せられ、力の誘惑に呑み込まれてしまった。 人の心を失くした男は、何よりも大切だったはずの息子を疎んじるようになったが、最初の目的を忘れてはいなかった。手段が目的にすり替わってしまったのだ。悪いものがあの男のなかに入りこんだのかもしれない。 「力で傷つけてしまった父さんが、それでも助けようとしてくれてたことがあったなんて、息子のほうは知らなかったろうな。あいつ、自分はずっとひとりぼっちだって思いこんでたから。昔のオレにちょっと似てたんです」 人知を超えた力を宿した人間に出会うと、孤立していた過去の自分の姿を重ね合わせてしまう。血を流しながら宿命の重石をかかげる彼らに手を貸してやりたくなってしまう。十代は悪い癖を自覚して顎を引いた。 デュエル・アカデミアを卒業をしてから、人と精霊の架け橋になりたいと願って世界中を飛び回っている。役割を果たせたことはまだ少なかった。 モクバが、十代をじっと見つめている。 「なんか、オレの顔についてます?」 彼はまごつく十代に、赤いラッピングフィルムで包まれた箱を荒っぽく押しつけてよこした。『メリー・クリスマス』と刺繍が入った緑色のリボンが巻かれている。 「おまえにはいろいろと世話をかけた。じゃあな。十代」 しかめ面をそらして、ぬるくなったココアをあおり、慌ただしく去っていく。彼は大企業の副社長のポストにあり、秒刻みのスケジュール表に従う多忙な人間なのだ。 『下っ端』ではなく名前で呼ばれたことに驚きながら、十代はプレゼントの包みをほどいた。箱のなかから、以前モクバにカタログをせがんだノートパソコンが現れた。本体のカラーリングは赤だ。 むずかゆい心地良さがやってきた。ゆるんだ顔で蓋のシートを軽くひっかいていると、キッチンから遊戯が出てきた。彼は空っぽのマグカップとソファを交互に見て、呆れたような感心したような顔つきになる。 「相変わらず忙しい子だな。あ、それ、パソコン」 「はい。モクバさんからです」 「恰好良い。よかったな。ちゃんとお礼を言っておくんだぜ」 十代は頷いた。遊戯が淹れてくれたコーヒーは、熱くてかすかな苦みがあっておいしかった。 「キミはパパとママに顔を見せに帰らないのか?」 「母にはもう新しい家庭があるし……父も今度再婚するみたいなんです。ふたりとも新しい生活を始めています。オレの帰る家はもうありません」 失われた家族の話を遊戯にするべきではなかった。退屈な身の上話は居心地の悪い思いをさせるだけだ。曖昧な微笑みを浮かべて、頭を振ってごまかした。それは遊戯がよくやる仕草だ。 なくそうと努力している癖のひとつで、無意識に相手の話し方や身振りを真似ていることがある。 「精霊と人間の架け橋役をやりながら、また気の向くまま旅を続けます――逃げてるわけじゃ、ないですけど」 「そうか。おじさんもおばさんも大変そうだ」 遊戯は年長者の穏やかな理解を示して頷いてくれた。息を吹きかけるたびに揺れるカップのなかの水面を見つめながら、十代は引っかかるものを覚える。 「遊戯さん、オレの両親のこと知ってるんですか?」 「そうだ、うちに来るといい。じーちゃんも助かるし、母はイケメンが大好きだ。キミだって新しい生活を始めればいいんだ」 「そんな。そこまで遊戯さんに甘えられません」 十代は驚いて、「子どもじゃないんだから」と言った。 「遊戯。帰ってるの?」 住居側の玄関口から、年配の女性の声が聴こえてきた。遊戯の母親だろう。 居間に現れた彼女は、緊張でこわばっている十代を見ると軽く口を覆い、予想外の反応を見せた。ごく近しい人間へ向ける種類の笑顔を浮かべたのだ。 「十代ちゃん。久しぶり。本当にイケメンになって。遊戯『お兄ちゃん』の言うとおりね」 「え?」 「憶えてないの? 小さかったものねえ。最後に会ったのは十年以上前になるのかしら」 遊戯の母親は、手に提げていた買い物袋をコーヒーテーブルの上にひとまとめにして置くと、困惑している十代の前にかがみこんだ。どこか懐かしい感触の手で、まるで小さな子どもにするように頭のつむじを撫でてくれた。 「家にはずいぶん帰ってないんでしょ? お母さんがとっても心配してたわよ。そう、連絡。神月のお家に電話を入れないと」 遊戯の母親は見知らぬ番号にダイヤルを回した。受話器から零れてくる、数年ぶりに聞く、もう二度と耳にすることはないだろうと思っていた懐かしい声の主と親しげに会話を始めている。 十代は戸惑いながら遊戯を仰いだ。 「ゆ、遊戯さん」 「うん。知ってた」 ここで遊戯は十代が知らない顔を見せた。そのときの彼は、とりとめのない手品の種をそっと明かそうとするにわか手品師であり、ずっと前に教えた不正確な教訓を苦笑まじりに取り消す気のおけない友人だった。 「あの頃はボクもびっくりした。まさかあの未来から来た背が高くて恰好良い大人の十代くんが――ボクのいとこの、まだ七つの小さな男の子だったなんて。ずっと心配していたんだ。キミが知らない未来の話をして、変な奴だって思われたらどうしようって怖かった」 「そ、そんなこと、絶対にありませんから!」 「うん」 遊戯は人懐っこそうな笑顔になって、大きな手を十代の頭の上に置いた。優しげだがどこか醒めたふうだった印象が薄れていく。穏やかな厳しさがなりを潜めると、彼はいつもよりもずっと若く見えた。 「キミはボクにとって特別なんだ。とても大切に思っている。あの頃のこと、初めて出会った頃のこと、キミは『とても小さかったから』、よく憶えていないかもしれないけど――ううん、いいや。これからもよろしくね。遊城十代くん。あと、それと」 母親が長電話のサインを仄めかしてキッチンへ向かうのを見計らって、遊戯は長方形の紙箱を十代の手に握らせた。パッケージには体温計に似た細長いスティックの写真が印刷され、〈妊娠検査薬〉と表記されている。 「か、買ってきたんだけど。大丈夫なのか。わかるかな、使い方とか」 「な、何もされてませんってば!」 十代は後ろ髪を逆立てて叫んだ。 「やっぱり、オレ、いやです。い、い、いちばん好きな人じゃないと、そういうのは――」 心の部屋の片隅で埃をかぶっている、幼稚なまま留め置かれていた部分を、十代はやりきれない気持ちで直視する羽目になった。遊戯の前では、彼と肩を並べる者にふさわしい振る舞いをするべきだ。今は形だけでもいい。憧れの偶像に未熟な子どもだと思われたくはなかった。 しかし焦る気持ちが延々とスライドしていくばかりで、うまい取り繕い方も忘れてしまった。これでは、ようやくままごとを卒業したばかりの初心な少女だ。ディヴァインに笑われるのも無理はない。 「いいから使って」 遊戯は聞かなかった。 「遊戯さん!」 「頼むから安心させてくれ。女の子の恰好をしたキミがあんまり可愛かったから、心配でしょうがないんだ。あんな男に奪われるくらいなら……ボクが、その、ちょっと考えちゃったぐらい、なんて――ごめん。や、やだよね。ボクみたいなおじさんなんて」 照れかくしに頬を緩める遊戯の心を、十代はなにひとつ読み取ることができなかった。彼は身の丈に馴染まない女の扱いを受けて傷つけられた十代を、慰めようとしてくれているのだろうか。大人びた冗談を言って、屈辱に耐えて涙をこぼした記憶を、おかしみのある笑い話に転化しようとしてくれているのだろうか。 それとも、そこには僅かばかりでも真実が含まれているのだろうか。 彼とごく間近で向かい合っていると、あの夜の濃密に感じられた空気と、彼が焼け落ちた洋館で十代に手を差し出してくれた瞬間に早く短くなった心音が蘇ってくる。 あのとき遊戯は十代に、本当にキスをするつもりだったのだろうか。もしそうなら、なぜそうしようとしたのだろう。ひとまわりも年下の遊城十代を、ヒーロー・デッキを、半陰陽の肉体を、武藤遊戯はいったいどう思っているのだろう。 口にすることをためらう問いかけが、胸のうちに次々と浮かんできて苦しかった。迷宮の形をした感情の渦の底で溺れてしまいそうだ。 「遊戯さんなら。いえ、遊戯さんに、オレ。だって、ずっと、ずっとオレはあなたのことが……」 整った鼻梁と薄くて柔らかそうな唇に見惚れながら、夢でも見ているような気分で十代は言った。 遊戯は困惑していたが、それは悪いものではないと伝わってくる。ふわふわした緊張と、甘いにおいのする戸惑いと、わきまえのない期待で微動もできなかった――武藤家のドアチャイムが、けたたましい音を立てて鳴るまで。 よく磨かれた床をせっかちそうに踏み鳴らし、レアカードばかりのショーケースの間を抜け、眼鏡をかけた金髪の女性が居間に飛び込んできた。二十代の半ばほどに見える。彼女は十代には目もくれず、若い大型犬の無邪気さで遊戯の胸へ突撃していった。 「ダーリン! 会いたかったよ。えへ、来ちゃった。今度という今度はワタシのこと好きって言って、プロポーズしてくんなきゃ、アメリカには帰らないんだから」 押し倒した遊戯の腹の上にまたがり、うっすらとそばかすの残った頬をよせて、ごく当たり前のように顔じゅうにキスの雨を降らせる。 十代は、子どものころ、テレビの画面越しに彼女を見た覚えがある。非公式の試合において武藤遊戯に黒星をつけたという伝説さえ存在する決闘者、レベッカ・ホプキンス。海馬コーポレーションに所属する今となっては公の場に姿を見せなくなったが、かつては無敵を誇った元全米チャンピオンだ。 ここでようやくぽかんとしている十代を見返って、鈍感な観客を軽蔑するかのように鼻を鳴らした。 「だあれ? このみすぼらしい男の子!」 遊戯は肘で這うようにしてレベッカの下から抜けだすと、人間の顔面を舐めまわしたくて仕方がない犬を相手にするように、迫ってくる肩を押さえて彼女の突進を受け止めた。子どものご機嫌を取る大人の表情は、十代へ向けるものともよく似ている。 「レベッカ。久しぶり。教授は元気?」 「うん、おじいちゃんぴんぴんしてる! また研究で、今回は中東のほうに出掛けてるのよ。あ、そうだ。そこで会ったの」 レベッカが、カードショップへ続いている開け放しの入口へ向かって叫んだ。 「杏子! ダーリン帰ってきてるよ!」 遊戯が、あからさまに動揺する。 決闘王でもうろたえることがあるのだと十代は驚いた。無人の博物館を訪れ、すでに死に絶えてしまった種の獣の巨大な肋骨のアーチの下から、からっぽの頭骨を見上げるような気分になった。 ほどなく、気まずそうな顔をしたひとりの女性が部屋に入ってくる。 つややかな黒髪を肩のあたりで切りそろえ、よく身体を動かしているしるしに、長い四肢は山岳地帯に生息するひそやかな草食獣のように引き締まっている。非の打ちどころのない容姿をしていたが、大きな瞳は正しい道を探し疲れた迷子のように揺らいでいた。 「……久しぶり。遊戯」 「うん。あれ以来だっけ」 「ここは、変わらないね」 「そうでもないよ」 ぎくしゃくしたやりとりだ。ふたりは、一目見ただけでよそ行きの作りものだとわかる、柔和な微笑を浮かべていた。どちらも嘘をつけない性格をしているらしく、顔面の筋肉がこわばりきっている。 この女性は何者なのだろう。決闘者のにおいはしないが、彼女は姿を見せただけで、武藤遊戯を気おくれする哀しげな虚弱児に変えてしまった。 「私、しばらくこっちにいるんだ。また遊びに来ちゃうから。昔みたいに」 「また会えて嬉しいよ、杏子」 遊戯と杏子は同時に右手を差し出し、ぎこちない握手を交わしあった。 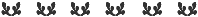 〈「アテムとソロモン」につづく〉      このコンテンツは二次創作物であり、版権元様とは一切関係がありません。無断転載・引用はご容赦下さい。 −「スクラップトリニティ」…〈arcen〉安住裕吏 12.12.31− |
||
 |
 |
