 |
 | |
実体化した〈サイコ・ソード〉がモニターに吸い込まれていったとき、十代はケイビング用のロープで両手首を縛り上げられ、ベッドの前脚の一本に買い手を待つアラビアの女奴隷のように繋がれていた。暴れ疲れたせいでぐったりとしていたが、赤毛の後ろ頭を嗤ってやった。 煙を吹いて沈黙したテレビを蹴って、ディヴァインが忌々しげに歯をむき出した。 「なんだ。このくだらない茶番は?」 マットの端に腰掛けたディヴァインが振り向き、八つ当たりの手が十代の頬を張った。笑いものにされたのがよほど気に障ったらしい。 「約束破るあんたが悪いよ、ディヴァイン」 罵声と呪詛で枯れきった喉でそう言って、十代はにやりとした。 「約束は守らなきゃ」 「黙れ。頭が空っぽの化け猫ふぜいが、優しくしてやっていたらつけあがりやがって」 「そっちこそ化けの皮が剥がれているぜ。ミスター」 「おまえは、どうやら痛い目を見ないとわからんようだな」 低く絞られた野獣の唸り声と、腰に伸びてくる腕。これから何をされるのかはわかっているつもりだった。深い怒りに彼なりの折り合いをつける行為だ。とてもおぞましいことだ。 嫌悪感から反射的に肩をひねると、皮膚にロープが深く食い込んでできた、這いずりまわる黒い蛇を思わせる痣があらわになった。臍のあたりをまさぐりはじめた手のひらの不快さに奥歯を噛んで耐えながら、脳裏にちらつくイメージがある。デュエル・アルカディア学園の焼け落ちたディヴァイン邸で見た体感幻覚の風景だ。 かぶと虫の幼生のように白くむっくりと肥った人間が、背骨を曲げて横たわっている。腹はまるく膨らんでおり、妊娠していることはあきらかだ。死んだ同類の女の忠告と、まぼろしの登場人物のチョコレート色の髪を思い出して、諦めに似た推測が降りてくる。 あれは遊城十代自身の未来の姿だったのだろうか。 ――もしそうだとしても、どうってことあるもんか。 一度は幾多の嘆きを吸った土の上に這いつくばり、手をぬかるんだ血で汚して人と精霊を殺し、肉を食らって生きながらえた外道の身の、これ以上何が貶められるというのだ。武藤遊戯の平安には比ぶべくもない。今は敗北の対価を支払い、耐えるだけだ。反撃の機会はいずれ巡ってくる。 しかし、太腿の間に指を差し入れられ、女の部分に触られて総毛立った。 「……っ、遊戯さんっ――」 思ってもいなかった声が漏れた。 「なんだ。かわいいところがあるじゃないか?」 愕然とする十代を見下ろすディヴァインの嘲笑は、苛立ちを含んで神経質に甲高かった。 童実野郊外の思いがけない数の星を隠した積乱雲が、体内をせわしく駆け巡る氷の粒にヒステリックな悲鳴を上げながら放電した。窓の外は昼間のような眩い光に包まれた。 一瞬、四角いフレームいっぱいに迫った黒い影が浮かび上がる。それはサバンナに野営するテントを訪れた象の成獣のようにも見えた。 ほどなく屋敷の女使用人が控えめに扉を叩いた。ディヴァインが十代の腰の上で、不機嫌な顔つきで応じる。 「何の用だ。私は今忙しい」 「申し訳ありません、お坊ちゃま。お客様がいらしております」 「こんな夜更けに訪ねてくるような礼儀知らずは追い返してやれ」 「それが、相手はあの決闘王の武藤遊戯でございまして」 分厚い板チョコレートに似た木製の扉越しに、女の困惑の気配が伝わってくる。 「無下に追い払うわけにもまいりませんし……」 ディヴァインは果ての知れない地割れの底まで投げ込むような深いため息を吐くと、上半身を起こし、しかめ面で上着を羽織った。 「やれやれ、わかった。私が出よう。カンナ、おまえの王子様がここへやってきたみたいだ。その奇形を憧れの男の前に晒したいならわめくなり騒ぐなりすればいい。どうぞお好きに、お姫様」 ディヴァインは、なつかない猫をなだめるような媚びと愚弄を十代に向けてきた。 透けたスリップの下にあるのは、完全な男ではなくなり、女にもなりきれなかった肉体だ。十代がこの性質を恥じたことは今までに一度もない。魂の半分と共有する実体を誇らしくさえ思っていた。 しかし、遊戯はこの身体を見てどう思うだろう。 ディヴァインの言葉の棘の先に仕掛けられていた心の闇の種が、栄養たっぷりの悪意の水を振りかけられて、十代の胸のなかの柔らかい場所へ徐々に根を張りはじめている。同じ穴のむじなの前で、わずかでも弱さをさらけ出してしまった愚を後悔した。 学究らしいほっそりした惰弱な指が十代の顎をとらえた。モスグリーンの残忍な瞳に映った遊城十代の顔は、やがて恐怖に移行するであろう焦燥と動揺をうまく隠せてはいない。 「おまえは思っていたよりも馬鹿だったから、わかりやすく教えてやる。遊戯がおまえのような怪物と結ばれる未来は存在しない。あの男には栄光と名誉がある。やつは必ずおまえの半端な肉体を軽蔑するぜ。ましてやその人間未満が自分に牝臭い劣情を抱いていると知ったら、気持ち悪いとさえ思うんじゃないかな」 ウィーク・ポイントは徹底的に攻め立てるべきだというディヴァインの信条は、じつに効果的に機能していた。十代には彼の次の手を読むこともできる。 まずは言語に変換されない不定形の衝動の海を進み、自我の大空の真ん中で輝いている宝石をわしづかみにする。拠り所や勇気や誇りとも呼ばれるそれを冷えきった岩山に打ちつけ、足蹴にしてやるのだ。 誰かの魂を完璧に粉砕してやろうと企んだとき、十代ならそうしてきた。手順や必要な前準備をわきまえているからこそ、汚泥が堆積した絶望の沼によけいに深く沈み込んでいく。荷物が重すぎるのだ。相手の思うつぼだ。 「たとえばだ、カンナ。もしも何かの気の迷いで遊戯がおまえを選んだとする。世間は低俗なタブロイドを見てびっくりだ。かの伝説の決闘王の変態嗜好が面白おかしく書き立てられ、やつはいい笑いものになる。現実を知れよ。鏡を見るんだ。おまえはそのいかがわしい正体を、武藤遊戯の前に、本当に晒すことができるのか」 ディヴァインの口から語られるまでもなく、子どものころから知っていた。武藤遊戯の心に十代の指が触れることは生涯ないはずだ。遊戯のまわりには、甘い果実が、飢える心配もないほどにたくさん実っているからだ。 花もつけない毒の草を、誰がかえりみるものか。 「言ったはずだ。おまえの言うとおりにする。オレはあの人が無事ならそれでいい」 汚れ役でも、大切な恩人のためになるのは悪くなかった。 ディヴァインがわざとらしく感嘆の溜息をついた。芝居がかってはいたが、どこか狼狽を後ろ手に隠し、意識して演じているようにも見える。 「魔女だと思っていたら、とんだ聖女だ。白状すると、おまえに一目惚れをしたんだ。現代のジャンヌ・ダルク」 「馬鹿にするのもいいかげんにしろ」 「本当さ。僕は嫉妬しているんだよ。かわいい男だろう?」 にやついた頬に唾を吐いてやった。ディヴァインは詐欺師の微笑を消し、十代を床に引き倒した。馬乗りの恰好になり、青筋を浮かべた二本の腕で首を掴んだ。怒りにまかせて頚椎が折れそうなほどに力を込める。 圧迫感で涙が滲み、息苦しさから舌を突き出した。十代を絞殺しようとしている今、ディヴァインは先ほど女の性器に触れたときよりも興奮しているのがわかった。 女使用人の金切り声を引きずって、「お待ちください、いくら何でも無礼が過ぎます!」、古い廊下を大股で歩く乱暴な足音が近づいてくる。扉がはじけ飛びそうな勢いで開かれた。 「――十代くん!」 まるでテレビから抜け出してきたかのような、オープニング・デュエルのステージに立っていた衣装のままの遊戯が、部屋の入口に立っていた。美しい光。二匹のクリボー族が彼の周りで輪を描いて浮遊している。十代は呆然とした。 ――遊戯さん。 尻尾を左右に揺らしながら、旅人のあとをどこまでもついてくる懐っこい野良犬のように思っていただろう青年が、半裸でベッドに縛りつけられている光景を目の当たりにしたとき、遊戯はまず綺麗な顔に正当な怒りを浮かべて、女の仮装をした十代にのしかかっているディヴァインをねめつけた。 ディヴァインはほんの一瞬の怯みを見せたが、すぐにふてぶてしさを取り戻すと、くせの強い前髪を気取った仕草で撫でつけた。 「いくら決闘王でも、ぶしつけな訪問は迷惑ですよ。遊戯さん」 「十代くんを、なんて姿に」 「彼女はもう私のものだ。私の妻になると誓ってくれた。そうだね、カンナ」 十代は遊戯を直視できなかった。横を向いたまま黙ってうなづく。 「いったい、彼になにをしたんだ」 厳しいまなざしが、詰問を上に乗せて覗きこんでくる。こんなに険しい遊戯の声を間近で聞くのは久しぶりだ。十代はもどかしく肩をよじり、教会で頭を垂れるような恰好で懇願した。 「オレ、ここに残ります……その、変なところ見せちまってすみません。それより会場に戻って下さい。みんなが遊戯さんを待ってます」 遊戯は彼にふさわしい居場所へ戻らなければならない。今すぐだ。吐瀉物を思わせる下劣な企みで覆い尽くされた埃っぽい小部屋に、サフィールのクリームをつけてよく磨かれた靴を踏み入れるべきではない。 武藤遊戯はすべての決闘者の憧れで、たくさんの子どもに夢を与えられる人だった。昔の十代のような孤独だった幼児にも、テレビのなかから平等に微笑みかけ、決闘を楽しむ心があれば真の孤立は訪れないのだと説いてくれた。 顔と名前を黒く塗りつぶされた異物の前で、無数の憧れと期待を背負った決闘王が足を止めてはいけない。 「オレは大丈夫ですよ。だから、はやく……」 「キミは今楽しいのか?」 遊戯が静かに言った。 「ワクワクしている?」 十代は頷いた。遊戯は困った様子で、すこし笑ったようだった。 「嘘つきだね」 「嘘なんかじゃ」 「悪いけど、そんな男にキミをやれない」 ディヴァインが肩をすくめ、上着の中に差し入れた手で軽薄なプラスチックフレームの拳銃を抜いた。十代は色を失う。モクバに握らせていたグロックだ。 「やめろ! おまえ、約束したじゃないか。遊戯さんには手を出さないって」 溺れている人間がもがきながら救いを求めて両手を差し出すときのように、思いきり身体を伸ばす。手首と片足を拘束されているせいで無様に横倒しになったが、ディヴァインの腕に深い歯形をつけてやった。 相手は舌打ちを零し、袖に隠れるほど小さな端末装置のスイッチを押した。上映会のホールに集まった何十人もの小等生がてんでばらばらに手のひらを打ち鳴らすような、心もとなくて耳障りな音を立てて銀の髪飾りが弾けた。神経を侵す電流が、脊髄を伝って全身を駆け抜ける。 「十代!」 数秒の間気絶していた十代の意識が、遊戯の呼び声を拾い上げた。たしか、以前にも、同じ体験をした。急に何も見えなくなって、遊戯の叫び声が聴こえるのだ。『十代』――普段の『十代くん』ではなく。 球体の裏側へ反転した視界に、前後不覚が作り出した偽りの思い出が浮かんでいる。 ――『■■■■』と小さな十代が聞き慣れない言葉で呼ぶと、学生服を着た遊戯が振り向いた。宵の空の色の優しい目がこっちを向いているのが嬉しくて、ふわふわした頬が上につり上がって目が細くなった。 花束をたずさえて『ハッピー・バースデイ』の歌を口ずさもうとしたところに、横から中型のキャブオーバートラックが滑り込んできた。遊戯の凍りついた笑顔。 この光景はただのまぼろしだ。十代は今ここにまぎれもなく生きていて、粘り気のあるゴムタイヤの下で轢死した子どもではないのだから。 「言っておくが自業自得だよ。おまえが邪魔をするからだ」 小馬鹿にするディヴァインの声が、おぼつかない無感覚の波間を漂っていた十代を現実に引き戻した。うつぶせになって床に倒れていることに気がついたのは、すこし後だった。 髪を犬のリードがわりに引かれて持ち上げられ、人を殺す道具にしてはなかなかに軽すぎる感触のひやりとした銃口が、顎の骨に打ちつけるのがわかった。 「おまえは黙って優秀な兵士を孕んでいればいい。『おれ』がおまえに必要としているのは、類稀な潜在能力とけちな子宮だけだ。せめて従順にしてろ。それがうまくできれば、みっともない身体もいやしい心も可愛がってやるよ」 「おまえの愛なんかいらない。鏡に向かって話してるほうがまだましだ」 「いい余興を思いついた。カンナ、このわからずやの遊戯おじさんが祝福してくれるように、彼の前で僕を愛していると宣言してくれ」 ディヴァインが十代のうなじを捕らえて遊戯のほうへ向け、嗜虐癖を備えた陽気な料理人が、生きた獲物のとっておきのいたぶり方を見つけたときに唄う歌に似た口調で命じた。十代は、耳の後ろにある冷血漢のにやけ面を心の底から軽蔑した。 「は? ふざけるな。なんなんだよ、それ」 「言えなければ遊戯が死ぬぜ」 十代の顎をえぐっていた銃口が引かれ、遊戯の眉間にぴたりと照準が合う。 「い、言う! 言うから」 十代は上ずった声で叫んだ。 「やめてくれ! その人を傷つけないでくれ。何でもするから、遊戯さんだけは……」 クランプで固定された丸型フラスコのような窮屈な姿勢のせいで、言葉を失っている遊戯の、焦点の合わない瞳から視線を逸らすことができない。 今のディヴァイン青年は、手綱のない野生のけだものだ。ほかの誰にも、彼自身にさえ、まったく制御がきいていない。 この場は望みどおりに振舞うしかない。 「オレは、おまえを」 「ディヴァイン様だろう、カスが」 「ディヴァインさま……を。あ、あい……あいして……」 遊戯がゆっくりと首を振った。 「十代くん。嘘はだめだ」 生真面目にいさめる声。十代は嗚咽に変わりかけの湿った喉で、「だって」と言い訳をした。 「あなたを護りたいんです。こんな形でしか、役に立てないんです」 「役に立つとか立たないとか、ボクはそんなことを言ってるんじゃない。キミはボクの大切な仲間なんだよ」 彼の振舞いに十代への軽蔑はなかったし、低俗な喜劇を見せつけられて逆上した観客の野次もない。ディヴァインは遊戯の淡々とした態度を鼻で笑い、十代を哀れんだ。 「残念だったなカンナ。仲間だとさ。決闘王もおまえの親と同じだ。おまえのことなんか何も考えちゃいないんだ。残酷だ、おまえは心からその男を愛し、尽くしてきたっていうのに……私の腕に抱かれたおまえが、遊戯の名前を呼んで助けを求める姿はすこぶる刺激的だったよ」 「やめろ。この人の前でそんな薄汚い言葉を口にするな」 ディヴァインはチーズのように濃厚な狼狽を味わいながら、さらなる恐慌の風味を引きずり出そうと図っている。 「遊戯にそうされたいと願ったんだろう。私がおまえにしたように、犯されて、よがって、子どもを孕みたいと考えたんだ。人間未満の奇形のくせに、かわいいところがあるじゃないか」 「嘘だ。嘘だッ!」 十代は悲鳴じみた絶叫を上げた。 悲しい目が十代を見つめてくる。取り返しのつかないプレイング・ミスがもたらす後悔にさいなまれた。遊戯には、彼が住む世界の裏側にある、人の心の闇が凝り固まってできたなまぐさい掃きだめを覗いて欲しくなかった。 「十代くん」 「軽蔑してください。オレ、あなたの前で女みたいに、ガキみたいにこんな……」 「泣かなくていい。キミの強さをボクは知っている。ディヴァイン、その子はキミのことも気遣っているんだ。優しい人間だから。人を傷つけないように、羊の皮をかぶって屈辱に耐えている」 「わかったような口をきくが、的外れもいいところだ。こいつは私と同類だ」 ディヴァインが細い顎をしゃくって十代を示してみせた。 「十代くんはキミが思っているような人間じゃない。彼は力を持つことの責任を自覚している。キミとは違う」 遊戯が言った。 背後から十代のうなじの薄い皮を針のように刺していた愚弄の気配が、ふいに消える。それと入れ替わりに、もしもそんなものが深い自意識の湖に溺れきったディヴァイン青年に残っていればだが、義憤の揺らぎのようなものが生まれた。 「そうか、おまえか。この女を壊したのは」 かねてからの仇敵を見つけたように、憎々しげに囁いた。 「手にした運命が、尊い暴力が、さも間違った解答のように思いこませたのか」 ディヴァインは、この世に悪が無限に生まれ落ちてくる意味を理解しかけていた。悪魔たちが思いつく限りの汚物を使って穢すべく宿命づけられた存在の一端に遭遇した彼は、眼をふさがれた十代には知りようもない、拒絶をまじえた高揚を覚えていた。 「どうやらあなたはこの神月カンナがよほど大切なようだ。もし、あなたが旧世紀の夢にすがりつく臆病者の王さまでなければ、決闘といかないか。そっちが勝てば、我らがいとしのカンナはすぐに返してやる」 遊戯を挑発して、十代の耳の上部のカーブを、覆いかぶさったチョコレート色の髪ごと唇で食んだ。ぞっとする触感。唾液に濡れた跡をひややかな空気が撫でていく。 「私の決闘はあんたのデモンストレーションと違って多少痛むが、安心しろ。負けても死なない程度には手加減してやる。せいぜい身体機能に障害が残る程度だ。殺してしまっては意味がないのでね。あんたが地面に膝をついたときは――この女が孕むまで豚のように犯せ」 十代は愕然としてディヴァインを見上げた。 「よりによって、この野郎、遊戯さんになんてことを言うんだ」 「一度道具として使われてみればいい。悟り澄ました顔の遊戯もまた下衆な男のひとりにすぎんとわかる。決闘王と規格外の掛け合わせなら、最強の兵士ができあがるだろうぜ」 「おまえとは絶対に同類なんかじゃない。遊戯さん! これはオレの甘さが招いた問題。あなたが決闘を受けることはないんです!」 「それはボクが決めるよ」 遊戯が冷静に言った。彼は下劣な条件を提示されても、それほど堪えた様子はなかった。 「ボクは大切なキミを助けたい」 「た、たいせつな、って」 瞬時に頬が熱を持つ。ディヴァインが不機嫌に鼻を鳴らした。 「むかつくんだよ。自分よりも弱いやつらに迫害される屈辱も知らないくせに、わかったふうな口をきく。あんたは私に触れることさえできないのに、言葉の力でこの女をがんじがらめに縛りつけて操っている。無力な人間ふぜいが、何様のつもりだ」 十代は喉の奥で、首輪をつけられた猛獣が発するような、苛立ちのうなり声を上げた。 「遊戯さんは間違ってない。遊戯さんは、どんな時だってこの人の光がオレを導いてくれる」 ディヴァインには十代の怒りの根源がわからないだろう。孤立のうちに留め置かれている者に、人に焦がれる異物の気持ちはわからない。十代は遊戯の名前を繰り返す。うわごとのように祈りを口走る。 「この人はオレに正義を教えてくれた。かけがえのない仲間をくれた。友情の大切さを教えてくれた。誰かのために闘うことの尊さを教えてくれた。なにより決闘の楽しさを思い出させてくれたんだ」 「人間にはそれぞれの役割がある。搾取されるものも略奪するものも、生まれたときから運命が決定している。闇に向かって光り輝けなどと、地を這うとかげに飛べというのも同じだ。崖の上から飛び降りて潰れて死ねと。おまえは空を覆い尽くすだけの闇を持ちながら、なぜ遊戯の足跡をたどる影なんかに甘んじているんだ?」 「黙れ。オレをひとりぼっちの闇の中から救い出してくれた遊戯さんを否定するやつは赦さない」 ディヴァインはあきらかに面食らっている。十代の思慕が、彼の痣だらけの骨折した信念とはあまりにもかけ離れているせいだろう。 「ボクは優しい十代くんが好きだ」と遊戯が言った。 「たとえ何度闇が彼の心を呑み込もうとしたって、ヒーローになりたいと願う、みんなを護ってくれる十代くんは必ず戻ってくる。それを信じているんだ」 諦めの雲間から射す幾筋もの光の柱を十代は見た。遊戯の口から聞かされる信頼は、なによりも心強い芯になる。 「ひとりぼっちなんかじゃない。正しくあるから、優しいから、みんなはこの子の強さを頼るんだ」 力ない言葉は無力だと身に染みている。遊戯の言葉が決してうつろな空洞ではないという事実もまた知っている。彼には語る正義を現実にする力がある。 しかし、本当の畏れを知らない者の胸には、正しい言葉が偽善極まりないひとりよがりなお仕着せにしか響かない。 「最低だ」 ディヴァインが吐き捨てた。 「カンナ。目を覚ませ。武藤遊戯は私以上に傲慢なエゴイストだ。おまえに馴染まない光を期待する。人には誰しも生まれ持った使命があると僕に言ったのはおまえじゃないか。その意志を折ってまで遊戯に媚びるのか。おまえはただ利用されているだけだ。そんなに力があるのに、そんなに知恵があるのに、考えろ、なぜわからないんだ!」 「わかるさ。遊戯さんは正しい。遊戯さんの言うとおりだ」 「カンナ!」 ディヴァインは癇癪を起こし、十代を突き飛ばしてデュエルディスクを装着した。 「それならやつをおまえの目の前で八つ裂きにして正気に戻してやる。力こそ正義だ。権力こそ信頼だ。選ばれた者の使命を思い出させてやる」 遊戯の手にあるべき〈ブラック・マジシャン・デッキ〉からカードを引き、実体をともなった〈翻弄するエルフの剣士〉を召喚した。星四つの、遊戯のデッキの斬り込み役だ。 ソリッドビジョンが触感を持っただけの魂のないオブジェが構築され、プレイヤーの隣で無気力に立ちつくしている。エルフの剣士が本来纏っているはずの決闘王のしもべとしての風格は、カードの彼方に取り残されていた。 ディヴァインが最上級の自尊心をもって語るサイコ・デュエリストとは、デュエルモンスターズの絵柄を現実世界に投影し、ガラス繊維入りのプラスチックでできたマネキンを造りだす人形職人を指すのだろうか。 十代は、もしかするとディヴァインの枯れた森の眼には、精霊の魂が見えていないのではないだろうかと訝った。精霊たちが仲間を鼓舞して上げる鬨の声が、あるいは墓穴の底へ落下していく戦士の無念の叫びが、はたして彼には届いているのだろうか。 彼は目と耳をふさいで、精霊たちの呼びかけを自ら絶ってしまっているように見える。 人と精霊がお互いに心を通わせようと努力する姿を嘲笑し、強力な外殻の形を盗んで都合の良い力に変える――それは、絆で結ばれた仲間たちとの共闘ではなく、ひとりぼっちの戦争だ。 そんなものがディヴァインのスタイルなら、彼は決闘者として武藤遊戯に対峙することすら許されない。 「〈翻弄するエルフの剣士〉、遊戯をやれ!」 ディヴァインが叫んだ。十代の想像のとおり、剣士はマッチ棒のように身じろぎもしない。 「なぜだ。なぜモンスターが私の命令に従わないんだ?」 ディヴァインがカードのテキストを睨みつけた。彼はカードに何らかの不具合が発生していると踏んだのだろう。 そうではない。選ばれしマスター以外の者がデッキからモンスターを召喚し、真実の忠誠を誓った武藤遊戯に矛を向けるよう命じたとき、遊戯とカードたちとの間に存在する絆を凌駕して攻撃を強制し、主君殺しを実現させるだけの力が、ディヴァインには存在しないのだ。 「このクズカードどもが不良品なだけだ。私の本当の力を見せてやる」 人とカードの間に存在する目に見えない絆に、自負する超能力を寄せつけないほどの厚みが存在することを、ディヴァインは認められないようだった。〈ブラック・マジシャン・デッキ〉のカードを恨めしげにばらまいて、自らが所持していた〈ファイヤー・ボール〉の魔法カードを発動した。 武藤遊戯に、はっきりとした生命の危険が迫っている。囚われの大型動物が、頑丈な鉄の檻が壊れるまで何度も全身をぶつけてついには脱走を図るように、十代の深淵から漏れ出した力が、銀の封印装置を内部から破裂させた。 十代は金の双眸を光らせ、手足を拘束するロープを引きむしって遊戯を突きのけた。わずかの間隔の差で攻撃対象を逸れた火球が、ションガウアーの版画がかかった漆喰の壁を直撃する。 聖アントニウスを誘惑する飢えた竜に似たみすぼらしい悪魔たちが、赤い輝きを放つ光の触手に呑まれていく。天井に燃え移った火の粉が柱を食い散らしはじめ、あたりは一瞬のうちに炎に包まれた。 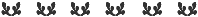 〈「バース・オブ・アルカディア(10)」につづく〉      このコンテンツは二次創作物であり、版権元様とは一切関係がありません。無断転載・引用はご容赦下さい。 −「スクラップトリニティ」…〈arcen〉安住裕吏 12.12.31− |
||
 |
 |
