 |
 | |
|
『愚かな女。彼女はやかましく、分をわきまえず、無軌道だ。
彼女は自分の家の戸口にすわり、町の高いところの座にすわり、 まっすぐに歩いていく往来の人を招いて言う。 「身の程を知らない者は、誰でも私のもとへ来なさい」 また、彼女は思慮の欠けた人に向かって言う。 「盗んだ水は甘く、隠れて口に入れる食物は何よりも美味い」 彼女の客たちは、そこに死者の霊がいることを、 自らが黄泉の深みにいることを、知らない。』 (旧約聖書『箴言』 九章十三〜十八節) 8
ぬるい硫黄の雨が、折れたアーチとくすんだ緑の茂みを打ち据えている。石畳の割れ目から、つる草がほうぼうに巻きひげを伸ばしていた。親に見捨てられたとらじまの痩せた仔猫が、幼い十代の足元で死にかけている。
赤い傘を傾けて短い指を差し伸べると、仔猫は目を見開き、唸り、爪の先に噛みついた。毛むくじゃらの尻尾を魔女のほうきのように逆立てて、肢を引きずって逃げていく。 後ろから誰かが――のっぽで兎の眼をした男が、慰めるように十代の肩を抱いてくれた。 仔猫は、あの後どうなったのだろう。猫の姿はいつのまにか泥まみれの若い男の姿に変わっている。 日々のありふれた光景の断片が、ふとしたはずみで記憶の糸玉を解くことがある。彼との出会いがそうだった。薔薇園の植えこみの中から、手負いの獣の恐怖を孕んだモスグリーンの瞳が睨みつけてきたとき、十代はいつかどこかで見た人慣れしない仔猫のことを思いだしていた。 修道女の恰好をした〈神月カンナ〉は、彼に手を差し伸べてやった。噛みつかれるだろうか? 彼は唸り声を上げたが、弱った猫とは違って噛みつかなかった。 頭蓋の内側に直接打ちつけるような雨粒の音を聞きながら、遊城十代はひどく重いまぶたを上げた。 メダリオンつきの白い天井が見えた。知らない部屋だ。前時代的な積み煉瓦の暖炉の奥で、炎が乾いた薪を食い散らかしながらまばゆい光を放っていて、暖かくて心地が良かった。 木製の窓枠のなかを、暴風を呼んだ水っぽい雲が真っ黒に塗りつぶし、時折懐中電灯の点き方を確かめるような短い間隔で発光している。遠雷の音。 十代はベッドの上にいた。頭を起こしてシーツを蹴飛ばしたところで、自分がスリップ一枚しか身につけていないことに気がついた。ジョーゼットだ。下ばきはつけていない。 『私を飲んで』と書かれた札がくくりつけられた小瓶のように、サイドテーブルに〈ブラック・マジシャン・デッキ〉が無造作に置かれている。 拍子抜けの気分で四十枚のカードに腕を伸ばした途端、指に透明な焼きごてを押しつけられたかのような灼熱感に襲われた。焦げて黒ずんだ指を口に含んで、十代は顔をしかめた――いったいどんな性質の悪いトラップだかは知らないが、決闘王のデッキに触れることができない。 不穏な落雷の音にかぶさって、扉の蝶番が重々しく軋んだ。赤毛のミスター・ディヴァインが、初秋の遠い青空を思わせる微笑をたたえて現れた。銀のトレイに温かいミルクが入ったマグカップをふたつ載せている。 「おはようカンナ。気持ちのいい夜だ」 人を寄る辺のない気持ちにさせるさわやかな青年の声は、どこかの異空間から響いてくるように場違いだった。サイドテーブルの上から〈ブラック・マジシャン・デッキ〉を苦もなく取り上げてポケットに入れ、トレイを置いて十代の隣に座った。 思い出した。この男が海馬モクバに十代を撃たせたのだ。十代は彼との駆け引きに敗北した。 グロックが肉体のあちこちに空けた穴はすべて塞がっている。皮膚が引きつる不快感もなかった。おそらくディヴァインが、デュエルモンスターズの力を使って癒したのだ。 敵対者を生きながらえさせた理由はなんだ――決まっている、彼の頭の中にある鍵つきの金庫にしまい込まれた、とっておきのたくらみに利用するためだ。 いったい何を目論んでいる? なによりも、モクバは無事でいるのだろうか。 ディヴァインに問い詰めてやりたいことはいくつもあったが、十代は口を閉じ、つとめて平静を装った。がっつくのはうまくない。相手につけいる余地を与えることになる。 「おはよう、ミスター。理事長ってやつは、どこでも悪いことしてんのかな」 「きみの身体はすべて調べさせてもらった」 「どうだった?」 「とても素敵だよ。私がそのボビー・コークみたいな半陰陽を気味悪がるかと思ったのか? まさか」 十代はごく自然に振る舞って見えるように注意して、スリップの上に薄いシーツを巻きつけた。そしてあらためてディヴァイン青年を観察した。 沈み込んだ色をした赤毛で、前髪の右側にひどいはねがついている。排他的で高慢な瞳は、冬を前にして虫の息になった森の緑だ。それと揃いの色のベストを着ていた。 顔立ちは整っていたが、性根の曲がった悪徳教師や嗜虐癖を持ったインチキ宗教者と共通する皮肉っぽい唇の歪ませ方が、彼の印象を人を寄せつけない冷ややかなものにしていた。 「きみを見てると、僕は子どものころに背表紙が擦り切れるほど読んだジャンヌ・ダルクの伝記を思い出すよ」 ディヴァインが芝居がかった溜息を零して言った。 「十五世紀当時、百年戦争の英雄で神に愛された聖女がじつは両性具有者だという噂が、民衆の間にまことしやかに流れていた。裏切り者たちが彼女を魔女だと糾弾したからだ。中世、魔女は両性具有だと信じられていたからね。きみのように」 彼の感情の仮面の使い分け方は非常に巧みだった。気のおけない『僕』の顔、有能な『私』の顔、それからさっきまで見ていたおぼろげな夢の中にいた、傷つき怯える仔猫のような行き倒れの『おれ』の顔もどこかに隠しているはずだ。 目の前にいる貴族然とした青年と、二か月前に十代が介抱してやった泥だらけの粗野な男の容姿が、まだうまく結びつかない。 「僕の父は政治家でね、カンナ。子どものころは優しかったんだ。つまり僕がまっとうな、何の変哲もない、普通の息子だと思っていたころは。多忙で家を空けがちな父がデュエルモンスターズをお土産に買って帰ってきてくれたときは本当に嬉しかった……だけど僕の中に超能力が発現してからは、すべてが変わってしまった」 心の膜の最も薄い部分をつつくのは、悪魔が良くやる手口だ。自分がされるのはこたえるものだ。 思考は醒めていたが、染み出してくる同情心は止められなかった。目論見が成功したディヴァインは、内心上機嫌だろう。たいした役者だ。 「決闘の最中に父をカードの力で傷つけてしまってからは、あの人は僕とは顔も合わせてくれなくなった。僕は徹底的に遠ざけられ、もう家族のぬくもりも憶えていない。親に愛されない虚しさ、弱いものによってたかって排斥される屈辱。きみが長い間感じ続けてきた心の欠落が、僕には自分のことのようにわかる」 「おまえはただ同類を憐れんでいるだけさ」 十代は吐き捨てた。 「キミは、自分しか愛せない。同じ穴のむじなのオレに自己愛を投影しているだけだ」 「きみもそうだから?」 「さあな」 「きみの目は猫の目のようだな。プライドが高いくせに寂しがりだ。僕ならきみをわかってあげられる。僕だけだ。そして僕を理解できるのもきみだけだ」 理想の男性像を夢見る少女用に甘ったるく作られた声は、十代におぞましい嫌悪感しか植えつけなかった。 自分の力のみを信じ、ほかの人間をただの道具としてしか認識できない。力と正義を同一視し、盲目に信奉するディヴァインは、たしかにかつての十代と同類だった。 『あの人』が導いてくれなければ、おそらく十代はまだそんなふうな人でなしだっただろう。だからこそ、この男を決して好きになれそうにない。 「僕を信じてついてきてくれるなら、カンナ、きみに新しい世界をあげよう。そこではもう誰も僕らを傷つけないんだ。レンチを手に持って追いかけてくるやつらもいない。僕らを化け物と呼んで排除しようとした者みんなが僕らを敬い、僕らの手先となってかしずく理想郷だ。なあ、それってとても素晴らしいと思わないか」 十代は強い自己嫌悪とともに押し寄せてきた嘔吐感を、かろうじてのところで呑み込んだ。 ――そんなことをしても、なんにもならなかった。 世界を自分のものにしたことがある。すべてを力でねじ伏せて、逆らうものは皆殺しにしてやった。 はじめは大切なものを救うために求めた力が、護るものはなにもない。多くの罪を覚え、罰を背負ったが、犠牲と引き換えに探し物が帰ってくることはなかった。失い続けるだけだ。無意味さが黒い螺旋を描いていた。 十代は光に満ち溢れた人の世界の土を再び踏んだとき、もう二度と無価値な力を振りかざさないと誓ったのだ。冷たい炎に焼き尽くされた世界へは戻らない。 「なにが新しい世界だ。キミがあの時のオレと同じ間違いを犯そうっていうのなら……」 「どうだっていうんだ?」 ディヴァインが、にやつきながら覗き込んできている。彼が優位を確信している理由を、十代は身を持って知った。 精霊たちの声が聴こえない。ユベルの悪魔の眼球が見通す世界は消失し、身の丈に合わない壮大な夢から醒めたばかりの朝に訪れるきまり悪さが、石油臭い工場排煙のように肺を蝕んでいる。 ベッドの正面に置かれた大型のドレッサーに、円錐形をした、見覚えのある銀細工の髪留めでツーテールを飾る十代の姿が映っていた。髪留めを外そうと上げた腕が、強烈な電流に弾かれる。 「父がサイコ・デュエリストを捕獲するために造らせた、超能力抑制装置のひとつさ」 得意そうにディヴァインが言った。 「髪留めの形をしているのは、繁殖に使える牝が必要だったから。女を縛り付けるなら、どうせなら美しい装飾品のほうがいいと考えたんだと思うぜ、おそらく」 この罰当たりな機械は、デュエル・アルカディア女学園の地下牢獄へ囚われていた元生徒たちが着けられていたものだ。無力化された異端の少女たちは、自らが普遍的人類の慰み者にされるべき家畜だという間違った認識を受け入れてしまった。 孤独な運命に絶望しながら炎に呑み込まれていったのは、十代やディヴァインと同じく人の領域からこぼれ落ちた決闘者たちだ。だからこそ、亡父の腐り果てたやり方を肯定する同類に怒りがわいた。 「きみ本来の姿はじつに恐ろしいぜ。だがカンナ、あの悪魔のような超能力は封じられた。そんなに細い腕でいったい私をどうしようっていうんだ? ぜひ知りたいな」 にやにやしながら、ディヴァインが十代の肩をヘッドボードに押しつけた。ふたりの体格はそう変わらないはずなのに、彼を押し返すことができない。 アカデミア時代に親友と喧嘩をしたときの悔しさがまざまざと蘇ってきた。言い争いが取っ組み合いにまで発展した理由はもう思い出せないが、紫色の柔らかい袖に組み敷かれて、耳の後ろから押し殺した声で一方的な言い分を聞かせられるのが腹立たしくて涙がにじんだ。 ひさしぶりに、非力な人間の気持ちを痛感する。 「そうだ、カンナ。面白いものを見せてやろう」 ディヴァインが片手を上げて、板状の端末を壁のモニターに向けた。電源が入り、画面が明滅する。 どこかのダンスホールの天井からぶら下げられた、巨大な吊りかごが映し出される。餓死用の鉄の檻だ。なかには海馬モクバが囚われている。水が枯れた井戸のように開けっ放しのうつろな灰色の瞳が、彼の精神はまだディヴァインの支配下にあることを仄めかしていた。 「きみを殺そうとした海馬モクバだよ」 「おまえがそうさせたくせに」 十代はディヴァインを睨みつけた。彼はおどけて片目を瞑った。 「私はやつがきみに抱いていた殺人衝動を遂げさせてやっただけさ。モクバはもともと、きみが生きていることが我慢ならないほど憎んでいたんだ」 十代はうつむいて唇を噛んだ。ディヴァインはそんな十代を、真摯な同情を浮かべて見つめていた。 「モクバから聞き出したよ。きみはやつの命令で我がデュエル・アルカディア校に潜入したスパイだったんだな。ここは相応の礼を尽くさねばならんところだが、美しいきみを傷つけたくはない。なにより我がディヴァイン家の花嫁となる娘なのだから」 十代は唖然として顔を上げた。ディヴァインに冗談を言っている様子はない。枯草色の瞳に熱っぽい真剣さが光っている。 「私のものになれ、カンナ。そして最強のサイコ・デュエリストを産むのだ」 「ばかか? ガキなんか産めるかよ。オレは……」 「きみは男とも女とも交わることができ、両方の子孫を残すことが可能な両性具有者だ。強く望むなら――これもモクバから聞いたんだがね、きみが異常な憧れを抱いている武藤遊戯の種を宿すことだってできる」 十代は息を呑んで、モニターに映った吊りかごを見た。いたたまれない気分になる。 「あの人は、オレなんかには見向きもしないさ」 「きみの魅力は普通の人間にはわからないんだ。価値を見分けられる者にだけ理解ができる。もしもきみが痩せっぽちの野良犬に見えるとしたら、きみのアイドルは他人よりも少しばかりカード・ゲームがうまいだけの凡人に過ぎない」 遊戯を馬鹿にされて頭に血がのぼっている十代を、満足そうに一瞥する。 「たとえばだ。あの男の好みそうな女を見繕ってこよう。彼の精液を手に入れたら、そいつできみは孕むことができる」 「そんないい加減な人じゃない」 「子どもの潔癖な憧れは破れたちり紙と同じだ。童貞処女のきみにはわからんだろうが。人にはね、何を犠牲にしても欲しいものがひとつやふたつは必ずあるんだ。私にももちろんある。なあカンナ、きみが憧れの男の子どもを孕むのがいやなら、それでいいさ。私は強い決闘者の掛け合わせなら誰の子孫だろうと構わないんだ。私が欲しいのは力を持った無知な子どもだ。私に忠実な兵士となるのなら、我が一族の血を受け継いでいる必要はない」 「あんた、いかれてるよ」 十代は唾を吐いた。淑女らしくない下品な仕草に、教育者の顔をしたディヴァインが眉をひそめる。 「お断りだ。あの人に手を出すな。それに、親に愛されない子供にいったい何の意味がある?」 「自分のことを言っているのか」 「さあな」 「私は愛してやる。きみのことも、生まれてくる子どもも心から愛そう。なぜならきみたちにはそうされるだけの価値があるからだ。これは取り引きだ、カンナ。私の望みを叶えてくれるなら、きみの願いは私が叶える。きみが私の言いなりになるなら、武藤遊戯のデッキはくれてやる。海馬モクバを解放しよう。そして今後一切彼らには関わらないと約束する」 ディヴァインは秘密めいた山師の微笑を浮かべながら、十代のあごの横へ両腕をついた。まっすぐ見つめてくる目は、好意こそちらついてはいたが、無機物を見る種類のものだった。 「答えは今すぐにとは言わない。処女のきみにはいたく重要な決断だろうからな。わかるぜ。だが急いだほうがいい。武藤遊戯もいろいろと多忙だろうからな」 海馬コーポレーションが主催する冬期グランプリのオープニング・デュエルに招かれたゲストは、レオンハルト・フォン・シュレイダーと武藤遊戯だった。 今の遊戯は丸腰だ。十代は顔色を変えた。 「そう。聡明な人間が私は好きだ、カンナ」 ディヴァインがほくそえんだ。無力な殺意を、ひどく気分が良さそうに見下していた。 「武藤遊戯がいくら最強の決闘者だと謳われていても、ありあわせのカードで闘える程レオンハルトは甘くない。なあ、遊戯は決闘を辞退するかな? 臆病者だと謗られるだろうな。王の称号を奪い取られることを怖がって戦争に赴かない腰抜けを、誰が決闘王だと認める? 彼の名誉のためにも、きみにはぜひ物わかりが良くなってほしいものだが……」 ディヴァインは十代から身体を離し、わずかに乱れた衣服を整えると、きざな仕草で淑女へ向ける一礼をした。 「じゃ、失礼するよ。私は忙しい身でね。いつまでもきみの相手をしていられないんだ。あとで一緒に決闘王の醜態をテレビで観よう」 武藤遊戯はどんな困難な状況にあっても、いつだって堂々と闘って勝ってきた。それでも絶望的な妄想が頭から消えない。 遊戯が、彼とは関わりのない誰かの謀略の手に足を掴まれ、決闘王ではなくなる。冬の冷たい海を往く船の羅針盤が指し続ける、北の空の星が地に堕ちる。誰もが光を見失い、船団は沈み、凍った海の底に呑み込まれてしまう。 そんなことがあってはならない。 「ま、待て!」 喘ぐように叫んだ。去りゆく背中を追って、ベッドから転げ落ちた。 ディヴァインは気のなさそうな顔を作って振り向いた。まだ何か用があるのか、というポーズ。色の褪せた絨毯の上に座りこみ、十代は震えながら声を絞り出した。 「なる。……おまえのものになるから、あの人には手を出さないでくれ」 ディヴァインは十代の顎をとって、悲壮な表情と潤んだ目を、収穫したばかりのりんごの具合を確かめるようにためつすがめつした。 「上出来だ。きみはじつに美しい。私の妻にこれほどふさわしい女はいないだろうよ」 肌が粟立った。今まで向けられたことがない種類の湿っぽい賞賛の囁きを、全身が拒絶している。 しかし、奇妙に満足してはいた。 これで武藤遊戯は穢されない。彼が傷つくことはない。王の栄光は守られたのだ。 ならば、それでいい。 一人きりで部屋に取り残されたあとで、十代はシーツを頭からかぶってうずくまり、自嘲で喉の奥を痙攣させた。滑稽な振る舞いしかできなくなった無能な手足に嫌気が差していた。 身ひとつで引き受ける犠牲が何よりも嫌いだったはずなのに、彼のことを考えると十代はおかしくなる。大人になったはずの心のなかに、庇護者のぬくもりを求めてさまよい歩く自分本位の子どもじみた甘えが還ってくる。 それでも世界中の決闘者たちに注目されているあのヒーローが、ブラウン管テレビの中から抜け出し、無数のファンが伸ばした腕の中からひとりの子どもの手を掴んで――親のように抱擁してくれるわけもない。 わかっている。 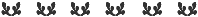 作り物の人格者の顔は、頬の筋肉がひどく凝るものだ。デュエル・アルカディア学園での日々に、ディヴァインはほとほとうんざりしていた。 馬鹿な小娘たちのご機嫌を取って、求められるのはつまらない社交辞令ばかりだ。華やかなダンスパーティーには、特別に耐えがたい吐き気をもよおしていた。 あの女どもは、自らが搾取されていることを知らないのだ。 せめてダンスを踊るのは、赤いドレスが似合う女がいい。軽薄な赤ではだめだ。青ざめた肉の袋から残らず絞り出した血のような、諦観と絶望の染み出した色でなければならない。その女が猫みたいな疑り深いつり目をしていると、もっといい。 神月カンナに似ているものがいればまだましだが、期待はしていなかった。あんなに冷ややかな死のにおいのする魔女がほかにいるものか。 ディヴァインは力のある人間が好きだった。強いくせに頭が空っぽで、耳のそばでいちいち道を示してやらなければ何もできないような、便利で役に立つクイーンのチェスピースをこの上なく好んだ。本当は臆病で愛を渇望しているくせに、口が裂けても本当の心をさらけ出せない、気むずかし屋の女。 あの女は自分の力の価値を知らない。夜空のポラリスが見えなければ何もできやしないだろう。 自分でも驚いているが、ディヴァインは神月カンナを軽蔑しているわけではなかった。彼女は御しやすく、世界一精巧で、いくつもの仕掛けを隠したきらびやかな操り人形だ。その愚かさを見下し、得体の知れない力に嫉妬し、心の欠落を撫でさすり――もしかするとそういうふうになら、気まぐれだが、自分以外の誰かを愛せるかもしれないと思ったのだ。 ディヴァインは、カンナとの約束を果たすつもりだった。自分で思っているよりも、ディヴァインは彼女を気に入っていたのだ。 遊戯の〈ブラック・マジシャン・デッキ〉はカンナにプレゼントしよう。それを彼女が自分のものにしようが、人懐っこい猫をかぶってもとの持ち主に返そうが、どちらでも構わない。 ただしそれは、夜が明けたあとだ。 明日の朝には、〈ブラック・マジシャン・デッキ〉の価値はただの紙くず同然になっているだろう。尻になじんだ玉座から蹴り出された男のデッキなど、誰がありがたがるものか。 神月カンナには、決闘王が膝を折るさまをぜひ見てもらっておきたかった。憧れの遊戯がみじめな敗退者に落ちぶれた姿を目の当たりにすれば、今はのぼせあがっている彼女も目が覚めるだろう。 熱が引いたファンの姿を見たことがある。あんなに目を潤ませて見上げていたのに、本当に見向きもしないのだ。まるでそこに誰もいないような残酷な仕打ちをする。 カンナが遊戯にあの目を向けるとなると、にわかに気分が良くなってきた。ディヴァインは、初めて自分が嫉妬深い男だったことを自覚した。 あの魔女は決闘でしか物事を計れない。決闘王の肩書きを引きはがされた哀れな遊戯には、すぐに何の興味も失くしてしまうだろう。 9
蛾の羽音に似たぶうんという低い音を立てて唸るテレビが、人工的な冷たい光を放っている。窓の外の雨脚は強まっていた。氾濫する川底の黒い泥のような雷雲から青白い矢が放たれ、轟音とともに森の木々を引き裂いている。
スピーカーから陽気なファンファーレが流れてきた。〈KCグランプリ二〇〇九〉予選大会の特設会場の座席は、この悪天候のなかにあって、詰めかけた観客たちですべて埋まっている。七色の紙吹雪が舞い、リボンつきのゴム風船が閉じたドーム天井に向かって上昇していく。 突然照明が落ち、一筋の眩いスポットライトが、ぶどう色の髪の青年の姿を浮かび上がらせた。 『さあ現れたぞ。今夜ふたたび伝説に挑む初代KCグランプリ優勝者、レオンハルト・フォン・シュレイダー! ヨーロッパ大会では惜しくも準優勝だったが、はたして前大会の雪辱は果たせるか?』 調子のいいMCにはやしたてられ、期待と賞賛の拍手の嵐に包まれたレオンは、さえない表情をしている。ヘーゼルナッツ色の瞳を迷子のようにさまよわせ、ディスクを構えた。 レオンは武藤遊戯に本気で立ち向かわなければならない。彼のもとにはディヴァインからの手紙が届いていた。すこしでも決闘に手を抜いたが最後、海馬モクバと神月カンナに面会することは二度とかなわないだろうという旨の脅迫状が。 ――この警告はレオンハルトにはよく効いたようだよ。もっとも、やつは旧友の僕のことをペテンにかけようとしたがね。きみもあまり信用しないほうがいいぜ。 ディヴァインは鼻で笑って、そんな無用の忠告を十代にくれた。 「対するは――決闘王、武藤遊戯!」 歓声が膨れ上がり、湿度の高い熱気がモスケンの渦潮のようにうねっている。そこに混ざり込んだ微量の猜疑心に、観客たちは誰も気がついていない。決闘者たちだけが、無作法に損なわれた暗黙のルールに対して面白くなさそうな顔をしている。グランプリの参加者にとっては、武藤遊戯との対戦権は優勝杯よりも価値のあるものなのだから。 遊戯がテレビの前に現れた。彼は落ち着き払った穏やかな物腰で、毅然と前を向いてデュエルフィールドに立っていた。 しかし、今の決闘王は、手に馴染まない拾い物の剣を握らされた戦士だ。彼が全幅の信頼を寄せる〈ブラック・マジシャン・デッキ〉は、ディヴァインのポケットの中にある。 レオンと遊戯の決闘が始まった。 〈おとぎの国のレオン〉の異名のとおり、彼はヤーコプとヴィルヘルムのグリム兄弟が編纂したドイツのメルヘン集をテーマとしたカードを使う。小さな赤ずきんが黒い森をさまよい、ずる賢いオオカミが彼女をたぶらかし食らう。森の狩人が悪いオオカミを撃ち殺して赤ずきんを救う。 魔法で山男にされた鉄のハンスは、とある王国の王子をさらって鉄の騎士へと育て上げた。誰もが見惚れるシンデレラの魔法の美貌は、彼女を幸福に導く小道具たちの親切心によるものだ。 善と悪の対角線上に位置する登場人物たちが織りなす勧善懲悪の教訓を含んだ物語のなかでは、善人は取りこぼしなく幸せをつかみ、悪人は悲惨な末路を迎える。年月を経て黄ばんだ紙の一ページには、おとぎ話の主人公たちへのはっきりとした道しるべが示されていたが、彼らを操るプレイヤーは行き先を見失っていた。 死に際に長く苦しむ病気の小鳥の喉を潰して楽にしてやるような、いたましいドロー。レオンには、友人の命がかかっている決闘を笑って楽しむ余裕はなかった。大きな口の〈森のオオカミ〉を召喚し、レオンのターンは終了する。 遊戯が、デッキからカードを引いた。 頬は、なにかとても嬉しい知らせを聞いたときのようにかすかに紅潮しており、そこに諦観はない。彼は白を基調としたローブをまとった魔法使いの子どもを喚んだ。〈サイレント・マジシャン〉。レベル四の幼体だ。 遊戯が〈ミスト・ボディ〉の魔法を発動すると、その姿が白いもやに包まれていく。このカードを装備したモンスターは、戦闘では破壊されなくなる。 「〈サイレント・マジシャン〉。〈森のオオカミ〉に攻撃だ」 遊戯が幼い魔法使いに攻撃命令を下した。レオンは、困惑の表情を浮かべた。攻撃力は〈森のオオカミ〉のほうが勝っている。遊戯のしもべは魔法の力に護られて戦闘破壊をまぬがれるが、彼は差分のダメージを受けることになるのだ。 「魔法使い族の〈サイレント・マジシャン〉が攻撃宣言をしたとき――」 発動条件を満たした罠カードが開いた。〈マジシャンズ・サークル〉。攻撃力が二千を下回る魔法使い族のしもべを召喚できる。 遊戯は、攻撃力千六百ポイントの〈魔導騎士ディフェンダー〉を召喚した。 〈森のオオカミ〉の攻撃力は千八百ポイントだ。ディフェンダーではかなわない。彼はカードを伏せ、ターンを終えた。 『みなさん、驚きです。決闘王が使うのは〈ブラック・マジシャン・デッキ〉ではありません』 MCがマイクを握りしめて唾を飛ばした。熱病にかかったような観客の叫び声が加速する。 『これは来年の〈KCグランプリ二〇〇九〉本戦に先駆けて発表された、永遠の十六歳。身長百七十センチ、体重、三サイズ未公開。あの神月カンナがコマーシャル・ガールを務めるストラクチャーデッキ、〈ロード・オブ・マジシャン〉だ。特典カードはカンナの相棒〈カードエクスクルーダー〉だぞ!』 レオンのターンだ。ドローの瞬間に、遊戯の〈サイレント・マジシャン〉に魔力カウンターがひとつ乗った。このモンスターは、たしか、魔力カウンターを五つ蓄積することでレベルアップを行うはずだ。子どもから大人に成長した〈サイレント・マジシャン〉は大幅に攻撃力が強化され、加えて魔法カードを受けつけなくなる。 それでなくても、カウンターが増えるごとに五百ポイントの攻撃力が上昇する。まだ手がつけられるうちに対処しなくては、厄介なことになるだろう。 レオンは〈親指小僧〉に〈大男の修行〉の魔法をかけて、攻撃力二千六百ポイントの〈グローバーマン〉を召喚した。このモンスターなら、〈サイレント・マジシャン〉の歩みを止められる。 「ぼくは〈グローバーマン〉で、〈サイレント・マジシャン〉を攻撃です」 遊戯が〈魔導騎士ディフェンダー〉の魔力カウンターを解放した。モンスター効果によって、〈グローバーマン〉の攻撃は無効となる。 それならば、ディフェンダーを先に破壊するまでだ。レオンは〈森のオオカミ〉に攻撃の指示を出した。 遊戯が伏せていた罠カードを開いた。ひやりとしたが、レオンの攻撃を無効にする類のものではない。〈漆黒のパワーストーン〉だ。自らのターンに、望みのモンスターに魔力カウンターをひとつ与えることができる。 これで〈サイレント・マジシャン〉は、毎ターンごとに魔力カウンターを増やしていく。やはり遊戯は、魔法使いの子どもの成長をなによりも優先してきている。 〈森のオオカミ〉が大きな口を開けて、〈魔導騎士ディフェンダー〉を呑み込んだ。悪いオオカミに襲われたモンスターは、オオカミが誰かに退治されるまで胃袋の中で装備カードとして扱われる。 いずれは膨張を続ける〈サイレント・マジシャン〉の攻撃力が〈グローバーマン〉を上回ってしまう。しかし、まだ手はある。レオンのターンは終わりだ。 〈漆黒のパワーストーン〉の恩恵で、〈サイレント・マジシャン〉の攻撃力は本来の二倍にまで上昇する。 「〈サイレント・マジシャン〉で〈森のオオカミ〉に攻撃だ。そして、〈森のオオカミ〉が破壊されたことにより、食べられてしまった〈魔導騎士ディフェンダー〉がボクの場に戻ってくる」 レオンのターンだ。ドローの瞬間、〈サイレント・マジシャン〉に魔力カウンターが集う。彼女が大人に成長するまでに、何としても進化を食い止めなければならない。 「手札から魔法カード発動。〈糸つむぎの針〉! 」 この針は〈いばら姫〉の童話に登場するひがみっぽい魔女の道具で、相手モンスターに三ターンの死の眠りを与える呪いがかかっている。王子が迎えにやってくるまでは、墓地へ送られた眠り姫の目を覚ますことは誰にもできない。 のけ者にされた恨みの針が〈サイレント・マジシャン〉を封印する。レオンはひとまず安堵した。三ターン後に墓地から戻ってきたときには、彼女に蓄えられていた魔力カウンターはリセットされている。 「ぼくは〈シンデレラ〉を召喚します。彼女の効果で〈かぼちゃの馬車〉を呼び、〈ガラスの靴〉を装備する。〈ガラスの靴〉の力で、遊戯さんにダイレクトアタックです!」 〈シンデレラ〉がドレスの裾をつまみあげて、ガラスのキックを遊戯にぶつけた。続いて、〈グローバーマン〉の攻撃が〈魔導騎士ディフェンダー〉を捕らえる。おそらく遊戯はディフェンダーのモンスター効果を使い、しもべの破壊を防ぐだろう。しかし、魔力カウンターにも必ず限界がある。 遊戯が、伏せていた罠カードを開いた。 〈魔法の筒〉だ。相手モンスターの一撃を無効化し、その攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える凶悪なとらばさみ。強いモンスターを従えているのが仇になった。手痛いダメージだ。 やはり遊戯は簡単には勝たせてくれない。だが、〈グローバーマン〉が破壊されずに済んだのはよかった。 遊戯を護るのは、攻めを不得手とする〈魔導騎士ディフェンダー〉が一体きりだ。一見レオンのほうが有利な戦況だが、遊戯はただ一度の引きで圧倒的に不利な決闘をくつがえし、勝利をもぎ取る規格外の決闘王だ。わずかな気の緩みが敗北へ繋がっていくことを知っている。 レオンがこのターンに引いたカードは、切り札の〈ヘクサトルーネ〉だ。次のターンで〈シンデレラ〉と〈カボチャの馬車〉を生贄に、エースの彼女を召喚することができる。 遊戯のターンだ。彼は〈ブラック・マジシャン・ガール〉に酷似した、明るいオレンジ色のローブをまとった魔法使いの子どもを喚んだ。場内が大きく沸く。 『おおっと。きたぞ、〈カードエクスクルーダー〉。とくに目立った効果はないものの、その愛くるしさで過酷な決闘を和ませる魔法使い見習いの少女。神月カンナのアイドルカードだ』 エクスクルーダーは白くてもちもちした頬を膨らませて、彼女の評価に対する不満を表現している。遊戯が、小さな魔法使いに優しく声をかけた。 「キミの本当のマスターのために、力を貸してくれるね」 エクスクルーダーは、ぶかぶかのとんがり帽子をかぶりなおして頷いた。 遊戯が、〈マジシャンズ・クロス〉をかかげた。自分のフィールドに魔法使い族のしもべがふたり以上いるときに発動できる魔法カードだ。片側の魔力をもうひとりの魔法使いに注ぎこみ、攻撃力を三千ポイントにまで引き上げる。レオンのしもべは、攻撃に耐えられない。 「〈カードエクスクルーダー〉。さあ、頼んだぜ」 遊戯の攻撃宣言と同時に、レオンの二度目の敗北は確定した。魔力を増幅させた〈カードエクスクルーダー〉が、ガラスの破片でかりそめの主を傷つけた〈シンデレラ〉を吹き飛ばす。 遊戯の勝利だ。 『今回のオープニング・デュエルは、本来ならばグランプリのコマーシャル・ガールを務める神月カンナさんが行うはずでした』 決闘の終わりに、MCが粛々と告げた。草原の緑が風に撫でつけられて頭を垂れてしなるように、会場がざわめいた。観客たちの表情は憂鬱そうにかげっており、カンナの安否に関わる不安げな囁き声が揺れている。 『ご存じのとおり、カンナさんは卑劣な誘拐犯の手によって行方不明となっています。武藤遊戯さんは、決闘によって犯人の胸に何かを訴えかけることができればと、急遽カンナさんの代役を引き受けたのです――神月カンナさん誘拐事件について、情報の提供を引き続きお待ちしています』 カメラが栄えある常勝の決闘王を大写しにした。凛々しく引き締まった戦士の横顔だ。宵の空に浮かぶ美しい光を見たような、敬虔な気持ちになる。 彼のカードの扱い方は見事だった。人と精霊の区別もなく気のおけない友人たちと向き合い、共に楽しいゲームに興じるのだという姿勢が、人見知りのデッキとの信頼関係を一瞬で構築していた。 それは彼の生まれながらの才能だ。だからこそ彼は決闘王なのだ。十代は、視界を曇らせていた心配事がどれほどの的外れであったかを再確認した。 決闘のあとでマイクを向けられた遊戯が、薄い液晶パネルを通して、夕焼けのあとに訪れる不思議な空の色の瞳でこちらを見すえた。 『こんなおじさんじゃ華はないから、彼女の代理はつとまらないが。神月カンナさんが一刻も早く無事に解放されることを願っています。もし、彼女を傷付ける人がいたら――』 穏やかで静かな迫力をともなって、遊戯は宣告した。 『ボクは決して許さない』 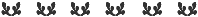 〈「バース・オブ・アルカディア(9)」につづく〉      このコンテンツは二次創作物であり、版権元様とは一切関係がありません。無断転載・引用はご容赦下さい。 −「スクラップトリニティ」…〈arcen〉安住裕吏 12.12.31− |
||
 |
 |
