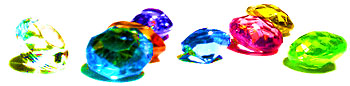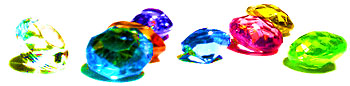透き通った、気高く、何よりも美しい『宝玉の王サマ』。
すっごい皮肉。
*
「宝石獣たちの王様なのに、コウモリの翼、トカゲの手足、不穏な眼の色。なんかイメージ違うな〜」
それというのは、俺の今の所のエースモンスターであるこの宝玉獣の中の宝玉獣、最も気高く美しいダイヤモンドの化身である宝玉王、十代の事だ。俺の家族である他の宝玉獣達は、『純粋』とか『荘厳』とかいうふうな言葉がしっくり来るというのに、このヒト(?)はひとり、濃い夜の匂いを振り撒いている。
まるで――
まるで、悪い夢に登場する悪魔のように。
「がっかりしたか?」
「あー…いや、そういうわけじゃ」
「顔に書いてある」
鋭い。
十代はとくに怒った様子も堪えた様子もなく、いつものようにどうでも良さそうに肩を竦めて見せた。俺に関しては、いつもこのヒトは『どうだっていい』だとか『気にしない』というスタンスを保ち続けている。
「……いいぜ。お前の好みに合わなければ、使わなきゃいいんだ。無理にデッキに入れる事はないさ。オレも楽できるしな」
宝玉王ダイヤモンド。攻守0、特技はナイトメア・ペイン。高位モンスター。十代は身を乗り出して俺と鼻の先で顔を突き合せ、軽薄っぽい感じで言った。
「これでも時価数億円の身だからさぁー。もしもの時の備えになるぜ?」
モンスターカードが持ち主の俺に身売りを持ちかけるな。
「なんで君はそんなアバズレなんだ。一応王様だろ」
十代は悪びれもしないでニヤニヤしている。
「あーあ、つれねェの。ヨハンは他の宝玉獣達にはすっげー優しいのに、どうしてヨハンと同じヒト型のオレには冷たいんだろうなァ。あー、ヨハンは何だかんだ言って、結局人間嫌いだもんなぁー。線引きが上手くて要領もいいから誰も気付かないけど、異端者は『ふつう』に傷付けられた思い出を消せない。動物だって、一度だって自分に危害を加えようとした奴は、一生天敵だもんなァ。それで精霊と人間の架け橋になりたいなんて言うんだよなァ。おもしれーよなァ?」
十代は俺の首に腕を回して、心底軽蔑したような、馬鹿にするような、蟻でも観察するような目で、俺の背中をばしばしと叩いた。
「オレ達精霊が見えるって位で、なーにがトクベツだか! 何が偉いんだか? 悔しかったらツノでも生やしてみろって!」
「……あんまり俺の心の闇を覗かないでくれ」
この悪魔族め。なんでこんな奴が、あんなにきれいな宝石の王様の化身なんだろう。
十代は、俺の心のなかを見透かすように目を細めた。
「オレはみにくいから、ひどいやつだから。悪魔だから。そういうもんなんだ。しょうがないと思ってくれよ」
……俺は、まだこいつに認めてもらってねぇんだろうな。さすが王様。ガードが固いというか、何と言うか。
いつか俺がこいつのお眼鏡に適う事なんてありえるんだろうか?
――いいや、考えたってしょうがない。だから俺はただ、譲れないところだけを十代に提示しておくにとどめた。
「ひとつ訂正しておく」
「なに?」
「俺の家族は誰も醜くなんかない」
十代は俺の事を探るような値踏みするような、疑り深い眼で一瞥した。それから言おうか言うまいか迷うような素振りを見せた。この性悪で辛辣な快楽追及者には珍しいと言える。
「そのさ、その『家族』ってのの――」
十代は言葉を濁して、俺からすっと目を逸らした。
「いいや、何でもねぇよ。あーあ、バッカみてェ」
肩を竦めて、どうでも良さそうに言う。いつものように。
きっと『ただちょっと精霊の姿が見えるだけで、特別でも何でもない(十代談)』俺は、彼にとっては取るに足りない、些細な、ちっぽけな生き物なんだろう。
それが、十代のスタンスが、人間の中で異端児として特別視されてきた俺の事をどんなに救ってくれたか。この悪魔族の男女は微塵も知らないだろうし、欠片も気にしてはいないのだ。たぶん。
十代が、初めて出会ったあの日から、カードの持ち主の俺を主と呼んでくれたことは一度もない。
敬意も、誠意も、優しさも何もない。
そんな十代にどうしようもなく惹かれる俺は、時々、蛍光灯にぶつかってパチパチと音を立てる、みじめな羽虫のような気持ちになる。
|