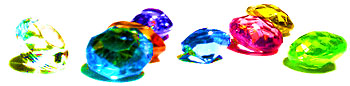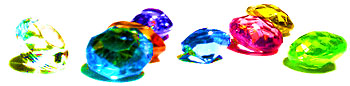『俺の家族は誰も醜くなんかない』
――その『家族』のなかにオレも入っていますか、マスター。
ヨハン。
エメラルド色の、きれいな――。
*
「気に入った子を困らせて遊ぶのは、貴方の悪い癖だと思うわ」
「アメジスト」
大会の最中はホテル暮らしが続く。ヨハンはふかふかのベッドに仰向けに寝転んで、だらしない格好で夢の中だ。家族がいつも傍にいる。その事がヨハンを安心させる。だからヨハンは大抵、どんな時でも、どんな場所でもリラックスしている。
寝相の悪いヨハンが蹴り飛ばしたシーツを掛け直してやる事を諦めて(オレ達精霊は現実世界において、余程のエネルギーが無ければモノには触れないのだ)、馴染みの薄紫色の猫に向き直った。ニヤニヤ、笑う。
「だってさぁ、オレ達の事が見える人間だぜ。レアだ。デュエルも強い。からかえばそれなりの反応を返してくれる正常な青少年だ。どうもオレの事が苦手みてぇだけど? 楽しくてやめらんねぇんだよ。嫌われるのは自業自得さ」
ニヤニヤ。
しかしアメジストは笑い返さないし、『もう、あまりヨハンをいじめないで。大人げないわね』もない。
「……なんて、なァ」
鏡台の中には映らない、オレのニヤニヤ笑いが、歪んで崩れる。
「ヨハンは真面目で真っ当ですごくいいやつだからさ。こいつはオレを好きにならないほうがいい。わかるだろ。……きっとつらい」
アメジストが長い睫毛を伏せた。
「ねぇ」
「なに」
「みにくい身はみにくい心を表すというけれど……はじめにそう言い出した奴を八つ裂きにしてやりたいわ」
「おっかねぇよ、アメジストは」
アメジストの紫色のきれいな眼が、まっすぐにオレを見上げる。
まっすぐに、ヨハンみたいに。
「貴方はきれいよ。ヨハンと同じくらい」
「………」
オレは鏡に映らないけど、たぶんすっげぇ子供っぽくて、すっげぇ間抜けな、馬鹿みたいな顔をしていただろう。自分の顔だ。そのくらいは分かる。何というか、何か大きな動物に引っ掴まれて振り回され、ぐちゃぐちゃにされちまう小さな子鼠のような、そんな気持ちになった。
「サンキュ、アメジスト」
アメジストの首に抱き付いて、つやつやの毛皮に頬擦りする。彼女は、今日はいつものように怒ったりはしなかった。
「ありがとう。うそでも、うれしい」
|