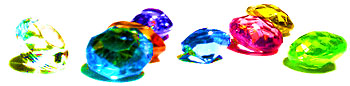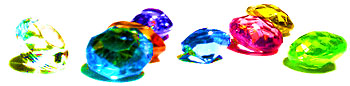――昔むかし、ひとりでふたりの悪い悪魔がいました。
――いたずらが大好きな悪魔は神様が眠っているうちに身体を7つに割り、あちこちにばらまいてしまいました。
――でも怒った7つの神様が、悪魔の身体をふたつに裂いて、ひとつをダイヤモンドの宝石の中に閉じ込めてしまったのです。
――悪魔をとじこめたダイヤモンドが砕けると、ばらばらになっていた宝玉の神様は復活して、悪い悪魔ももとどおり。
――全部が正しい形に戻るのでした。
――めでたしめでたし。
*
レインボー・ドラゴン。七色の宝玉の力の結晶。その真の力が解放された時、ヨハンも気付いただろう。
『八色目』のオレはイレギュラーだった。存在価値のない王で、悪魔だった。
そして今、敵として目の前にいる存在もまた、悪魔だった。
まるでオレと鏡合わせのように同じ、異形の、人の心を食らう、化物だった。
ユベル。悪夢と罪の象徴。
「……十代。君は一体何なんだ?」
ヨハンが言う。声は固く、ヨハンの困惑がありありと伝わってくる。
「どうしてあいつはあんなにも君に似てる? どうして君を知ってる?」
ユベルが子守唄でも唄うように言う。あの頃のように。
「王はただの枷。神を縛る鎖」
隠そうともしない愛情を湛えた、オレと同じちぐはぐの目で、手を差し伸べる。
「おかえり、愛しい十代。やっとボクのもとへ帰ってきてくれたんだね」
ユベル。オレの半分。ひとつに戻るのが、すべての正しい形。
ヨハンがレインボー・ドラゴンを手に入れた今、オレがヨハンのもとにいる理由はなにもない。ダイヤモンドなんてもうとっくに砕けてしまった。オレはもう宝玉の王なんかじゃない。
ただの、一匹の――悪魔だ。
「……十代。どうしてなんだ? そんな奴の所に行くんじゃない!」
ヨハンの制止を聞かずに、迷わずユベルの手を取った。
オレはたぶん、何の表情も浮かべてはいなかったろうと思う。これは自然な事だった。正しい事だった。
自分が自分に還る事。そんなの、あたりまえだろ?
オレは振り返って、ヨハンにいつもの目を向ける。家族に向けるものでは決してない目。侮蔑、軽視。そして無関心。お前の事なんてどうだっていいんだ、ってやつ。
「……ずっと」
――すきだった。
はじめて見た時から、なんてきれいな人間なんだろって。
オレと似ているようでオレとは違い過ぎて、オレが大っ嫌いなオレから遠過ぎて、いとしくて。
いとしくて。
だから、何があっても護ってやろうと決めた。
「ヨハン。お前の事なんかだいっきらいだった」
ヨハンが目を丸く見開き、そして胸に鋭いナイフが食い込んだような顔をする。
ユベルが嬉しそうに微笑む。
もしも、もう一度ヨハンと会う時には――オレは、本物の悪魔になってるだろう。
主人の事も分からない、ただの獣に成り下がっているだろう。
お前に害を与える邪悪な精霊に堕ちているだろう。
闇を統べるものに。
血塗られた覇王に。
お前に出会う前の、闇の中にいたオレに。
その時は容赦も遠慮もいらない。
お前の光で、オレをつらぬけ。
「もう二度とお前の顔なんか見たくない」
ずっと遠くから見ていただけで、辛い時に優しい言葉のひとつも掛けてやれなかった。
ニヤニヤ笑いながら見てるだけだった。
そんな奴は、欠片も家族なんかじゃなかった。
だから――へいきだろ?
「……君は、悪い奴だった?」
ヨハンが呆然とした、焦点のぼやけた目でオレを見る。ヨハンの目に映るオレは、優しい心もなく、人を愛することもできない、完璧な悪魔の顔をしていた。誰よりもみにくかった。
「今更何言ってるんだよ。相変わらずボケた奴だな」
「俺達を騙していたのか?」
「ああ、そうだよ」
「本物の、人を傷つける悪魔だったって言うのか」
「ああ。お前の心の闇も食ってやりたかったけど」
オレはいつものニヤニヤ笑いを浮かべて、かなうかぎりのつまらなさそうな声で、「気分じゃない、吐き気がする」と言ってやった。
「馬鹿な子供。何も知らずにオレの主人気取りでさァ。きれいだとかなんだとか、そんなつまんねェ事は人間に言われても気持ちわりぃだけだ。お前はただオレのカードを持ってただけ。オレはお前を主だなんて認めてない。だから――」
光は光へ、闇は闇へ。
「あとはまかせろ。元の世界へ帰れ。皆で、仲間と共に」
全部が正しい姿に戻る。
ヨハンは元の世界へ戻り、家族と一緒に、いつものように楽しくやっていくだろう。オレがそばにいた事も忘れ、やがて今より大人になり、家族に看取られて死んでいく。
優しい奴は、優しくされるべきだ。ひどい奴がひどい目に遭うように。
正しい奴は、光の中にいるべきだ。悪い奴が闇に呑まれるように。
悪い奴は、いい奴に倒されるべきだ。
いいやつは、幸せになるべきだ。
ハッピーエンド。
オレとヨハンはどこまでも交わらない。
オレはみにくいから、民も敵も皆オレを悪魔と呼んだ。
お前もそう呼んだ。
でも。
ありがとう。
オレのこと見てくれて。
声聞いてくれて。
ヨハンの目は、オレに裏切られても曇ったりはしなかった。澱まず、澄んでいた。まるで透き通った海のように、冬の青空のように、生命溢れる緑の森のように。宝石よりも宝石のようなきれいなエメラルドの眼で、しっかりとオレの事を見つめていた。
「……君が悪い奴でも、それでも君は俺の家族で、宝玉獣たちの王だ。待ってろよ。必ず連れ戻してみせる。その責任がある。覚悟も」
ヨハンは言った。
「俺は君の主だ。君は俺が守る」
ヨハンは、オレの話を全然聞いていなかった。
まだオレを信じていた。
オレを家族と呼んでいた。
オレは――オレは、ヨハンに出会ってから、もう何年も、それが恐ろしくてたまらなかった。
怖くて仕方なかった。
ずっと脅えていた。
「嘘ついても、騙しても、俺は君を赦す。何度でも赦してやる。だって、大切な家族なんだから」
「……黙れよ、馬鹿野郎」
だまれよ。
頼むから、もう何も言うなよ。
心も肉体もオレはみにくいから。
そんなにきれいな感情をぶつけられたら、泣いてしまうだろ。
ばかやろう。
ヨハン。
ヨハン。
……すき。
だいすき。
人間だったら、一緒に高校生やって、触れ合えて、せめて――ともだちになれたのかな。
……なあ?
――オレを。
……オレを殺してください、マスター。
|